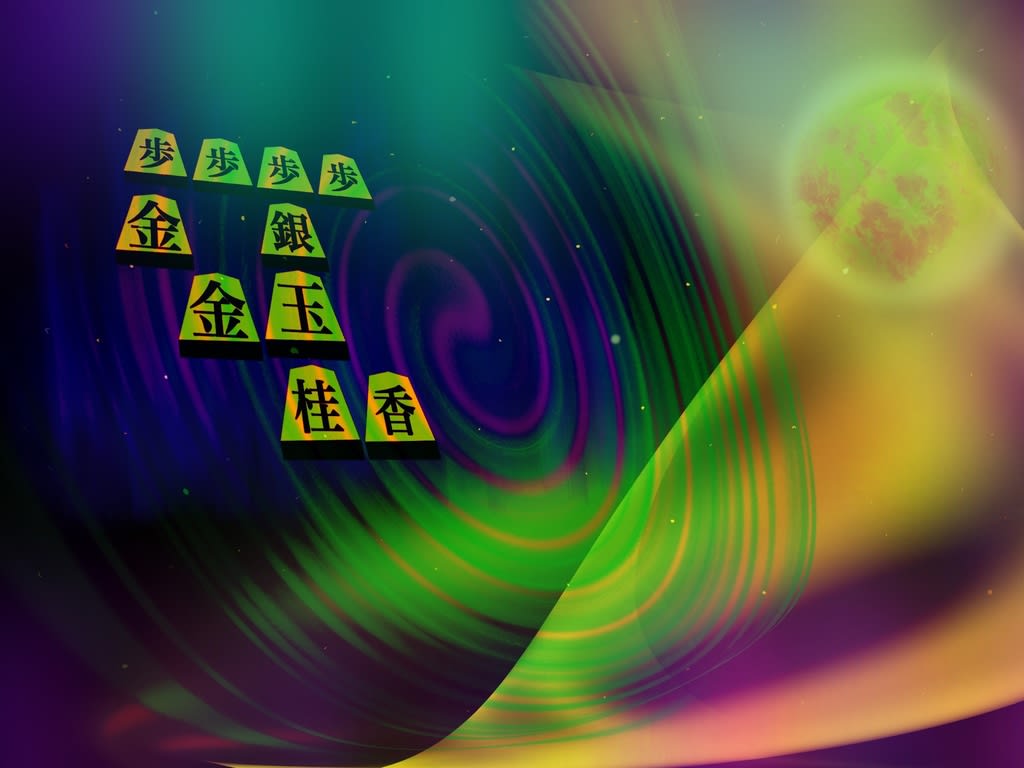
わるい局面では一手も勝ちがない。(相手を楽にさせないことが望まれる)ぎりぎりの局面では一手しか勝ちがない。
よい局面では、勝ち方が何通りも存在することがある。その意味では最善手は1つではない。勝ち方を選ぶ自由が許されるのだ。(また、将棋の局面には絶対地点と分岐地点が存在するようである。例えば、駒が当たっている時にはこの一手であるという傾向が顕著だが、割と手が広くどれを選んでもそうわるくならないという局面がある)
どこからどのようにして勝つか。よい局面では考えることができる。
その時にこそ人間が出る。(個性を出せる)
AIにとっての最短ルートをなぞる必要はない。
人間には「この一手」として見逃さない一手と、全く発想の外に出てしまう手が存在する。自分にない手で将棋を作ることはできない。人間にとっての強さとは、自分を知ることだろう。
自分にとって明るい道を行くことだ。
「最善手はお前が決めろ!」
そう言って棋神が僕を突き放す。
~AIの寄せを真似することはない
ソフトの推奨する最善手を人間が引き継ぐことはない。人間には人間同士の戦いがあり、人間なりにやった方がいい。ソフトは1秒で億の手を読めるが、人間は一瞬にして何も読むことなく悟れるし、感じることができる。人間には人間の領域があって、人間と人間の戦いの中では、人間力を頼るべきなのだ。
AIの寄せをみていると持ち駒をため込んで一気に詰まし切るような傾向を多く感じる。(そこで駒を取ってるのか。何か温いな。でもよくみるとこれでちゃんと詰んでいますよみたいなことがある)詰む詰まないがはっきりわかるから何の問題もないのだろうが、人間的にみていると少し「危なっかしい」とも思える。最終的に将棋は詰む詰まないのゲームだから、そこの読みの精度の差はどうしようもないが、短い時間の将棋の中で詰みを読み切るというのはとても大変だ。(そればかりか慌てている状況では、初歩的な詰みさえ見逃してしまうのだし)だけど、詰ますことが絶対じゃない。状況が許す限り、別に詰まさなくてもいいではないか。
人間的にわかりやすい順であることが何より大切だろう。玉を包むように寄せるとか、下段に落とすとか、基本に沿った方がいいと思う。
人間にとってわかりやすい寄せは、自玉を瞬間的にゼット(絶対に詰まない形)の状態にして、敵玉に必至をかけることだ。
・
明け方の将棋ウォーズで振り合った
ライバルは香一枚強い
(折句「アジフライ」短歌)















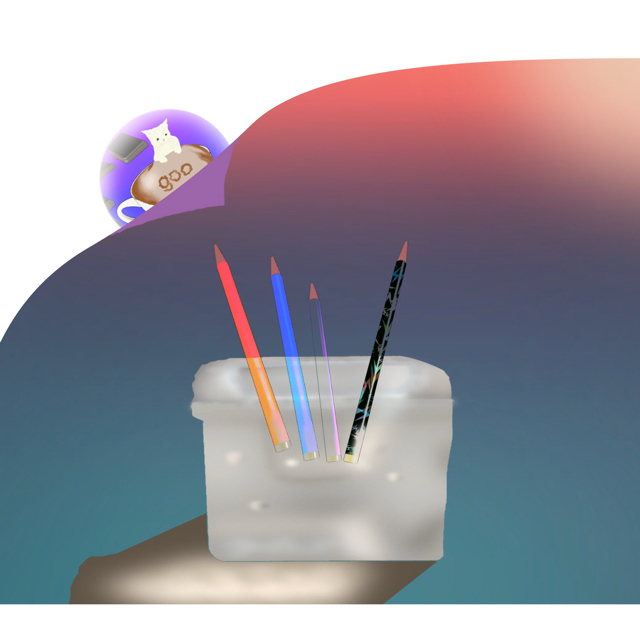

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます