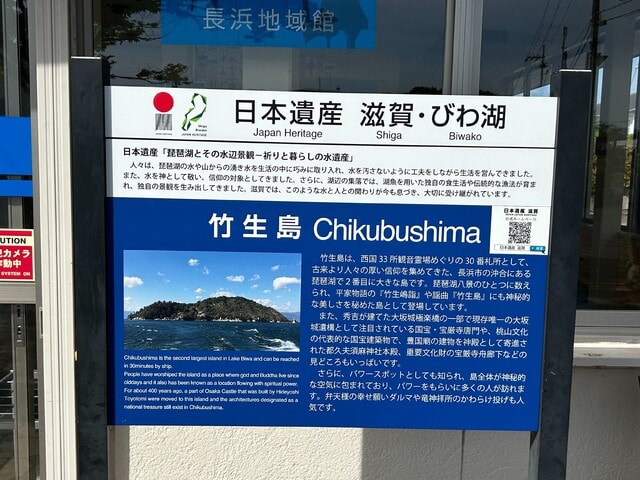筑波山99回目の登山の後は、筑波実験植物園へ。TXつくば駅で自転車を借りて、約10分で到着。自販機で入場券を買ったが、受付で65歳以上は無料だと知る。マイナカードを出して確認、返金してもらう。
この植物園は2回目。今日は、森林インストラクターのテキストに出ている植物のうち主要なもの80種、できるだけ多く実物を確認しようというものだ。この植物園は珍しい熱帯の植物もあるが、私は主にどこでもある温帯の普通の植物を観る。
ただし、2,3は珍しい植物をチェック。まず、筑波山の固有種、ホシザキユキノシタ。1ヶ月ほど前に来た時、花が咲いていたが、まだ咲いてる。

もうひとつ、エゴノキ。この植物にはオトシブミという昆虫の住処がぶら下がっている。写真のピンボケになっている部分。

ここからは、森林インストラクターの学習。
サンショウ、青い実がついてる。落葉低木、鋸歯、葉は羽状複葉、棘がある、香りがよく食用。ペアで出題されるのはカラスザンショウ。葉の先は尾状に尖る、サンショウのように価値はない。

ネズミモチ、常緑広葉樹、全縁、対生。葉は常緑4~8cm、光にも透けない。ペアで出題されるのは、トウネズミモチ、違いは葉を光に指すと透ける。

ツクバネガシ、常緑広葉樹、互生、樹皮は黒褐色、葉はアカガシより短く、先端は鋸歯。ツクバネって羽子板の羽根のこと。関連して出題されるのは、アカガシ、シラカシ、ウラジロガシ、ウバメガシ、アラカシなど。カシ類の出題は幅広く、苦手。

アラカシ、枝が太く武骨から名がついた。葉は最も幅広、途中まで鋸歯で先端が尖る。

モミ、クリスマスツリーだ。樹皮は灰色、若木は先端で二裂。モミ・ツガ林を形成、大気汚染に弱く都市部では少ない。ウラジロモミは葉の 先端が二股、ツガはわずかにくぼむ、トウヒは一本と違う。

エノキ。落葉広葉樹、互生、葉は上半分が鋸歯、表面はツヤ。果実は赤く熟す。虫食いが多い、美しい昆虫が集まり餌にする。枝を大きく張り出し日陰を作ることから、一里塚の木。ペアで出題されるのは、ムクノキ。葉は全体が鋸歯で、表面はざらつく、ヤスリに使った。果実は黒く熟し、ムクドリが好む。

コナラ。落葉広葉樹、鋸歯、互生。暖温帯、幹はミズナラより深い割れ目、葉柄は1cmと長い。葉芽の先から土用芽(ラマスシュート)が出る。雑木林の代表、薪炭林、カブトムシ。ペアでの出題は、ミズナラ。冷温帯、葉は大型で荒波のような鋸歯が目立つ、葉柄は短い。

オオバボダイジュ。落葉広葉樹、互生、鋸歯。葉が大型、葉先が長く伸びる、裏面に白い星状毛が密生。ペアで出題は、シナノキ。葉は小さく、無毛。

最後はカラマツ。葉が柔らかく痛くない。

樹木の特徴、だいぶ覚えたな。実物を見るのが一番、また来よう。