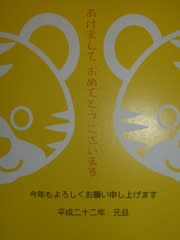ふと、というか、つい、というか、このブログを始めてしまったのが2008年4月のことだ。
自分なりの記録にでもなれば、という軽い気持ちだった。
あと3ヶ月で丸2年になる。
ふだん三日坊主が得意なので、自分でもびっくりだ。
しかもアクセス数のカウンターを見たら、閲覧数のトータルが約18万。訪問者数が7万人を超えていた。
有名な方々のブログの数字は途轍もないものだが、一個人である私にとって、7万人は大変な数だ。
何しろ、私の故郷の町の人口が約6万7千人。市民全員が一度は訪問してくれたことになる。
すごいじゃないですか(笑)。
また、知り合いの中には、「見てますよ」と言ってくれる人もいて、私が、いつ、どこで、どんなことをしているのか、本人よりも詳しかったりする(笑)。
このブログのおかげで、物理的には離れた所にいる方々も、自分を見守っていてくださるような気がして、とても有難い。
たかが7万人、されど7万人。
今年も引き続き、気張らず、楽しみながら、専門であるテレビを中心に書かせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。