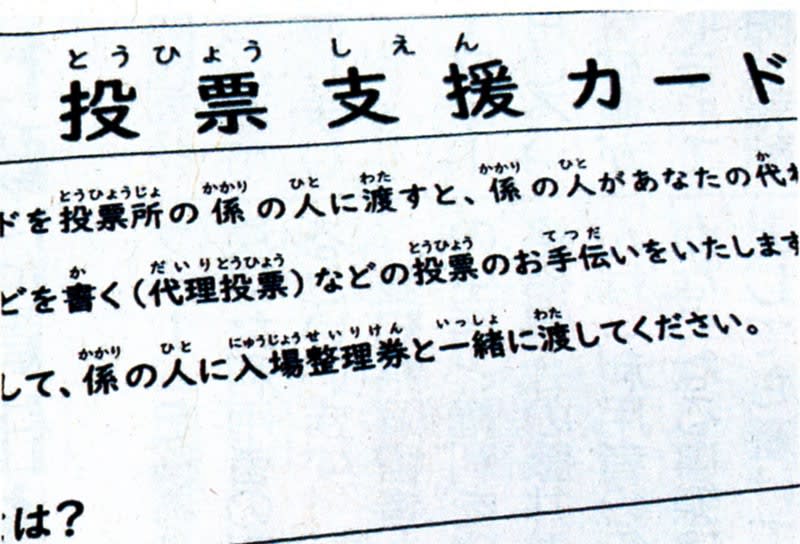検証 維新「身を切る改革」⑦ 議員定数削減 民意切り捨て
「身を切る改革」の名で維新がやろうとしていることに、議員定数削減による民意の切り捨てがあります。
「まず議員が身を切る改革を実践し覚悟を示す」として「国会議員定数の3割削減」を主張。馬場伸幸代表は「国会議員は半分でも十分。衆参を合併する形で一院制にする」とまで言っています。
有権者を「切る」
議員定数削減は国民の政治参加の権利を削り、多様な民意を切り捨てることです。行政をチェックする議会機能を弱めることにほかなりません。
第一に、憲法は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すると明記し、「国権の最高機関」と位置付けています。国会に多様な意見が反映することが大切です。「身を切る改革」で議員定数を削減するなどは暴論です。
上脇博之神戸学院大学教授は「議員定数を削減すれば、衆参の少数派が減り、内閣・政府を監視・批判する勢力が少なくなり、内閣・政府の地位を事実上高め、『国権の最高機関』である国会の存在意義の低下を招き、議会制民主主義に反する」「『主権者の身』を『切る改悪』なのです」と指摘しています。
維新による府議会、市議会の定数削減に関する「読売」社説(7月4日付)も、「看板政策の『身を切る改革』の実績を重ねることで支持を広げる狙いがあろう。議員の政務活動費などに無駄があれば削減することは大切だ。だが、議員が少なければ少ない方がいい、と言うなら住民の代表は不要になってしまう。定数削減は、少数派の声を議会に届きにくくさせる。効率化を至上の目的とするようでは民主主義の根幹が揺らぎかねない」と指摘。
東京新聞も「議員定数の削減なら、有権者の代表として行政監視や政策立案に取り組む人数が少なくなるのと同義だ。どれだけ聞こえが良くても、負の影響が生じる可能性も含めて慎重に見極める必要がある」との冨田宏治関西学院大教授の忠告を掲載しています。

下から3番目
第二に、今の日本の国会議員定数は、他国と比べて、もっとも少ない国の一つです。
参議院常任委員会調査室・特別調査室の経済のプリズムコラム「『議会の大きさ』について~OECD諸国における比較~」(2021年12月)は、「第一院(下院)についてみると、日本の衆議院は人ロ100万人当たり3・7であり、OECD諸国の中では米国とコロンビアに次いで少ない方から3番目。G7諸国と比較すると、日本は米国を除く英独仏伊加の5カ国のそれぞれの2分の1以下の規模となる」「第二院(上院)を加えた定数で比較してもおおむね同様の傾向となっている」と指摘しています。
今でも少ない国会議員の定数削減などすべきではありません。
第三に、「身を切る」というのなら、年間約320億円もの政党助成金(税金)こそ廃止すべきです。維新は本部収入の8割は政党助成金です。政党助成金が入る政党支部で高級料亭やフランス、イタリア料理店等で飲食し、スーツ代やアスレチッククラブ会費まで支出しています。税金にどっぷり漬かり、野放図な使い方をしながら「身を切る改革」「議員定数削減」を口にする資格はありません。
やるべきは、議員定数削減ではなく、政党助成金の廃止です。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年10月20日付掲載
議員定数削減は国民の政治参加の権利を削り、多様な民意を切り捨てること。行政をチェックする議会機能を弱めることにほかなりません。
参議院常任委員会調査室・特別調査室の経済のプリズムコラム「『議会の大きさ』について~OECD諸国における比較~」(2021年12月)は、「第一院(下院)についてみると、日本の衆議院は人ロ100万人当たり3・7であり、OECD諸国の中では米国とコロンビアに次いで少ない方から3番目。G7諸国と比較すると、日本は米国を除く英独仏伊加の5カ国のそれぞれの2分の1以下の規模となる」「第二院(上院)を加えた定数で比較してもおおむね同様の傾向となっている」と指摘。
「身を切る」というのなら、年間約320億円もの政党助成金(税金)こそ廃止すべき。
「身を切る改革」の名で維新がやろうとしていることに、議員定数削減による民意の切り捨てがあります。
「まず議員が身を切る改革を実践し覚悟を示す」として「国会議員定数の3割削減」を主張。馬場伸幸代表は「国会議員は半分でも十分。衆参を合併する形で一院制にする」とまで言っています。
有権者を「切る」
議員定数削減は国民の政治参加の権利を削り、多様な民意を切り捨てることです。行政をチェックする議会機能を弱めることにほかなりません。
第一に、憲法は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すると明記し、「国権の最高機関」と位置付けています。国会に多様な意見が反映することが大切です。「身を切る改革」で議員定数を削減するなどは暴論です。
上脇博之神戸学院大学教授は「議員定数を削減すれば、衆参の少数派が減り、内閣・政府を監視・批判する勢力が少なくなり、内閣・政府の地位を事実上高め、『国権の最高機関』である国会の存在意義の低下を招き、議会制民主主義に反する」「『主権者の身』を『切る改悪』なのです」と指摘しています。
維新による府議会、市議会の定数削減に関する「読売」社説(7月4日付)も、「看板政策の『身を切る改革』の実績を重ねることで支持を広げる狙いがあろう。議員の政務活動費などに無駄があれば削減することは大切だ。だが、議員が少なければ少ない方がいい、と言うなら住民の代表は不要になってしまう。定数削減は、少数派の声を議会に届きにくくさせる。効率化を至上の目的とするようでは民主主義の根幹が揺らぎかねない」と指摘。
東京新聞も「議員定数の削減なら、有権者の代表として行政監視や政策立案に取り組む人数が少なくなるのと同義だ。どれだけ聞こえが良くても、負の影響が生じる可能性も含めて慎重に見極める必要がある」との冨田宏治関西学院大教授の忠告を掲載しています。

下から3番目
第二に、今の日本の国会議員定数は、他国と比べて、もっとも少ない国の一つです。
参議院常任委員会調査室・特別調査室の経済のプリズムコラム「『議会の大きさ』について~OECD諸国における比較~」(2021年12月)は、「第一院(下院)についてみると、日本の衆議院は人ロ100万人当たり3・7であり、OECD諸国の中では米国とコロンビアに次いで少ない方から3番目。G7諸国と比較すると、日本は米国を除く英独仏伊加の5カ国のそれぞれの2分の1以下の規模となる」「第二院(上院)を加えた定数で比較してもおおむね同様の傾向となっている」と指摘しています。
今でも少ない国会議員の定数削減などすべきではありません。
第三に、「身を切る」というのなら、年間約320億円もの政党助成金(税金)こそ廃止すべきです。維新は本部収入の8割は政党助成金です。政党助成金が入る政党支部で高級料亭やフランス、イタリア料理店等で飲食し、スーツ代やアスレチッククラブ会費まで支出しています。税金にどっぷり漬かり、野放図な使い方をしながら「身を切る改革」「議員定数削減」を口にする資格はありません。
やるべきは、議員定数削減ではなく、政党助成金の廃止です。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年10月20日付掲載
議員定数削減は国民の政治参加の権利を削り、多様な民意を切り捨てること。行政をチェックする議会機能を弱めることにほかなりません。
参議院常任委員会調査室・特別調査室の経済のプリズムコラム「『議会の大きさ』について~OECD諸国における比較~」(2021年12月)は、「第一院(下院)についてみると、日本の衆議院は人ロ100万人当たり3・7であり、OECD諸国の中では米国とコロンビアに次いで少ない方から3番目。G7諸国と比較すると、日本は米国を除く英独仏伊加の5カ国のそれぞれの2分の1以下の規模となる」「第二院(上院)を加えた定数で比較してもおおむね同様の傾向となっている」と指摘。
「身を切る」というのなら、年間約320億円もの政党助成金(税金)こそ廃止すべき。