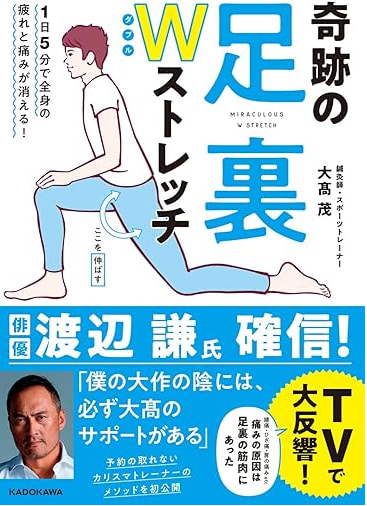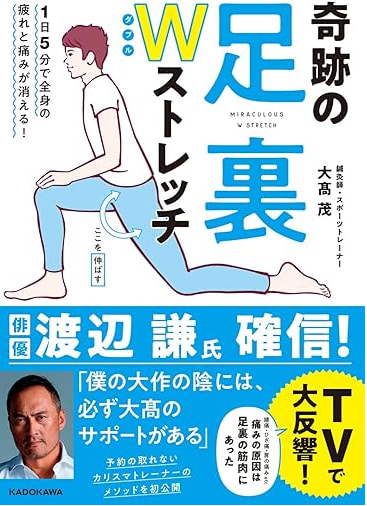
身近な知人が「ぎっくり腰」で苦しんでいるので、メモしておきます。
p.56 整形外科的に見ると、腰を支える筋肉や肩に痛みがあるので、
痛み止めと湿布を処方されますが、原因は腰以外にある機能的疾患
であることが多いのです。ヒスタミンと言う痛みを感じる物質が
出ているので、痛いのは事実ですから、痛みを軽減させるためには
p.57 アイシングが有効です。つまり、お医者さんが湿布をくれるのは、
痛みを抑えるためであって、治すためではありません。
こうしたこともあって、ぎっくり腰は冷やすのがいいと思い込んで
いる人も多いのですが、冷やさない方が良い場合もあります。
冷やすのは痛みを抑えるためであって、治すためには、硬くなって
しまった。筋肉を温めた方が良いのです。
ぎっくり腰のきっかけは、くしゃみをした時が一番多いのですが、
打撲や捻挫とは違い、本来はくしゃみをしただけで炎症など起きません。
ぎっくり腰とは、腹筋の1番深い位置にある「腹横筋」に力が入らなく
なる症状なのです。
腹横筋は、帯状に内臓を包み込むように発達している筋肉で、
コルセットのように体幹と腰回りを安定させてくれています。
座る時、立つ時、歩く時、そして足を上げる時、このです。
ぎっくり腰の人には、施術の後に腹式呼吸をやってもらいます。仰向けに
p.58 横になった状態で、鼻からゆっくり息を吸って、お腹の腹横筋を膨らませて、
次に、息を吐きながら凹ませます。この運動を何回か繰り返し行います。
その後、凹ませた状態をキープしたまま運動をしてもらいます。
鍼治療だけで終わるのではなく、正しく使えていない筋肉を動かしてあげる
トレーニングも大切だといえます。
私の教室では先日、この腹横筋が使えていない女性がいたので、びっくり仰天。
お腹全体を床に押し付ける動作ができないので、色々試した結果、
笑いヨガのように「無理やり大笑い」したら理解できた!という笑い話のような話。
長年教室に参加していても、簡単なことが出来ていないことがあり、驚きます。
それでも「教室が楽しくて、体調がイイから生き甲斐になっています」とのこと。
喜んでいいのかどうか、悩んでしまいます。