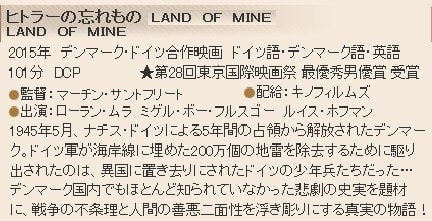面白いですが、秀作とはとても言えません。
遠藤周作の原作をイタリア系アメリカ人・マーティン・スコセッシが監督しました。
冒頭から不思議を通り越して違和感いっぱいでした。
いかにアメリカ映画と言っても、スペイン人のカトリック司祭が英語を話し、日本の役人、牢屋の看守、農民も皆
流ちょうな英語を話すんです。
何とも不自然、言語そして音は大事です。私は出だしで「転ばされた」感じでした。
ただその一点で、この映画は大失敗作です。
そのことは置いて、日本へのキリスト教の伝搬と普及、そして在来の日本の宗教、仏教・神道の関係は、
私には複雑過ぎて良く理解できないことが多いです。
一口に日本の仏教と言っても密教、鎌倉時代以降の新興・大衆仏教と支配階級の武士の禅宗など様々な宗教があります。
キリスト教が、日本と日本人の一部であっても広がることが出来たのはどうしてでしょうか?
日本へのキリスト教の伝搬について、当初、支配階級はとても緩やかだったそうです。
それは、貿易などの経済活動から得る利益の方がはるかに大きく、キリスト教に改宗した大名もたくさんいました。
しかし、西洋と日本の生活習慣の違いは大きく、言葉の壁は厚く高いものでした。ゼウス・神は大日と説明したそうです。
仏教の大日の意味は色々あるようですが元は宇宙の真理ということで、決して太陽を意味してはいません。
八百万の神の日本でも、太陽信仰・天照大神は特別です。ゼウス・神は太陽と同じだと言うわけです。
また日本に入ってきたのは、プロテスタントではなくキリスト像や十字架など偶像崇拝を認めるカトリック
だったことの意味も大きいと思います。
文字を知らない民衆にとって、目に見える偶像・絵の存在は大きいです。
とりわけ日本では、仏像、絵巻などは大きな力を持っていました。
戦国末期から江戸初期にかけて、在来の仏教勢力は大きな力を有していました。
石山本願寺、比叡山などは封建体制・大名を脅かし、武家秩序を根底から覆すほどの力、持っていました。
一向宗では阿弥陀様に帰依し、南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば、死後極楽浄土に行くことが出来ると信じられました。
それは、あたかもムスリムの一部のジハードや、カトリックの殉教精神にもつながるのではないでしょうか。
とまれ、悪政・身分制の現世は苦痛が多く、苦しむ民衆にとって、死後天国に行ける浄土・阿弥陀信仰とキリスト教殉教は
同じような精神構造だったのではないかと私は思います。
さて、映画に戻ります。
スペインからかつて来た宣教師のその後が不明で、「棄教」したと本国では噂されていました。
その真相を探るために、彼の弟子二人が日本に派遣されます。
そこで彼らが目にしたのは、苛酷に弾圧される民衆でした。
二人の司祭も捕まり、棄教すれば、目の前の日本人切支丹を助けると言われ、苦悩します。
信仰に生きる彼らにしては、棄教より殉教の方が選択しやすいのですが、目の前で信徒が殉教して行きます。

切支丹が処刑されるこのシーンは雲仙の地獄谷でロケされたそうです。
彼らは、「神にどうするべきか?」と問うのですが、神は「沈黙」でした。
彼らの師と仰ぐ宣教師・フェレイラは、目の前の惨劇を回避することが最善であるとし、棄教しました。
旧約聖書の中で、神がモーゼに自らの息子の命を差し出せと試練を与える話しが思い出されました。
また、釈迦は、前世で飢えた飢えたトラの親子に自らの体を投げ出したと言う「捨身飼虎」の話しも思い出しました。
「神は民衆が苦しんでいるのに救いの手を差し出さない、何も語らない」=沈黙なのです。
ヨーロッパ・キリスト社会では、厳しい異端審問・魔女狩りが行われました。
現代でも、想像を絶する民衆への悲劇が日々起きています。
神と宗教世界そして人々はこの問にどう答えたら良いのでしょうか?
この映画、遠藤周作さんはこの重い問を私達に問うていると思います。
162分はどうしようもなく長過ぎます。これがこの映画の第二の失敗です。
ゆっくりな台詞回しは良いのですが、ストーリー展開が余りにゆっくり、同じようなシーンが繰り返され、冗舌です。
映画の冒頭、音が全くしない真っ暗な画面がながく続きます。「サイレント」の暗示なのでしょうが、安易すぎる演出でした。
所々の印象的な低音の音楽は良かったです。 【6月26日】