
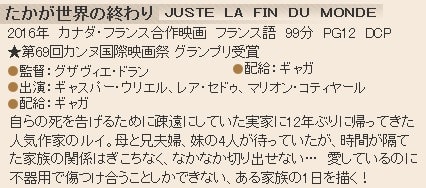
ひどい駄作です。
更に、この大仰な題にはもう二の句がありません。
さて、有名作家のルイが12年振りに帰省した一日のお話。
彼はゲイで12年前に家を出、歳はたしか30代前半です。
理由はわかりませんが死期が近づいた彼は家族にそのことを言いに帰ったのです。
ところが、彼が家に入ると、妹はどうして高いタクシーを使ったのかと延々と大げんか。
次は、兄嫁が子どもの話をすると、兄は下らない話しをするなと大激怒。
母親は、マミキュアをドライヤーで乾かしながら、何か大声で叫びます。
家族中が、全く下らない内容で大声で怒鳴り合いの喧嘩を延々と続けるのです。
ウッデイ・アレンの様にしゃれている会話なら面白いのですが、下らないの一言の内容ですから、もうウンザリ辟易です。
そして、ルイは、何故か激怒した兄の「帰れ」の一言で、ルイは「世界の終わり」を言い出せず帰り、映画は終わります。
この映画では、登場人物の生活感が全く無いばかりか、お互いを思いやるなどという感情も皆無、
おまけにマリファナを吸いまくっています。
カナダ・フランス映画で言葉は、フランス語なのですが、舞台がどこなのか私には、はっきりわかりません。
そして冒頭と最後に英語の歌が流れる奇妙さなのです。
家族は、ルイからたくさんのポストカードをもらっているのに、長い間詳しい音沙汰がないと文句を言っています。
そもそも子どもが成長すれば、家を出るのは当たり前、頻繁に連絡などしないものです。
たった12年なのに、なぜ連絡しないのだと大怒りしているのです。
と言うのに、第69回カンヌ国際映画祭でグランプリ受賞と言うのですから、驚きを通り越して「何てこった」、です。
やっぱカンヌって感じ。カンヌはこうした意味不明の駄作に賞をあげることに自らの存在価値を感じているのでしょう。
「Juste la fin du monde」(ちょうど世界の終わり)と、大それた題を恥ずかしげも無く付けられたものです。
映画は、つくづくギャンブル、大いなる失望・落胆でした。 【7月24日】


















