台風一過で、やや暑さが戻ったが、朝晩はもうすっかり秋の気配だ。夏も終わりである。
夏と言えば、海や山で楽しく遊んだ記憶が(今ではそんな意欲はさして湧かないが 笑)蘇るが、もう一つ、私の妄想が勝手に思い描く心象風景がある。昭和20年8月15日、セミの鳴き声が喧しかったであろう、それだけに松尾芭蕉じゃないけれど静寂さが際立ち、厳粛な「敗戦」の現実を、玉音放送という史上初めて聞く天皇陛下の声を通して受け止めざるを得なかった日のことだ。当時はまだその年末に始まるGHQのラジオ放送を通じた歴史教育による洗脳や、勝者が敗者を一方的に裁くという極東軍事裁判によりナチス・ドイツに準じて日本の軍国主義が否定されるという一種の茶番を知らない、敗戦直後の人たちだ。文字通りの総力戦が終わったという脱力感や開放感があったであろうことは想像に難くないが、その実相は戦後の私たちの想像を遥かに超えている。今に続く戦後日本人の原点である。
昨年、たまたまブックオフで小野田寛郎・元少尉の『たった一人の30年戦争』(東京新聞)を見つけて、この夏、もう一度、読み返した。日本の敗戦を信じないで30年間、フィリピン・ルバング島で「残置諜者」の任務を黙々とこなし、昭和49年3月、かつての上司の投降命令を口達で受けて、ようやく投降された。「一人ぼっちの・・・」は誇大広告で、昭和47年10月までは戦友の一等兵が(更に言うと、昭和29年5月までもう一人、伍長が)一緒だったのだが、いずれにしてもその苛烈さは、陸軍中野学校のお陰なのか、戦前の教育のせいなのか、本人の資質なのか。帰還後、一年足らずで日本を逃げ出し(とは、ご本人が嫌う言い回しだろうが)、ブラジルに移住されたのは、戦後社会への違和感だったのか。この本を読むと、戦後の平和の中で私たちが見失ったものがあるとすればそれは何なのか、思い当たれるような気がして、つい訪ねてみたくなるのである。
最も有名なのは、広島・平和記念公園での次のやりとりであろう(同書P14)。
(引用はじめ) 同行の陸軍中野学校同期生と無言で公園を歩いた。慰霊碑があった。「安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから」 私は戦友に聞いた。「これはアメリカが書いたものか?」「いや、日本だ」「ウラの意味があるのか?負けるような戦争は二度としないというような・・・」 戦友は黙って首を横に振った。日本は昭和二十年、米英など連合国の前に屈服した。しかし私はいま、人間の誇りまで忘れて経済大国に復興した日本に無条件降伏させられているのだ――と感じた。(引用おわり)
帰国を果たして、そのまま羽田東急ホテルで行われた記者会見では、さながら浦島太郎を取り囲んで寄ってたかって珍しがるジャーナリズムの愚かしさと滑稽さが手に取るようであり、まるで絵に描いたようなチグハグさが微笑ましい(同書P194-196、東京新聞の昭和49年3月13日付朝刊記事がそのまま引用されている)。
(引用はじめ)
――三十年ぶりに故国の土を踏み、肉親と対面した心境は。
「やはり自然の山や川の姿は、他国のフィリピンと変わりがないように思われますが、皆様方の住んでおられることを脳裏に思い浮かべますと、見えたところから、すぐ降りて行って土を踏みたい気持ちであります」
――人生の最も貴重な時期である三十年間をジャングルの中で暮らしたことについて。
「(質問者を凝視して暫く考えたあと)若い、勢い盛んなときに大事な仕事を全身でやったことを幸福に思います」
――三十年間、心で思い続けて来たことは。
「任務の完遂すること以外にはありません」
――両親について考えたことはなかったか。
「出掛ける時、両親には諦めてもらっていたので、そんなことは考えませんでした」
――日本の敗戦をいつ頃知ったか。また元上官の谷口さんから停戦命令を聞いたときの心境は。
「敗戦については少佐殿から命令を口達されて初めて確認しました。心境はなんとも言いようのない・・・。(うつむき加減で、力なく言葉が途切れかけたが、再び顔をキッとあげると)新聞などで予備知識を得て、日本が富める国になり、立派なお国になった、その喜びさえあれば戦さの勝敗は問題外です」
――小塚さん(一等兵)の死で山を下りる心境になりましたか。
「むしろ逆の方向です(ムッとした表情)。復讐心の方が大きくなりました。二十七、八年も一緒にいたのに、“露よりもろき人の身は”と言うものの、倒れたときの悔しさと言ったらありませんよ(唇を震わせ、絶句)。男の性質、本性と申しますか、自然の感情として誰だって復讐心の方が大きくなるんじゃないですか」(引用おわり)
私たちは、勝てそうにない戦争をなぜ仕掛けた!?と教え込まれているが、次のようなくだりもある(同書P36)。三十年という年月をものともしなかった所以であろうか。洗脳と呼ぶのは簡単だが、狂気の中とは言え、京都学派の哲学科の教授たちだって、いったん始まった以上は国民として協力し、「共栄圏の論理」「世界史の哲学」を真面目に論じる真摯さがあったことを忘れることが出来ない。
(引用はじめ) 私は陸軍中野学校で「大東亜共栄圏完成には百年戦争が必要だ」と教え込まれてきた。陸軍参謀本部内の一部には開戦当初から「これは勝てる戦争ではない」という見方もあった。勝てない戦争なら、負けないように戦えばいい。アメリカは民主主義の国だ。戦争がいつ果てるともない泥沼状態と化し、兵が死に、国民生活が疲弊すれば、アメリカ世論は反戦、厭戦に傾く。日本はそれを計算し、降伏でなく条件講和に持ち込む戦略だ、と考えていた。(引用おわり)
小野田さんには、別の本でゴーストライターだった作家の批判的な声もあるようだ。その方は、小野田さんが「戦争の終結を承知しており残置任務など存在せず、1974年に至るまで密林を出なかったのは『片意地な性格』に加え『島民の復讐』をおそれたことが原因であると主張している」(Wikipedia)そうだ。それだけのために、三十年という年月は重過ぎないだろうか。その息子さんは、「冷酷で猜疑心の強い人だった」(同)と述べている。確かに、小野田さんには、かつて父親に反抗ばかりしていたとは言え、三十年ぶりに帰還して、タラップを下りて、「目の前に年老いた父と母がいた。(おやじもおふくろも年をとったなあ)と思っただけで、何の感激もなかった。私はこの三十年間、肉親の夢を見たことは一度もなかった。戦場では故郷や肉親の話はタブーだった。肉親の話をすると、なぜか不運がやって来た」(同書P194)とは、尋常ならざるものがある。しかし、「出征するとき死を決意した」(同書P216)ともある。「覚悟した」のではなく、「決意した」のである。否定的ではない前向きなニュアンスには、やはり戦後の私たちには想像できない世界がある。私が懇意にして頂いている自衛隊の元・幹部は、小野田さんに直接お会いしたことがあるそうで、とても純粋な方だと振り返っておられた。そう言われると、分からないではない。三十年という年月には、愚直な、では済まされない苛烈さがある。
同書は、東京新聞の「戦後50年企画」として同紙上に連載されたコラムを一冊の本に纏めたものだ。帰還から既に二十年が経っており、回顧録の常で、自己正当化し、また美化している部分もあるかも知れない。所詮は小野田さんという個人の戦争経験であり、自己主張である。それは今年93歳になる私の父と同様に、所詮は大きな戦争というパズル絵のごく小さな一つの断片を示すものでしかない。それでも、敗戦という時代の大転換を挟んで、玉手箱を開けて時代をワープした浦島太郎が覚えた違和感には、傾聴すべきものがあるように思う。
引用したい箇所は一杯あるが、小野田さんが帰郷したときの思いにはドキリとさせられ、最後に引用する(P209-210)。
(引用はじめ) 四月三日、私は三十年ぶりに故郷へ帰る。新大阪からバスで和歌山に向かう沿道は人の波で埋まっていた。手を振る人々にまじって、地面にひざまずき両手を合わせているおばあさんの姿が目に入った。かつて我が子を戦場に送り出した方だろう。息子さんは亡くなられたのだろうか。私は涙が止まらなかった。歓迎の人々に頭を下げ、手を振って応えながら、私は胸が息苦しかった。(なぜ生きて帰った私だけがこんなに歓迎されるのか。戦争で死んだ仲間はどうなのか。私は遅まきながらも国家の恩恵を受けた。だが、死んだ仲間は非道な戦争の加害者のように社会から疎んじられている。戦友たちは国家と悠久の大義を信じて死んだのだ)(引用おわり)














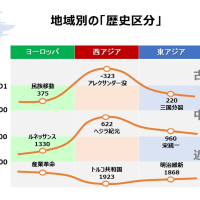




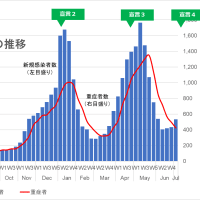






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます