茨城県薬剤師会の薬事情報からの転載です。
元ページ
薬事情報
--------------------------------------------------------------------------------
この度の、原子力施設事故では、ヨウ素剤について多数のご質問が寄せられました。ヨウ素剤については、すでに、動燃アスファルト固化処理施設事故の時に、会報48号(97年4月)薬事情報だより(P7)に掲載いたしましたが、一部改編し再度お知らせいたします。
薬事情報室
Q:原子力施設での臨界事故があった場合、どうしてヨウ素剤を服用するのか
A:先月、東海村の原子力施設において臨界事故が発生し問題となったが、臨界事故が発生した場合、ヨウ素、キセノン、クリプトン等、種々の放射性物質が放出されると言われている。この中で、放射性ヨウ素(131I)は、放出される割合の最も高い放射性物質であり、施設を破壊してしまうほどの事故の場合、気化して大気中に広範囲に拡散しやすい上、呼吸や飲食により体内に吸収されやすいため、内部被曝を起こす物質として特に注目されている。しかし、今回の事故では施設が破壊されなかったことや、ウランの量が少なかったことなどから、放射性ヨウ素は発生したが大気中に放出されたのは極僅かであった。10月5日にJCO周辺の雑草から131Iが最大0.037Bq/g検出されたが、これを食べると仮定しても実効線量当量は0.00036mSv(0.036ミリレム)となり、人の年間線量限度1mSvの約3000分の1ほどであった。
本来、ヨウ素は、甲状腺ホルモンの構成成分として生体に必須の微量元素であり、体内には約25mgが存在する。また、海草に多く含まれ、1日の摂取量は成人で約1.5mgとされている。一方、甲状腺は、ヨウ素を取り込み蓄積するという機能があるため、原子力施設の事故で環境中に放出された131Iが体内に吸収されると、甲状腺で即座に甲状腺ホルモンに合成され、甲状腺組織の中で放射能を放出し続ける。その結果、放射能による甲状腺障害が起こり、晩発性の障害として甲状腺腫や甲状腺機能低下症を引き起こすとされている。
これらの障害を防ぐためには、被曝する前に放射能をもたないヨウ素を服用し、甲状腺をヨウ素で飽和しておく必要がある。こうすることにより、131Iにより内部被爆しても甲状腺には取り込まれず予防的効果が期待できる。その際、ヨウ素剤の効果は投与する時期に大きく依存するとされており、表に示すとおり被曝直前に摂取した時に効果が最大で、時間が経過するとその効果は薄くなる。
100mgのKIを投与したときの131I摂取防止率
投与時期 131I摂取防止率
被曝24時間前投与 約70%
被曝12時間前投与 約90%
被曝直前投与 約97%
被曝3時間後 約50%
被曝6時間後 防止できない
また、ヨウ素の吸収は、食後で30分後、空腹時で5分後から始まるとされ、一旦甲状腺ホルモンに取り込まれ有機化されると、体内に長期間貯留するため、放射性ヨウ素に被爆する前に、ヨウ素剤を服用することが重要である。
予防投与量としては、1日1回服用し成人でヨウ化カリウム130mg(ヨウ素として100mg)、1歳以下の乳幼児でヨウ化カリウム65mg(ヨウ素として50mg)とされ、服用期間としては、事故の影響度にもよるが、3~7日程度と考えられる。なお、ヨウ化カリウムの入手が困難である場合は、市販のルゴール液(ヨウ化カリウムとヨードを2対1の割合で水に溶かしたもの)や、ヨウ素レシチン、または、試薬のヨウ化カリウム等を使うことも可能である。
ヨウ素の副作用としては、甲状腺障害(腺腫、機能失調)、ヨウ素アレルギー(発熱、関節痛、蕁麻疹等)、耳下腺炎等の報告があるが、一般には1回130mgのヨウ化カリウムの経口投与では、たいした副作用は発生しないとされている。しかし、食物からの摂取量が通常1日1.5mgであることからすると、被曝線量が5レム以下の場合は使用しないほうが良いとされ、逆に50レム以上の場合は積極的に使用することが望まれている。
現在、茨城県では、下記自治体施設や保健所に、夜間人口の1日分(244,000人×2錠)と、原子力医療センターに6日分のヨウ化カリウム錠を分散配置している。
保管場所 保管数量(50mg錠)
東海村役場 64,000
ひたちなか市生涯保健センター 120,000
ひたちなか保健所 10,000
日立市南部支所防災倉庫 60,000
日立保健所 104,000
常陸太田保健サービスセンター 24,000
那珂町役場 24,000
大洗町消防本部防災倉庫 42,000
水戸市常澄保健センター 12,000
鉾田保健所 18,000
茨城町役場(薬品室) 10,000
小 計 488,000
原子力医療センター(国立水戸病院内) 2,928,000
合 計 3,416,000
[参考]
1) 学術 放射能汚染 ヨウ素を:高橋保志、道薬誌3 (6) 11 (1986)
2) 放射能とヨウ素:ドラッグビュー(山口県 薬) (23) 6 (1986)
3) チェルノブイリ被曝のヨード剤による予防:石井淳、日本医事新報№3496 136 (1991)
4) 原子力事故緊急時医療活動マニュアル(その5):菅野商会医薬品情報 (17) 42 (1988)
5) 原子力事故緊急時医療活動マニュアル(その6):菅野商会医薬品情報 (20) 57 (1988)
(以上は、ミクシィのマイミクさんの中今呑さんの日記からの転転載です。)
マクロビオティック的には、海藻などからのヨウ素を摂ることおすすめしますが、その根拠を求める方も多いと思いますので、大いに参考になるのではと思います。
補足するならば、海藻からのヨウ素+玄米、味噌・醤油などの発酵食品がお勧めです。
特に、今回被災なさった地域(震度3以上)、福島に近隣する地域の方は、放射能の危険性が心配ですので、ご参考になさってください。
ただし、現病歴として甲状腺機能の障害等がある場合は、医師に相談してくださいね。
また、明日は雨が降るところもあるようなので、できるだけ雨に当たらないように気をつけてください。
政府の発表の信ぴょう性がどれほどか、<?>でもありますし、
だからと言って、恐怖感をあおるわけでもありませんので、
ご自身での判断でお願いしたいと思いますが、
食を整えておくことに、異論はないのではと思いますので、
特に、関東圏にいらっしゃる方にはお伝えしたいことなのです。
ココロより出ず、願わくばココロに帰らんことを。
と、思います。
そして、場所を問わず節電を。
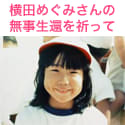
原発 チェルノブイリ 放射能 被爆 生体実験 電気 エネルギー 汚染
元ページ
薬事情報
--------------------------------------------------------------------------------
この度の、原子力施設事故では、ヨウ素剤について多数のご質問が寄せられました。ヨウ素剤については、すでに、動燃アスファルト固化処理施設事故の時に、会報48号(97年4月)薬事情報だより(P7)に掲載いたしましたが、一部改編し再度お知らせいたします。
薬事情報室
Q:原子力施設での臨界事故があった場合、どうしてヨウ素剤を服用するのか
A:先月、東海村の原子力施設において臨界事故が発生し問題となったが、臨界事故が発生した場合、ヨウ素、キセノン、クリプトン等、種々の放射性物質が放出されると言われている。この中で、放射性ヨウ素(131I)は、放出される割合の最も高い放射性物質であり、施設を破壊してしまうほどの事故の場合、気化して大気中に広範囲に拡散しやすい上、呼吸や飲食により体内に吸収されやすいため、内部被曝を起こす物質として特に注目されている。しかし、今回の事故では施設が破壊されなかったことや、ウランの量が少なかったことなどから、放射性ヨウ素は発生したが大気中に放出されたのは極僅かであった。10月5日にJCO周辺の雑草から131Iが最大0.037Bq/g検出されたが、これを食べると仮定しても実効線量当量は0.00036mSv(0.036ミリレム)となり、人の年間線量限度1mSvの約3000分の1ほどであった。
本来、ヨウ素は、甲状腺ホルモンの構成成分として生体に必須の微量元素であり、体内には約25mgが存在する。また、海草に多く含まれ、1日の摂取量は成人で約1.5mgとされている。一方、甲状腺は、ヨウ素を取り込み蓄積するという機能があるため、原子力施設の事故で環境中に放出された131Iが体内に吸収されると、甲状腺で即座に甲状腺ホルモンに合成され、甲状腺組織の中で放射能を放出し続ける。その結果、放射能による甲状腺障害が起こり、晩発性の障害として甲状腺腫や甲状腺機能低下症を引き起こすとされている。
これらの障害を防ぐためには、被曝する前に放射能をもたないヨウ素を服用し、甲状腺をヨウ素で飽和しておく必要がある。こうすることにより、131Iにより内部被爆しても甲状腺には取り込まれず予防的効果が期待できる。その際、ヨウ素剤の効果は投与する時期に大きく依存するとされており、表に示すとおり被曝直前に摂取した時に効果が最大で、時間が経過するとその効果は薄くなる。
100mgのKIを投与したときの131I摂取防止率
投与時期 131I摂取防止率
被曝24時間前投与 約70%
被曝12時間前投与 約90%
被曝直前投与 約97%
被曝3時間後 約50%
被曝6時間後 防止できない
また、ヨウ素の吸収は、食後で30分後、空腹時で5分後から始まるとされ、一旦甲状腺ホルモンに取り込まれ有機化されると、体内に長期間貯留するため、放射性ヨウ素に被爆する前に、ヨウ素剤を服用することが重要である。
予防投与量としては、1日1回服用し成人でヨウ化カリウム130mg(ヨウ素として100mg)、1歳以下の乳幼児でヨウ化カリウム65mg(ヨウ素として50mg)とされ、服用期間としては、事故の影響度にもよるが、3~7日程度と考えられる。なお、ヨウ化カリウムの入手が困難である場合は、市販のルゴール液(ヨウ化カリウムとヨードを2対1の割合で水に溶かしたもの)や、ヨウ素レシチン、または、試薬のヨウ化カリウム等を使うことも可能である。
ヨウ素の副作用としては、甲状腺障害(腺腫、機能失調)、ヨウ素アレルギー(発熱、関節痛、蕁麻疹等)、耳下腺炎等の報告があるが、一般には1回130mgのヨウ化カリウムの経口投与では、たいした副作用は発生しないとされている。しかし、食物からの摂取量が通常1日1.5mgであることからすると、被曝線量が5レム以下の場合は使用しないほうが良いとされ、逆に50レム以上の場合は積極的に使用することが望まれている。
現在、茨城県では、下記自治体施設や保健所に、夜間人口の1日分(244,000人×2錠)と、原子力医療センターに6日分のヨウ化カリウム錠を分散配置している。
保管場所 保管数量(50mg錠)
東海村役場 64,000
ひたちなか市生涯保健センター 120,000
ひたちなか保健所 10,000
日立市南部支所防災倉庫 60,000
日立保健所 104,000
常陸太田保健サービスセンター 24,000
那珂町役場 24,000
大洗町消防本部防災倉庫 42,000
水戸市常澄保健センター 12,000
鉾田保健所 18,000
茨城町役場(薬品室) 10,000
小 計 488,000
原子力医療センター(国立水戸病院内) 2,928,000
合 計 3,416,000
[参考]
1) 学術 放射能汚染 ヨウ素を:高橋保志、道薬誌3 (6) 11 (1986)
2) 放射能とヨウ素:ドラッグビュー(山口県 薬) (23) 6 (1986)
3) チェルノブイリ被曝のヨード剤による予防:石井淳、日本医事新報№3496 136 (1991)
4) 原子力事故緊急時医療活動マニュアル(その5):菅野商会医薬品情報 (17) 42 (1988)
5) 原子力事故緊急時医療活動マニュアル(その6):菅野商会医薬品情報 (20) 57 (1988)
(以上は、ミクシィのマイミクさんの中今呑さんの日記からの転転載です。)
マクロビオティック的には、海藻などからのヨウ素を摂ることおすすめしますが、その根拠を求める方も多いと思いますので、大いに参考になるのではと思います。
補足するならば、海藻からのヨウ素+玄米、味噌・醤油などの発酵食品がお勧めです。
特に、今回被災なさった地域(震度3以上)、福島に近隣する地域の方は、放射能の危険性が心配ですので、ご参考になさってください。
ただし、現病歴として甲状腺機能の障害等がある場合は、医師に相談してくださいね。
また、明日は雨が降るところもあるようなので、できるだけ雨に当たらないように気をつけてください。
政府の発表の信ぴょう性がどれほどか、<?>でもありますし、
だからと言って、恐怖感をあおるわけでもありませんので、
ご自身での判断でお願いしたいと思いますが、
食を整えておくことに、異論はないのではと思いますので、
特に、関東圏にいらっしゃる方にはお伝えしたいことなのです。
ココロより出ず、願わくばココロに帰らんことを。
と、思います。
そして、場所を問わず節電を。
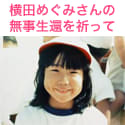
原発 チェルノブイリ 放射能 被爆 生体実験 電気 エネルギー 汚染









