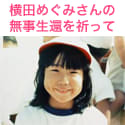夕方、てんつくマンが治療にきました。
島根から・・・。
今夜はその足で岡山入り。
夕飯ぐらい食べてって~ってことで、我が家で晩ごはんをご一緒しました。
被災地の話いろいろしてくださいました。
「アフガニスタンよりひどいよ。
とにかく、すごい。
空爆のあとみたいやねん。」
「たまさ~ん、ぼくら小豆島でることにしたよ。
被災者の支援はずっと続くから、もっと大規模に農業できて受け入れができる北海道を拠点に活動 することにしてん。」
「文昭さんと?」
「そう」
「被災地にいくとね、優しくなるよ」
「向こうでは、カップめんばっかりやね~」
「この玄米、おいしいなぁ。これやったらみんな玄米食べれるようになるよね。」
「東京では、飲食業の30%がつぶれるって言われてる。支えないかん人らが倒れていってる。」
「自粛もいい加減にせんと、皆倒れになるんよね。もっと元気にならんとね」
一時間ちょっとの間にいろいろな話をいたしました。
ちょっとやせたてんつくマン。
でも、やっぱりかっこいいね。
いつもびっくりするくらい大きな荷物をいくつも下げて、本当に頭がさがります。
ありがとう。
あなたがいてくれて、私たちは大きな力を頂いています。
身体をこわさないように、がんばってください。
わたしたちもがんばります。
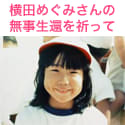
島根から・・・。
今夜はその足で岡山入り。
夕飯ぐらい食べてって~ってことで、我が家で晩ごはんをご一緒しました。
被災地の話いろいろしてくださいました。
「アフガニスタンよりひどいよ。
とにかく、すごい。
空爆のあとみたいやねん。」
「たまさ~ん、ぼくら小豆島でることにしたよ。
被災者の支援はずっと続くから、もっと大規模に農業できて受け入れができる北海道を拠点に活動 することにしてん。」
「文昭さんと?」
「そう」
「被災地にいくとね、優しくなるよ」
「向こうでは、カップめんばっかりやね~」
「この玄米、おいしいなぁ。これやったらみんな玄米食べれるようになるよね。」
「東京では、飲食業の30%がつぶれるって言われてる。支えないかん人らが倒れていってる。」
「自粛もいい加減にせんと、皆倒れになるんよね。もっと元気にならんとね」
一時間ちょっとの間にいろいろな話をいたしました。
ちょっとやせたてんつくマン。
でも、やっぱりかっこいいね。
いつもびっくりするくらい大きな荷物をいくつも下げて、本当に頭がさがります。
ありがとう。
あなたがいてくれて、私たちは大きな力を頂いています。
身体をこわさないように、がんばってください。
わたしたちもがんばります。