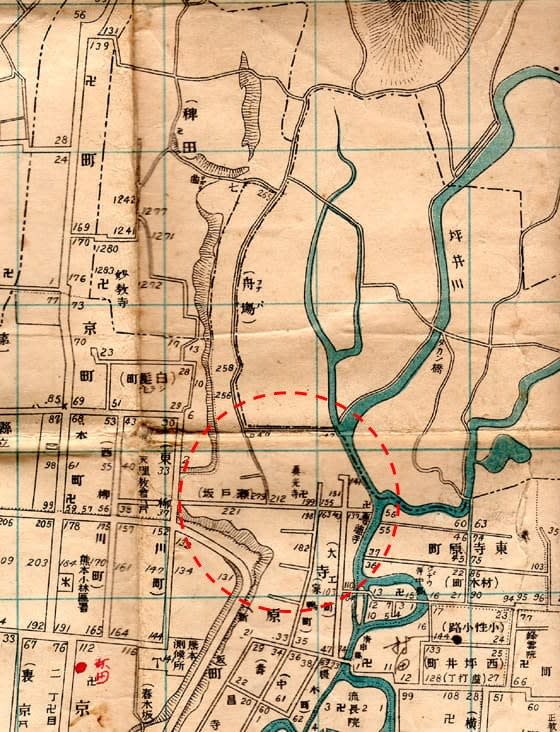浄国寺(熊本市北区高平2丁目)の寺宝「谷汲観音」様をしばらく拝観していない。近々お伺いするつもりだが、これまで「谷汲観音」様については何度もブログネタにさせてもらった。その中から主なものをピックアップしてこれまでの経緯を整理してみた。
2010年10月21日

NHK-BS2にチャンネルを回したら、「男前列伝」という番組の再放送をやっていた。俳優の山本耕史が熊本を訪れて、江戸末期から明治初期にかけて活躍した熊本出身の活人形師・松本喜三郎の作品についてリポートしていた。山本耕史が特に心を動かされたという「谷汲観音像(たにくみかんのんぞう)」。たしかにテレビ画面を通じても不思議なオーラを放っている。いったいこの観音像はどこにあるのかと見ていると、なんと僕が週2、3回はその前を通っている浄国寺というお寺だった。現存する彼の作品は数少ないそうだが、中でもこの観音像は特に貴重なものらしい。一般公開もしているらしいので、これは一度拝んでおかなければ。明日にでもさっそく行ってみよう。
2010年10月23日

買物のついでに浄国寺に立ち寄り、谷汲観音様とついに対面。ご住職の案内で観音様の前におずおずと進み、両手を合わせて見上げると、ちょうど視線が合う角度になっている。その存在感に圧倒的されそうだ。なんだか観音様はすべてお見通しのような気がして、思わず目をそらしそうになる。
作者の松本喜三郎は文政8年(1825)の生まれというから、勝海舟や坂本龍馬などと同じ時代に生きた人だ。若い頃から造り物に天賦の才を発揮し、郷里の熊本から大阪に出て、活人形(いきにんぎょう)師として成功を収めたそうだが、この谷汲観音像は、明治4年、浅草において行った「西国三十三ヶ所観音霊験記」という活人形興業で大喝采を博した三十三体の観音像のうちの一つだそうである。喜三郎にとってこの谷汲観音は会心の作だったそうで、晩年、郷里の熊本に戻った際、松本家の菩提寺であった、この浄国寺に寄進したものだそうだ。
いや、とにかく眺めていると離れがたくなるような不思議なひと時だった。
2011年2月23日
熊本県伝統工芸館の地下和室で「博多織屋次平展」をやっていた。2年ほど前、NHK福岡局の「博多 はたおと」という星野真里が出演したドラマが印象に残っていたので覗いてみた。展示場にいた四代目次平さんはなんと、あの谷汲観音の着物を修復した方だった。さっそくお話を聴いてみた。松本喜三郎が作った淨国寺の谷汲観音と来迎院の聖観世音菩薩の二つの活人形の着物を修復するのに約2年の歳月を要したそうだ。匠の世界の話には引き込まれてしまう。そう言えば昨年、谷汲観音を観に行った時、住職が着物の修復の話をされたのを思い出した。
2014年10月30日
松本喜三郎作の活人形「谷汲観音像」に会いたくなり、4年ぶりに熊本市北区高平の浄国寺を訪れた。本堂に上ると、奥様が開口一番、「今、BSで放送していますよ」と仰る。何という偶然、浄国寺を訪問した、まさにその時間、NHKプレミアムで、4年前にNHK-BS2で放送した「男前列伝」という番組の再放送をやっていた。俳優の山本耕史が熊本を訪れて、活人形「谷汲観音像」に強く心を動かされるという内容だったが、僕はその番組を見て初めて浄国寺を訪問したのだった。今日また再放送されることは全く知らなかったので、目に見えない力に動かされたような気がしてならない。そして4年ぶりに拝んだ観音様の表情は、今回もまた「すべてお見とおしだ!」と仰っているような気がした。
2016年10月19日
前回の参拝からちょうど2年ほど経つので、そろそろまた谷汲観音様をお参りに行こうかと思い、高平の浄国寺さんに電話をしてみる。ご住職が電話に出られたので、ひょっとして地震の被害を受けているのではないかとおたずねしてみると、谷汲観音様はご無事だったとのことでホッとする。ただ、本堂がかなり損壊し、修復工事があと1ヶ月ほどはかかりそうだとのことなので、年末くらいに一度お伺いしてみることにした。
2017年11月14日
先日、姉が高平の浄国寺近くのバス停で、栃木県からやってきたという若い女性と一緒になったそうだ。その女性は浄国寺の、松本喜三郎作の生人形「谷汲観音」を見に来たのだという。わざわざ栃木県あたりからも見に来る方がいるのかとちょっとビックリ。
そういえば、昨年、地震の影響がなかったかどうか確かめに浄国寺へ行ってからやがて1年。年内にまた拝観しに行くとしよう。
そもそもこの生人形「谷汲観音」は、熊本市迎町出身の人形師松本喜三郎が、維新後の明治4年(1871)から明治8年(1875)にかけて、浅草の奥山で興行し、大成功をおさめた「西国三十三所観音霊験記」の中の生人形の一つ。喜三郎にとって最も愛着が強い作品だったようだが、上野の西郷隆盛像などの彫刻で知られる高村光雲は、「光雲懐古談」の中で、谷汲観音について次のように述べている。
三十三番の美濃の谷汲観音、これは最後のキリ舞台で、中で一番大きい舞台、背景は遠山ですべて田道の有様を写し、ここに大倉信満という人(奥州の金商人)が驚いている。その後に厨子があって、厨子の中より観音が抜け出した心持で、ここへ観音がせり出します。この観音が人形の観音でなく、また本尊として礼拝するという観音でもなく、ちょうどその間を行った誠に結構な出来で、頭に塗傘を冠り右の手に塗杖を持ち左の手にある方を指している図で、袈裟と衣は紗の如き薄物へ金の模様を施し、天冠を頂き衣は透きとおって肉体が見え、何とも見事なもので、尤もこれはキリの舞台にて喜三郎も非常に注意の作と思われます。
2022年6月8日
しばらくご尊顔を拝していない浄国寺の谷汲観音様。12年前に初めて訪れた時、観音様の表情とともにそのポーズに魅入られた。「西国三十三所観音霊験記」第三十三番の美濃谷汲山・華厳寺には概ね次のようなストーリーが書かれている。
奥州の金商人である大倉信満は大慈大悲を深く信じており、その霊験か、ある時、文殊菩薩の化身である童子が現れ、霊木の松の木で十一面観音像を造って信満に与えた。信満は京都仁和寺でこの像の供養をした後、美濃垂井までやって来たが、背負った観音像を納めた厨子が重くて動けなくなった。すると厨子の中から観音様が出てきて、ここにゆかりの地がある。あと五里ほど行った辺りに鎮座させなさいと宣う。そこが谷汲という地だった。信満は観音様の大悲の御心に従い、そこに伽藍を建立した。観音像の蓮台の下から湧き出る油によって常灯明を灯し、谷汲寺と号した。
この話から察するに谷汲観音様は、今まさに厨子から出てきたところで、信満に進むべき方向を指し示している場面なのだろう。だから観音様の視線は信満に注がれており、左手が指し示しているのが谷汲の方向なのだろう。具体的には書かれていない観音様を造形し、谷汲観音と名付けた松本喜三郎のセンスは並外れていると言わざるを得ない。



















 昭和48年11月29日に多数の犠牲者を出した「大洋デパート火災」から今日でちょうど50年。
昭和48年11月29日に多数の犠牲者を出した「大洋デパート火災」から今日でちょうど50年。




 NHK-BS2にチャンネルを回したら、「男前列伝」という番組の再放送をやっていた。俳優の山本耕史が熊本を訪れて、江戸末期から明治初期にかけて活躍した熊本出身の活人形師・松本喜三郎の作品についてリポートしていた。山本耕史が特に心を動かされたという「谷汲観音像(たにくみかんのんぞう)」。たしかにテレビ画面を通じても不思議なオーラを放っている。いったいこの観音像はどこにあるのかと見ていると、なんと僕が週2、3回はその前を通っている浄国寺というお寺だった。現存する彼の作品は数少ないそうだが、中でもこの観音像は特に貴重なものらしい。一般公開もしているらしいので、これは一度拝んでおかなければ。明日にでもさっそく行ってみよう。
NHK-BS2にチャンネルを回したら、「男前列伝」という番組の再放送をやっていた。俳優の山本耕史が熊本を訪れて、江戸末期から明治初期にかけて活躍した熊本出身の活人形師・松本喜三郎の作品についてリポートしていた。山本耕史が特に心を動かされたという「谷汲観音像(たにくみかんのんぞう)」。たしかにテレビ画面を通じても不思議なオーラを放っている。いったいこの観音像はどこにあるのかと見ていると、なんと僕が週2、3回はその前を通っている浄国寺というお寺だった。現存する彼の作品は数少ないそうだが、中でもこの観音像は特に貴重なものらしい。一般公開もしているらしいので、これは一度拝んでおかなければ。明日にでもさっそく行ってみよう。 買物のついでに浄国寺に立ち寄り、谷汲観音様とついに対面。ご住職の案内で観音様の前におずおずと進み、両手を合わせて見上げると、ちょうど視線が合う角度になっている。その存在感に圧倒的されそうだ。なんだか観音様はすべてお見通しのような気がして、思わず目をそらしそうになる。
買物のついでに浄国寺に立ち寄り、谷汲観音様とついに対面。ご住職の案内で観音様の前におずおずと進み、両手を合わせて見上げると、ちょうど視線が合う角度になっている。その存在感に圧倒的されそうだ。なんだか観音様はすべてお見通しのような気がして、思わず目をそらしそうになる。