巫女舞は記紀に書かれた「岩戸隠れ」の神話をその起源とする。天の岩戸にお隠れになった天照大神をつれ出すために岩戸の前で天鈿女命(アメノウズメ)が舞った神がかりした激しい舞。これが巫女舞の起源であり、また日本の芸能の始まりともいわれている。近代になってからは見せる神事芸能として、より洗練された舞や神楽歌が作られた。
下の「扇の舞」は毎年11月25日に行われる玉名市の梅林天満宮例大祭において、太宰府天満宮の巫女によって舞われる舞の一つ。この舞は、昭和2年(1927)に行われた昭和天皇のご即位の大礼に際して、明治天皇の御製3首を使って作られた「八乙女の舞」の一部で、まさに近代の創作神楽である。
【歌詞】
わが国は神の末なり神まつる昔の手ふりわするなよゆめ
わが国は神の末裔であるから、祭祀のしきたりは、いささかもおろそかにしてはいけない、と言う意味の歌詞はいかにも明治時代を思わせるが、能や日本舞踊の源流として巫女舞を見るとまた味わい深いものがある。

下の「扇の舞」は毎年11月25日に行われる玉名市の梅林天満宮例大祭において、太宰府天満宮の巫女によって舞われる舞の一つ。この舞は、昭和2年(1927)に行われた昭和天皇のご即位の大礼に際して、明治天皇の御製3首を使って作られた「八乙女の舞」の一部で、まさに近代の創作神楽である。
【歌詞】
わが国は神の末なり神まつる昔の手ふりわするなよゆめ
わが国は神の末裔であるから、祭祀のしきたりは、いささかもおろそかにしてはいけない、と言う意味の歌詞はいかにも明治時代を思わせるが、能や日本舞踊の源流として巫女舞を見るとまた味わい深いものがある。

















 今年の山鹿灯籠まつりは8月16日の千人灯籠踊りのほか、15日に予定されていた大宮神社での奉納灯籠おどりやおまつり広場での灯籠おどりなども中止されるという。今年はもう過去の映像で我慢するしかないようだ。
今年の山鹿灯籠まつりは8月16日の千人灯籠踊りのほか、15日に予定されていた大宮神社での奉納灯籠おどりやおまつり広場での灯籠おどりなども中止されるという。今年はもう過去の映像で我慢するしかないようだ。

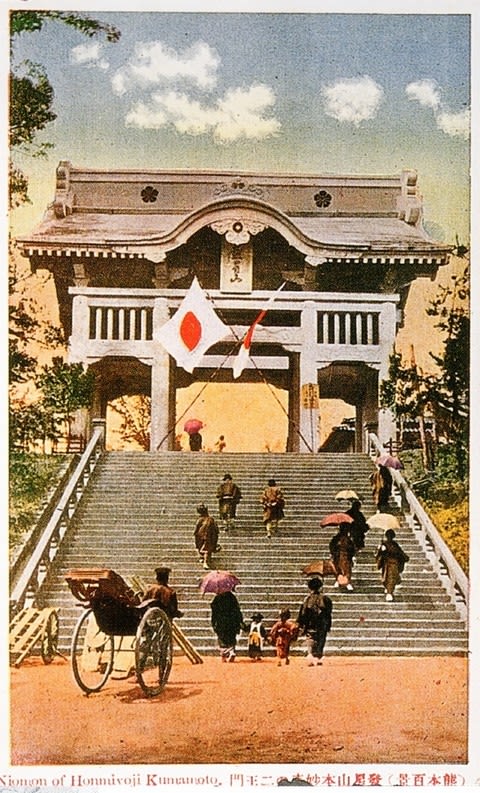

 稲荷神社の主祭神は、商売繁昌・五穀豊穣の神様である倉稲魂命
稲荷神社の主祭神は、商売繁昌・五穀豊穣の神様である倉稲魂命





 平成29年(2017)に他界された規工川佑輔先生の奥様から1冊の本が送られてきた。それは先生のノートに書き遺された2008年から2014年までの作品を、奥様がまとめられた歌集だった。先生にとって第五歌集となるこの「はこべら」は先生の遺作となった次の歌から採られた歌集名であることが奥様のあとがきに書かれていた。
平成29年(2017)に他界された規工川佑輔先生の奥様から1冊の本が送られてきた。それは先生のノートに書き遺された2008年から2014年までの作品を、奥様がまとめられた歌集だった。先生にとって第五歌集となるこの「はこべら」は先生の遺作となった次の歌から採られた歌集名であることが奥様のあとがきに書かれていた。






