名にしおはゞ あだにぞあるべき たはれ島 浪のぬれぎぬ 着るといふなり(伊勢物語 六十一段)
島は八十島 浮島 たはれ島 絵島 松が浦島 豊浦の島 まがきの島(枕草子 百九十段)
宇土市住吉町の有明海に臨む住吉神社西北の崖下に浮かぶ小さい岩島で、別名たばこ島とも裸島ともいう。三角大矢野海辺県立自然公園に含まれ、古くから歌や物語などにも詠まれた景勝の地。「後撰集」一五雑に「まめなれとあた名はたちぬ風流島よる白波をぬれ衣にきて 小宰相」、また「伊勢物語抄」には「染川は筑前に有り風流島は肥後国名所なり…」などと記されており、そのほか、「夫木和歌抄」「枕草子」などにその名が見えている。(熊本県大百科事典より)
島は八十島 浮島 たはれ島 絵島 松が浦島 豊浦の島 まがきの島(枕草子 百九十段)
宇土市住吉町の有明海に臨む住吉神社西北の崖下に浮かぶ小さい岩島で、別名たばこ島とも裸島ともいう。三角大矢野海辺県立自然公園に含まれ、古くから歌や物語などにも詠まれた景勝の地。「後撰集」一五雑に「まめなれとあた名はたちぬ風流島よる白波をぬれ衣にきて 小宰相」、また「伊勢物語抄」には「染川は筑前に有り風流島は肥後国名所なり…」などと記されており、そのほか、「夫木和歌抄」「枕草子」などにその名が見えている。(熊本県大百科事典より)















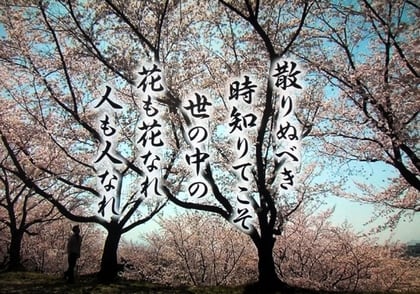


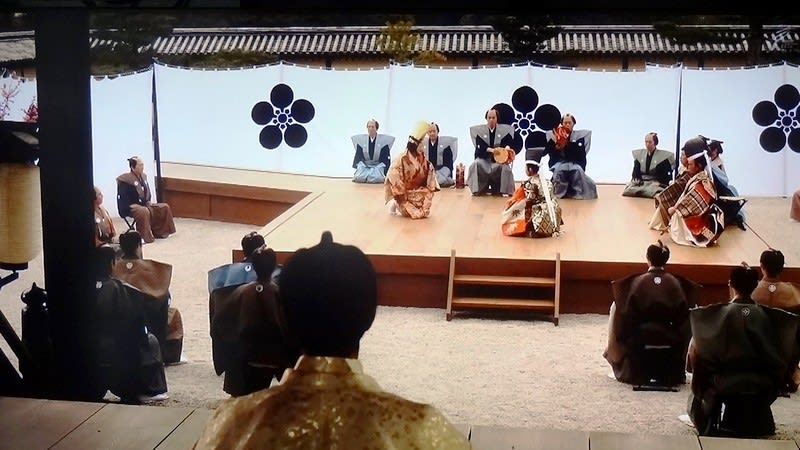










 陸上女子短距離の野林祐実さんが大学を卒業して郷里熊本へ帰って来た。中学・高校時代に全国大会で華々しく活躍し、期待されて大学へ進学したが、大学では思うような活躍はできなかった。周囲の期待が大きかっただけに本人は精神的につらかったろう。熊本では祐和會という会社に所属して陸上競技を続けるようだ。この会社のことはあまり知らないが、あの、幅跳び・三段跳びのトップアスリートから今はパラ陸上選手として挑戦を続ける中尾有沙さんが所属している会社だから、きっとスポーツ選手の面倒見もいい会社なのだろう。まだまだ23歳、これからいくらでもチャンスは残されている。故郷の暖かい環境で心身を癒しながら、もう一度トップスプリンターを目指してほしい。
陸上女子短距離の野林祐実さんが大学を卒業して郷里熊本へ帰って来た。中学・高校時代に全国大会で華々しく活躍し、期待されて大学へ進学したが、大学では思うような活躍はできなかった。周囲の期待が大きかっただけに本人は精神的につらかったろう。熊本では祐和會という会社に所属して陸上競技を続けるようだ。この会社のことはあまり知らないが、あの、幅跳び・三段跳びのトップアスリートから今はパラ陸上選手として挑戦を続ける中尾有沙さんが所属している会社だから、きっとスポーツ選手の面倒見もいい会社なのだろう。まだまだ23歳、これからいくらでもチャンスは残されている。故郷の暖かい環境で心身を癒しながら、もう一度トップスプリンターを目指してほしい。









