小学6年生と中学3年生を対象にした「全国学力テスト」の今年の結果が公表され、熊本県の小学生の国語の平均正答率は全国平均を上回った一方で、中学生の数学と英語の平均正答率は全国平均を下回ったという。特に中学生の数学が全国平均を下回るのは3年連続ということで、どうやら熊本人は数学が苦手?。僕自身も数学が苦手だったが、社会に出てから「もっと勉強しとけばよかった」と最も思ったのは数学だった経験からも、ぜひ中学・高校で数学をしっかり学んでおいてほしいと願うばかりだ。



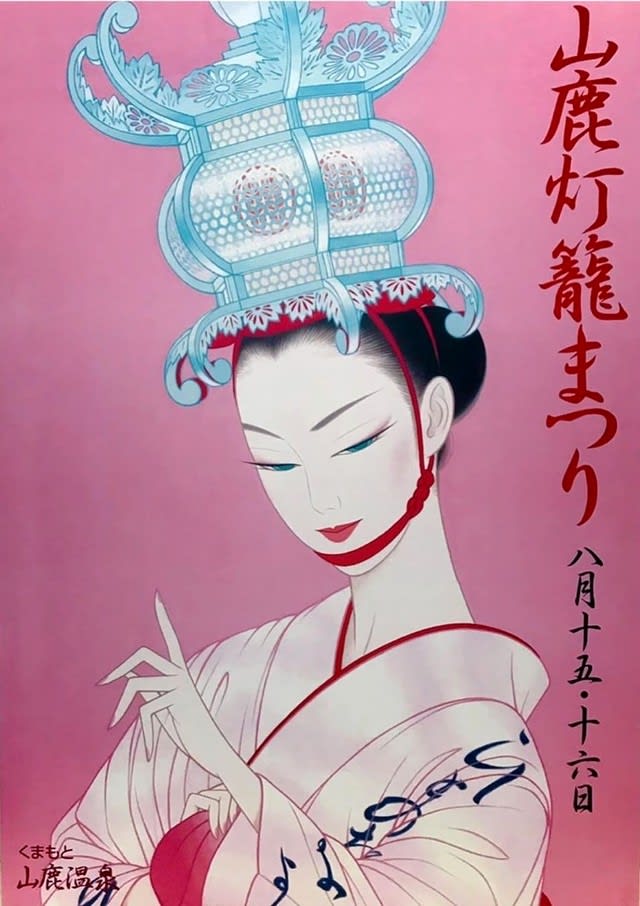

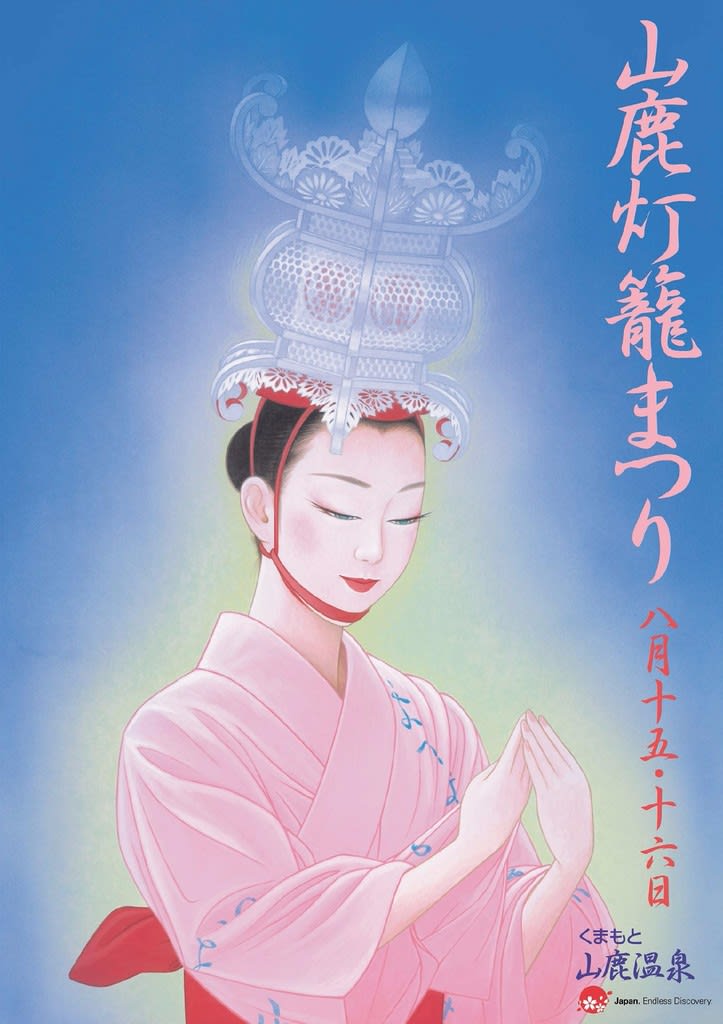
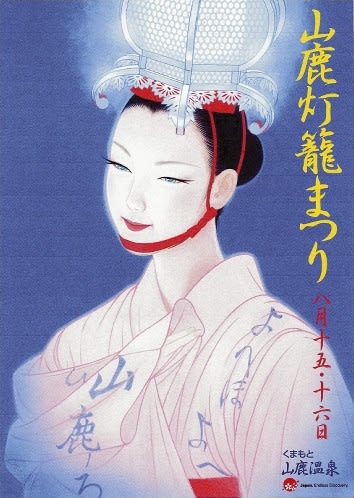
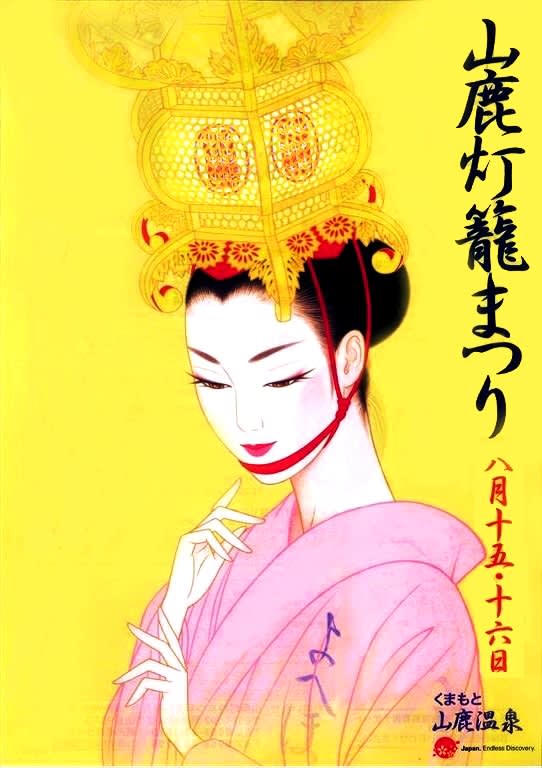
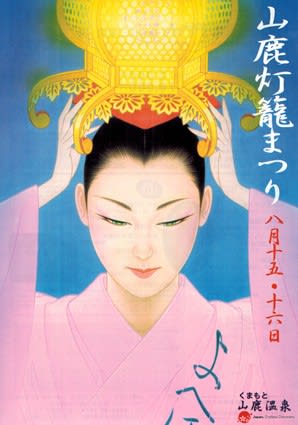
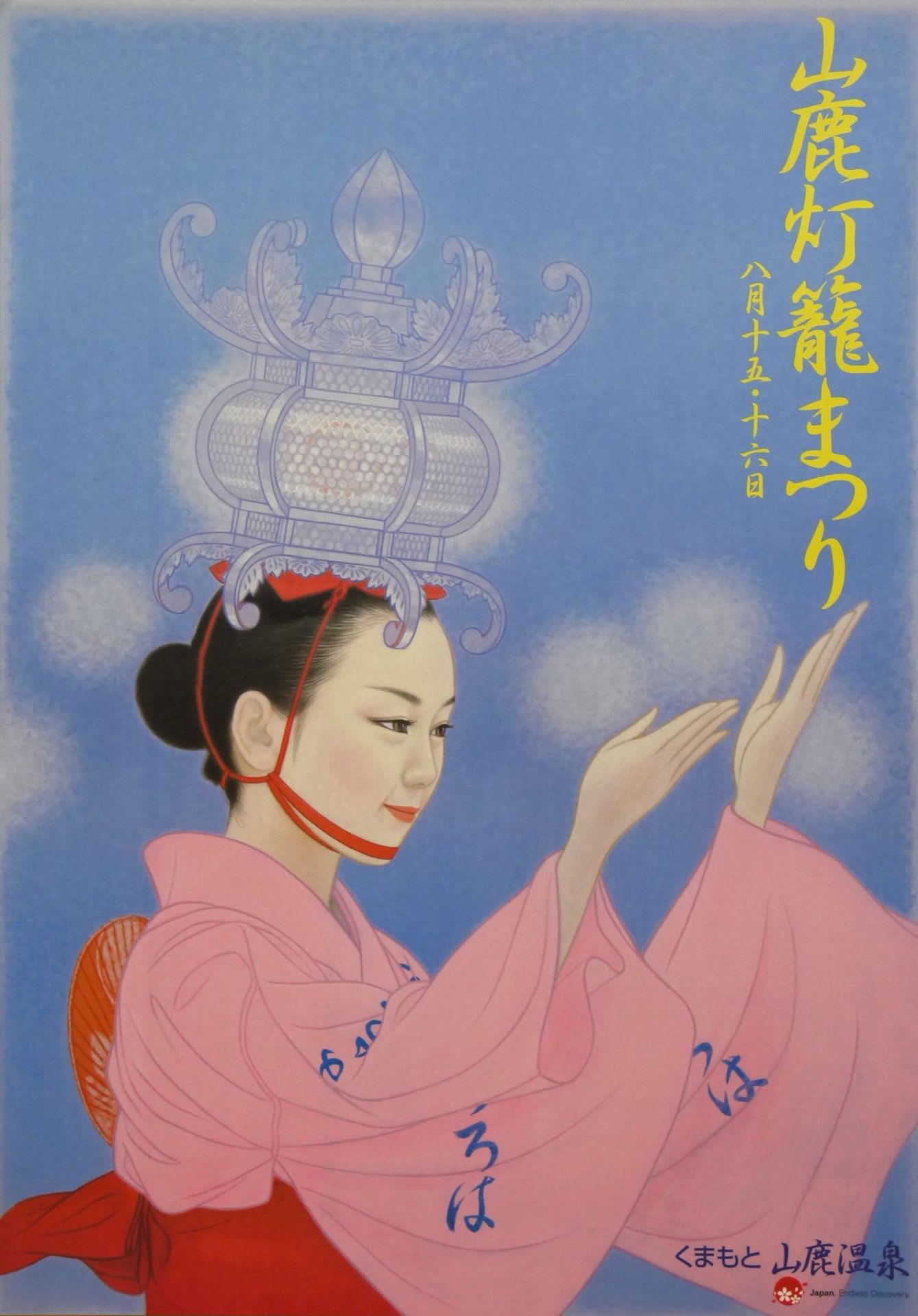
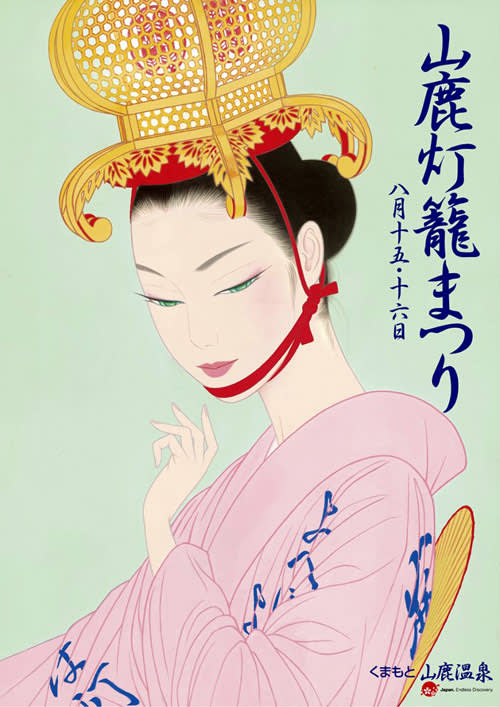
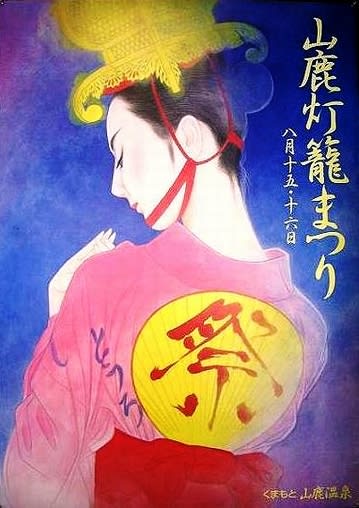










 僕の高校の大先輩である菅原平さん(85)が母黌・済々黌の水球部員に講話をされるというので聴きに行った。僕自身、校門をくぐるのは何十年ぶりだろうか。菅原さんは1968年のメキシコ五輪で日本水球が五輪初の勝利をあげた時の監督であり、また済々黌の水球部が昭和26年(1951)に初めて全国制覇した時のメンバーでもある。そんな経験を、現役の高校生に聴いてもらい、今後の活動のヒントになればという趣旨で開かれたもの。
僕の高校の大先輩である菅原平さん(85)が母黌・済々黌の水球部員に講話をされるというので聴きに行った。僕自身、校門をくぐるのは何十年ぶりだろうか。菅原さんは1968年のメキシコ五輪で日本水球が五輪初の勝利をあげた時の監督であり、また済々黌の水球部が昭和26年(1951)に初めて全国制覇した時のメンバーでもある。そんな経験を、現役の高校生に聴いてもらい、今後の活動のヒントになればという趣旨で開かれたもの。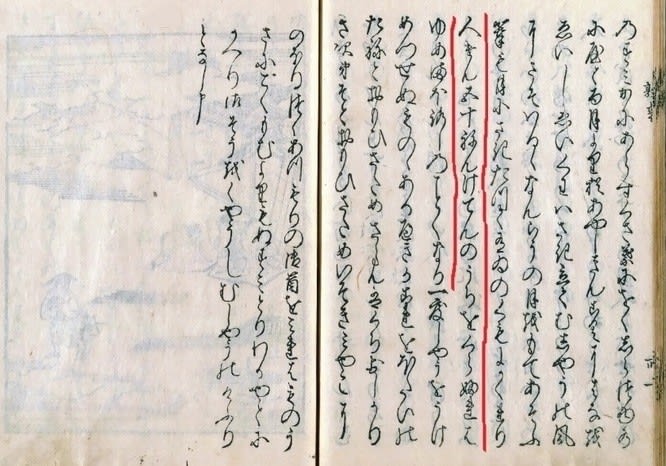
 アメリカでは映画のアカデミー賞に匹敵するテレビ業界最大の栄誉、エミー賞の候補に、なんと「こんまり流整理術」で知られる近藤麻理恵さんの番組「KonMari 人生がときめく片づけの魔法」がノミネートされたという。こんまり流の特長は何といっても「ときめき」と「感謝」の二つのキーワードにあると思う。事務的に行いがちな整理をエモーショナルに、そして日本的な万物への感謝の心によって行うこんまり流の思想がアメリカ人にも受け入れられたわけだ。7年前、初めてこんまり流で写真の整理を行なった日のことを、このブログに下記のように記している。
アメリカでは映画のアカデミー賞に匹敵するテレビ業界最大の栄誉、エミー賞の候補に、なんと「こんまり流整理術」で知られる近藤麻理恵さんの番組「KonMari 人生がときめく片づけの魔法」がノミネートされたという。こんまり流の特長は何といっても「ときめき」と「感謝」の二つのキーワードにあると思う。事務的に行いがちな整理をエモーショナルに、そして日本的な万物への感謝の心によって行うこんまり流の思想がアメリカ人にも受け入れられたわけだ。7年前、初めてこんまり流で写真の整理を行なった日のことを、このブログに下記のように記している。