 今日は弟夫婦の還暦祝いを、義弟(妹の夫)が自宅の庭に作った石窯の完成披露を兼ねて、ピザパーティーをやろうということで、玉名まで出かけた。とてもコンパクトな作りだが、家庭用としては十分過ぎるくらいだ。パーティーを始める前に早速焼いて試食。なかなか美味である。まだ11時前で、おなかもまだすいていないはずなのに皆、食べる食べる。肝心のパーティーでは、それとは別にバーベキューやちゃんちゃん焼きも用意されていたが、今日ばかりはピザの味にはかなわなかった。
今日は弟夫婦の還暦祝いを、義弟(妹の夫)が自宅の庭に作った石窯の完成披露を兼ねて、ピザパーティーをやろうということで、玉名まで出かけた。とてもコンパクトな作りだが、家庭用としては十分過ぎるくらいだ。パーティーを始める前に早速焼いて試食。なかなか美味である。まだ11時前で、おなかもまだすいていないはずなのに皆、食べる食べる。肝心のパーティーでは、それとは別にバーベキューやちゃんちゃん焼きも用意されていたが、今日ばかりはピザの味にはかなわなかった。
 今日は弟夫婦の還暦祝いを、義弟(妹の夫)が自宅の庭に作った石窯の完成披露を兼ねて、ピザパーティーをやろうということで、玉名まで出かけた。とてもコンパクトな作りだが、家庭用としては十分過ぎるくらいだ。パーティーを始める前に早速焼いて試食。なかなか美味である。まだ11時前で、おなかもまだすいていないはずなのに皆、食べる食べる。肝心のパーティーでは、それとは別にバーベキューやちゃんちゃん焼きも用意されていたが、今日ばかりはピザの味にはかなわなかった。
今日は弟夫婦の還暦祝いを、義弟(妹の夫)が自宅の庭に作った石窯の完成披露を兼ねて、ピザパーティーをやろうということで、玉名まで出かけた。とてもコンパクトな作りだが、家庭用としては十分過ぎるくらいだ。パーティーを始める前に早速焼いて試食。なかなか美味である。まだ11時前で、おなかもまだすいていないはずなのに皆、食べる食べる。肝心のパーティーでは、それとは別にバーベキューやちゃんちゃん焼きも用意されていたが、今日ばかりはピザの味にはかなわなかった。
 ワールドシリーズ第2戦の録画放送を見ながら、いろいろ考えた。松井には活躍してほしいし、今日もホームランを打ったのでよかったが、もともと“くたばれ!ヤンキース”派なので、勝敗はどうでもよい。あと最大で5試合残っているが、松井が活躍すると彼の去就がますます微妙になるなぁ。ヤンキース首脳も悩ましかろう。それにしても今日のホームラン、簡単に打てそうな球を二つも見逃しておいて、その後のクソボールを打つという曲芸的なバッティング。不思議な男だ。見ていてどうもフィリーズの方が魅力的な選手が多い。特に、昨日、サバシアから2本ホームランを打ったアトリー、そしてヴィクトリーノ、イバニエス。イバニエスなんか、マリナーズの時にもっと活躍しといてくれよ!と言いたくもなる。そう言えば、カルロス・ギーエンなんかもマリナーズからタイガースに移籍してからエライ打つようになった。イチローさんもあまり仲間に恵まれない人なのかな。今日のフィリーズの先取点のタイムリーを打ったのは、なんと昔、中日にいたステアーズじゃないか。DHで出てきた時、誰だ、この50がらみのオッサンは、と思った。いったい今いくつなんだろう。誰も言わないが、ヤンキースのジーターは、現役時代の長嶋茂雄さんにとてもよく似ている瞬間がある。僕の気のせいだろうか。
ワールドシリーズ第2戦の録画放送を見ながら、いろいろ考えた。松井には活躍してほしいし、今日もホームランを打ったのでよかったが、もともと“くたばれ!ヤンキース”派なので、勝敗はどうでもよい。あと最大で5試合残っているが、松井が活躍すると彼の去就がますます微妙になるなぁ。ヤンキース首脳も悩ましかろう。それにしても今日のホームラン、簡単に打てそうな球を二つも見逃しておいて、その後のクソボールを打つという曲芸的なバッティング。不思議な男だ。見ていてどうもフィリーズの方が魅力的な選手が多い。特に、昨日、サバシアから2本ホームランを打ったアトリー、そしてヴィクトリーノ、イバニエス。イバニエスなんか、マリナーズの時にもっと活躍しといてくれよ!と言いたくもなる。そう言えば、カルロス・ギーエンなんかもマリナーズからタイガースに移籍してからエライ打つようになった。イチローさんもあまり仲間に恵まれない人なのかな。今日のフィリーズの先取点のタイムリーを打ったのは、なんと昔、中日にいたステアーズじゃないか。DHで出てきた時、誰だ、この50がらみのオッサンは、と思った。いったい今いくつなんだろう。誰も言わないが、ヤンキースのジーターは、現役時代の長嶋茂雄さんにとてもよく似ている瞬間がある。僕の気のせいだろうか。
 最近の日本映画を見ていると、ファンとしてとても不満なことがある。それは映画を作る姿勢が、とても安易に見えるのだ。芸人やタレント(しかも二流の)を、いとも簡単に監督にして映画を作ったりしている。彼らが全て才能がないとは言わないが、それほど彼らのテレビ人気を利用したいのだろうか。ちょうど昨年の今頃、僕は映画「BALLAD」のボランティア・スタッフの仕事で、ある助監督さんと2週間をともにした。彼らは日々の撮影に追われ、渡り鳥のような生活を続けながら、自ら監督を務める日を夢見て、先輩たちから学びながら企画を練り続けている。そんな彼らをさしおいて、安直にタレントを監督に起用することは、決して日本映画の将来にためにならない、と強く思う。それとも、映画監督って誰にでもすぐにできるもんなの?
最近の日本映画を見ていると、ファンとしてとても不満なことがある。それは映画を作る姿勢が、とても安易に見えるのだ。芸人やタレント(しかも二流の)を、いとも簡単に監督にして映画を作ったりしている。彼らが全て才能がないとは言わないが、それほど彼らのテレビ人気を利用したいのだろうか。ちょうど昨年の今頃、僕は映画「BALLAD」のボランティア・スタッフの仕事で、ある助監督さんと2週間をともにした。彼らは日々の撮影に追われ、渡り鳥のような生活を続けながら、自ら監督を務める日を夢見て、先輩たちから学びながら企画を練り続けている。そんな彼らをさしおいて、安直にタレントを監督に起用することは、決して日本映画の将来にためにならない、と強く思う。それとも、映画監督って誰にでもすぐにできるもんなの?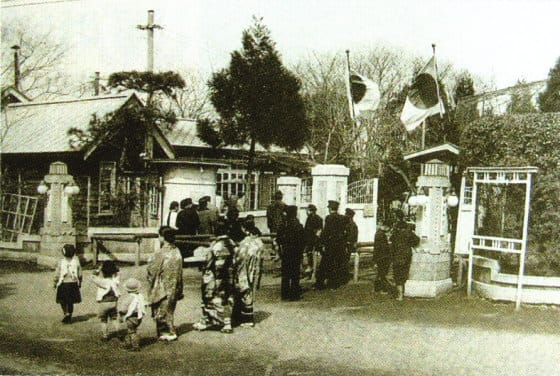




 オードリー・ヘプバーンの代表作の一つ「マイ・フェア・レディ(1964)」がリメイクされることになり、オードリーが演じたイライザ役には、なんとキーラ・ナイトレイが決まったらしい。彼女の映画は「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズや「プライドと偏見」「シルク」など、まだ数えるほどしか見ていないが、ちょっと60年代チックな顔立ちなので、若手女優の中では注目している。演技の実力のほどは、正直まだよくわからない。ただ、イライザ役に関しては、前半の、育ちの悪い娘を演じるのはオードリーよりも適役かもしれない。問題は、オードリーが声を吹きかえられて忸怩たる思いをしたであろう「歌」だ。この役のために歌のレッスンに励んでいるらしいが、はたして使ってもらえるかどうか。一方、前作で名優レックス・ハリソンが演じたヒギンズ教授の候補には、これまたなんと、現ジェームズ・ボンドのダニエル・クレイグが挙がっているらしい。まだ、これから紆余曲折があると思われるが、はたしてどんな作品に仕上がるやら、楽しみでもある。
オードリー・ヘプバーンの代表作の一つ「マイ・フェア・レディ(1964)」がリメイクされることになり、オードリーが演じたイライザ役には、なんとキーラ・ナイトレイが決まったらしい。彼女の映画は「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズや「プライドと偏見」「シルク」など、まだ数えるほどしか見ていないが、ちょっと60年代チックな顔立ちなので、若手女優の中では注目している。演技の実力のほどは、正直まだよくわからない。ただ、イライザ役に関しては、前半の、育ちの悪い娘を演じるのはオードリーよりも適役かもしれない。問題は、オードリーが声を吹きかえられて忸怩たる思いをしたであろう「歌」だ。この役のために歌のレッスンに励んでいるらしいが、はたして使ってもらえるかどうか。一方、前作で名優レックス・ハリソンが演じたヒギンズ教授の候補には、これまたなんと、現ジェームズ・ボンドのダニエル・クレイグが挙がっているらしい。まだ、これから紆余曲折があると思われるが、はたしてどんな作品に仕上がるやら、楽しみでもある。

 気付かなかったが、緒形拳さんが亡くなって、もう1年が過ぎていた。NHK-BS2では没後1年を記念して、来週月曜日から「緒形拳の渾身満力」と題して、三夜連続で彼の特集を放送する。中でも僕の一番の注目は第一夜(26日)に放送されるドラマ「破獄」だ。1985年に初めて放送された時に見て以来、再放送の都度見ているが、見るたびに緒形拳という役者の凄さを感じる。このドラマは戦前、戦中に服役し、脱獄を4回も繰り返した実在の人物をモデルにした吉村昭の小説が原作だが、この役は緒形拳以外には考えられない。凄まじい執念と生命力を体現する彼の演技は鬼気迫るものがある。また、津川雅彦演じる看守との奇妙な人間関係も見どころのひとつだ。僕は、良い役者かどうかは、「惨めな役」や「みっともない役」がやれるかどうかで決まると思っている。「カッコいい役」や「単純な悪役」は誰でもやれる。その意味において、緒形拳と三國連太郎が双璧だとずっと思ってきた。その緒形拳さんがいなくなり、三國連太郎さんもだいぶお歳を召した。今のところ後に続く役者が見当たらない。若手の奮起が望まれる。
気付かなかったが、緒形拳さんが亡くなって、もう1年が過ぎていた。NHK-BS2では没後1年を記念して、来週月曜日から「緒形拳の渾身満力」と題して、三夜連続で彼の特集を放送する。中でも僕の一番の注目は第一夜(26日)に放送されるドラマ「破獄」だ。1985年に初めて放送された時に見て以来、再放送の都度見ているが、見るたびに緒形拳という役者の凄さを感じる。このドラマは戦前、戦中に服役し、脱獄を4回も繰り返した実在の人物をモデルにした吉村昭の小説が原作だが、この役は緒形拳以外には考えられない。凄まじい執念と生命力を体現する彼の演技は鬼気迫るものがある。また、津川雅彦演じる看守との奇妙な人間関係も見どころのひとつだ。僕は、良い役者かどうかは、「惨めな役」や「みっともない役」がやれるかどうかで決まると思っている。「カッコいい役」や「単純な悪役」は誰でもやれる。その意味において、緒形拳と三國連太郎が双璧だとずっと思ってきた。その緒形拳さんがいなくなり、三國連太郎さんもだいぶお歳を召した。今のところ後に続く役者が見当たらない。若手の奮起が望まれる。
 熊本市のホームページに、市内のラーメン店が紹介されることになったそうだ。他府県はどうなのかよく知らないが、熊本県内の自治体のホームページに、個別の店の名前が紹介されるのは非常に珍しいのではないだろうか。ひょっとしたら初めてのケースかも知れない。ご当地ラーメンとしては、全国的にも歴史のある熊本ラーメンを、どうしてもっと自信を持ってPRしないのだろうかと、歯がゆい思いをしていたので喜ばしい。熊本市内でラーメン店が出来始めたのは、小学校の4、5年生の頃だったと記憶しているので、多分、昭和29年か30年だと思う。たしか一番最初に入った店は、上通りの「こむらさき」だったと思う。それまではどうだったかというと、屋台が夜中に市内をまわって「支那そば」を売っていた。おなじみのチャルメラの音を聞くと、親父がよく買って食べさせてくれた。夜来るので「夜鳴きそば」とも言っていた。しかし、ラーメン店が出来始めると、屋台の支那そば屋は来なくなった。
熊本市のホームページに、市内のラーメン店が紹介されることになったそうだ。他府県はどうなのかよく知らないが、熊本県内の自治体のホームページに、個別の店の名前が紹介されるのは非常に珍しいのではないだろうか。ひょっとしたら初めてのケースかも知れない。ご当地ラーメンとしては、全国的にも歴史のある熊本ラーメンを、どうしてもっと自信を持ってPRしないのだろうかと、歯がゆい思いをしていたので喜ばしい。熊本市内でラーメン店が出来始めたのは、小学校の4、5年生の頃だったと記憶しているので、多分、昭和29年か30年だと思う。たしか一番最初に入った店は、上通りの「こむらさき」だったと思う。それまではどうだったかというと、屋台が夜中に市内をまわって「支那そば」を売っていた。おなじみのチャルメラの音を聞くと、親父がよく買って食べさせてくれた。夜来るので「夜鳴きそば」とも言っていた。しかし、ラーメン店が出来始めると、屋台の支那そば屋は来なくなった。 昨夜、BS2で放送された中国映画「追憶の切符」。現在NHKアジア・フィルム・フェスティバルが開催中だというが、これは昨年の同フェスティバルに出品されて好評を博した作品だそうだ。中国映画ファンとしては見逃せない。良くも悪くも、ある意味、現代中国をよく表わしている作品だと思った。物語は、
昨夜、BS2で放送された中国映画「追憶の切符」。現在NHKアジア・フィルム・フェスティバルが開催中だというが、これは昨年の同フェスティバルに出品されて好評を博した作品だそうだ。中国映画ファンとしては見逃せない。良くも悪くも、ある意味、現代中国をよく表わしている作品だと思った。物語は、
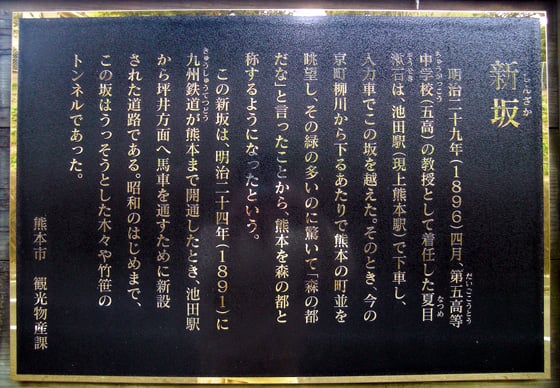


 今日は夕方から、熊本大学へ、姜尚中(かんさんじゅん)東大教授と幸山政史熊本市長の対談を聞きに行った。二人は15歳ほど年が離れているが、同じ高校の先輩後輩。僕も同じなのだが、それはさておき、幸山さんは野球部だったことはよく知られているが、実は姜さんも野球部に在籍したことがあるという。今のイメージからはちょっと想像しにくい。最初に幸山さんからマニフェストの進捗状況についてプレゼンがあった後、対談に入った。まず、今回の政権交代について意見を交わした後、「政治家のあるべき姿」論や熊本市の進むべき方向などについて熱心な意見交換が行なわれた。また、姜さんが熊本の観光政策について、いくつかの具体的な提案をされたのは意外だった。会場となった工学部百周年記念館のホールは300名ほどを収容するが、満席の状態で、二人の熱いトークに聴き入っていた。
今日は夕方から、熊本大学へ、姜尚中(かんさんじゅん)東大教授と幸山政史熊本市長の対談を聞きに行った。二人は15歳ほど年が離れているが、同じ高校の先輩後輩。僕も同じなのだが、それはさておき、幸山さんは野球部だったことはよく知られているが、実は姜さんも野球部に在籍したことがあるという。今のイメージからはちょっと想像しにくい。最初に幸山さんからマニフェストの進捗状況についてプレゼンがあった後、対談に入った。まず、今回の政権交代について意見を交わした後、「政治家のあるべき姿」論や熊本市の進むべき方向などについて熱心な意見交換が行なわれた。また、姜さんが熊本の観光政策について、いくつかの具体的な提案をされたのは意外だった。会場となった工学部百周年記念館のホールは300名ほどを収容するが、満席の状態で、二人の熱いトークに聴き入っていた。