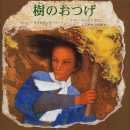
樹のおつげ/ラフカディオ・ハーン・原作 斉藤裕子・再話 藤川秀之・絵/新世研/2001年
原作は小泉八雲。5年余りのあいだで、小泉八雲の作品の語りを聞いたのは、一回ぐらい。
1854年の安政南海地震で津波から人々を救った、浜口儀兵衛がモデルで、「稲むらの火」という題で小学校の教科書にも掲載されていたといいます。
村長の息子、久作は、おとなしい子どもで、村の子なら だれでもできる木登りも 水泳も竹馬もコマまわしもできませんでした。
いつも一人で遊ぶのが好きで森の樹の下で遊んでいた久作。
ある夏の日、すずしいこかげでうとうとしていると「きゅうさく きゅうさく」と呼ぶ声。
おどろいて見上げると6才くらいのみたこともない女の子が。
やがてこの女の子と遊ぶようになった久作は、いつのまにか木登りができるようになり、水泳も竹馬もできるようになります。
あるとき、この女の子は「五日たったら大きな嵐がくる」と久作にしらせます。
嵐がくるというのを、はじめ信じなかった村人でしたが、雲や風の変化に気づき、いそいで船を浜にあげたり、家を戸板で囲って、嵐の被害は少なくてすみます。
村の人は、どうして五日もまえから嵐のくることがわかったんだ、と不思議に思います。
時折、樹の下を通った村人が話し声に気づきますが、そこには久作ただひとり。
それから、女の子のことはすっかりわすれてしまった久作も、立派な若者になり、子どもも大きく育ち、今では村長になっていました。
収穫を祝う祭りの準備で、みんなが家を空けていた時、縁側がこきざみにゆれ 柱が みしみしっと音をたてます。
久作は 地震だ!と思いますが、ゆれは すぐにおさまります。
ところが、久作の耳に、ほそい声がきこえてきます。その声は、昔遊んだ女の子の声。久作がひきよせられるように森の中に入っていき、声にひかれて、樹のこずえにのぼり、沖をながめてみると、海の色が暗くなって、潮が ぐんぐん 引いています。
つなみだ!つなみがくるんだ 早く 村の衆を 避難させなければ・・・。
でもどうすれば。今から走って行って一人一人に知らせては
まにあわない。
必死で考えを めぐらせた久作がとった行動というのは。
見開き2ページの六分の一に文が、あとは絵がかかれています。
「いねハゼ」に火をつけ村人を助けようとする久作。津波を見つめる村人。津波から復興を目指して働く人々の目が意志の強さをしめしているようです。
そして、「樹のおつげ」をしみじみと思い出す白髪の久作の目もどこか遠くをみつめています。
迫力のある絵を見ているだけで、津波の雰囲気が伝わってきます。















