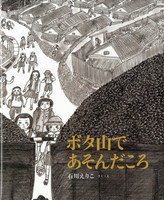|
ゆきみち/梅田俊作・佳子・さく/ほるぷ出版/1986年初版
ハチにさされた”ぼく”に
”うんと なくがええ、うんと ないて おぼえて おくんじゃよ”
たんぼの草刈をしているおばあちゃんたちに、冷たい麦茶を運んであげる途中で麦茶をこぼしてしまい、くやしくて大声で泣いている”ぼく”に
”おうおう、きばって ここまで きたのになあ。うんと なけ、きがすむまで なくがええ”
と、おばあちゃんはやさしい。
ともすれば、 ”男でしょ”といいたくなるところ。
お母さんに、あかちゃんがうまれ、吹雪の中を、お父さんとおばあちゃんの家に向かう”ぼく”。
ほとんどが雪の場面で、雪にかくれてしまいそうな”ぼく”とおとうさん。
はじめは、お父さんの足あとハンコのあとをおいかけていきますが、そのハンコも猛吹雪のなかでみえなくなりますが・・・・。
雪の冬と、春、夏、秋の場面が対照的です。
バスには車掌さんがのっていますから、少し前の時代。