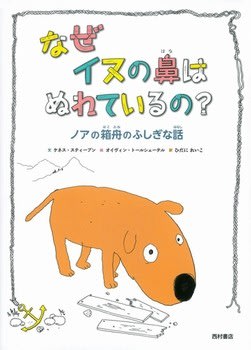青森のむかし話/青森県小学校国語研究会・青森児童文学研究会/日本標準/1975年
「若返りの水」と、おなじものかと思ったら、おわりかたもユニークです。
貧乏から抜け出したいと 毎日観音様に通って拝んでいたじさま。そこであきんど風のあん様とであいます。あん様は木綿問屋で、子どもが授かるように観音様においのりしていました。
じさまが三七、二十一日の終わりの日、いつものように観音様にお祈りしていると「ここに、ありがたい、護符が五枚あるから、おまえにさずける。この護符を一枚飲めば、二十ずつ年が若くなるから、たくさん若くなって、一生懸命働くがよい。そうすれば金持ちになるだろう」という声。
じさまが、もう、はやく若くなりたくて一枚の護符(お守り)をぺっろっと飲み込むと、すっと四十くらいになったど。もっと若くなりたくて、もう一枚護符を飲むと、こんどは二十ぐらいの若者に。
若くなったのはいいが、村へ帰ると「どこの若者だ」「みたことのねえ若者だな」と、誰も相手にしてくれない。
そこで、じさまは、観音様のところでであった木綿問屋で働かせてもらおうと町へでかけます。木綿問屋は蔵が七つもある大きな店で、着ているものを見た番頭は、相手にしてくれません。がやがやさわいでいるところへ、あん様がでてきて、きがついてくれます。
若くなった理由を聞かれ、護符のことをはなすと、あん様から「一枚、その護符をくれ」といわれ、うんとごちそうになったお礼に、護符をあん様にあげると、あん様は、すぐに、護符を飲み込み、すぐに二十五、六の若者になります。
それをみた、あん様の嫁っこも、びっくりぎょうてんして、「これだら、わたしが年上でつりあわねえから、わだしさも、一枚くれ」というので、しかたなく護符を一枚、嫁っこにやると、十七、八の嫁っこになってしまいます。
それをみていた、はげ頭の番頭も、一枚くれと頭をさげますが、一枚しかなくなった護符を、番頭にやることがおしくなったじさま。寝床で考えますが、どう考えても、ひとにやるのがおしくなって、「この一枚ば飲んでしまえば、だれにもとられないんだ」と、最後の一枚を、ぺっろと飲んでしまいます。つぎの朝、寝床の中には生まれたばかりのめんこい赤ん坊が。子どものいなかったあん様は、観音様のさずかりものだと、おおよろこびして、あかんぼうをそだでたぞ。
再度人生をやり直すことになったじさま。相方の若返った姿を見た嫁っこのおどろきが想像できる ほっこりした昔話です。