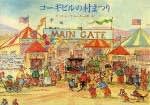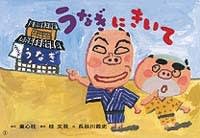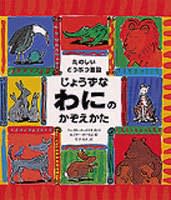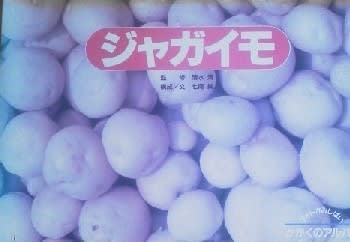チョコレート屋のねこ/スー・ステイントン・文 アン・モーティマー・絵 中川千尋・訳/ほるぷ出版/2013年
これといった名物のない、静かで退屈な村。その小さな村に、代々つづく小さなチョコレート屋がありました。お客はめったにきません。笑うことを忘れてしまったおじいさんがチョコレートをつくり、村人が、ねずみを取らないとばかにしていたねことのふたり暮らし。
ある日、おじいさんは ふと思いついて、チョコレートねずみをつくってみました。山積みになったチョコレートのひとつを ちょっぴかじってみたねこは そのおいさにびっくり。ほろ苦い味が、口いっぱいにひろがり、心がウキウキ弾んできて、ひげと前足が勝手に動い
てしまうほど。ねこは、こんなにおいしいんだもの、だれかにたべてもらわなくちゃと、おもしろいことを考えつきます。
ねこが、チョコレートねずみを、八百屋、パン屋、食料品屋、花屋、金物屋に置くと、そのチョコレートをたべたお店の人々は すばらしいことを思いつきます。
八百屋さんは、チェリーボンボン、果物の砂糖づけにチョコレートを絡めたもの
パン屋さんは、チョコレートをたっぷりはさんだチョコカステラや、チョコレートロールケーキ
食料品やさんは、いろんなナッツと はちみつ、ふしぎなかおりのスパイス ぎっしりつまった かたくて おおきな板チョコ
花屋さんとは、すみれや桜草の砂糖づけがのったチョコレート
金物屋は、星や月、さかなや、うさぎ、にわとりの形のチョコレート型をつくりました。
やがて、村の子どもたちもやってきて、いろんなアイディアをだし、村中の人が おじいさんに話しかけ、おじいさんも気軽に だれにでも 返事をするようになりました。それでもやっぱり おじいさんは 笑いません。
しかし、チョコレートねずみをたべてみたおじいさんに、なにかが、頭から、指先、そしてつま先へと かけぬけてたのです。おじいさんにも ひらめきましたとも。すてきで、ゆめのような、最高の考えが!
チョコレートの彫刻がうまれたのです。立派なお城、帆船、いまにも火をはきそうなドラゴン。たべるのはもったいない、すてきな作品。
村は、すっかり有名になり、おおぜいの人が、とおくから おじいさんのみせにやってくるようになりました。店の奥には、チョコレートの彫刻。
つぎからつぎへとでてくるチョコレートのなんと おいしそうなこと。上下の帯状にえがかれているチョコレートにも 注目です。どんな注文にもこたえられるおじいさんの 職人魂に、ねこが 火をつけてくれました。
巻末にはチョコレートの歴史、当初は不老長寿にきく魔力があると考えられていたこと、チョコレートは、ビター、ミルク、ホワイトの三つにわけられること、ねこにチョコレートを食べさせると病気になってしまうことなどにも、ふれられています。