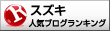昔、近くに勤めていながら恵比寿神社には行ったことが
無かったので、どんなものかと夫婦で十日ゑびす大祭を
見てみることにした。
交通手段はいつものごとく健康歩き。

出町柳の橋の欄干に松が生えていると新聞に載っていたので、
探してみるとありました。
松ぼっくりも付いていた。
数年前にど根性大根が有名になったが、これはど根性松である。

四条通りを越えて、団栗橋から恵比寿神社へ向かうことにしたが、
こちらは逆コースだったみたい。
参拝を済ませた人がぞくぞくと神社から出てくる。

逆周りで申し訳なく入らしてもらった。
参拝者の列は大和大路通りが歩けないほどびっしりと並んでいた。
由緒:公式HPより
京都ゑびす神社は西宮・大阪今宮神社と並んで日本三大ゑびすと
称され、「えべっさん」の名で親しまれています。
その起源は約800年前土御門天皇の建仁2年(1202年)に禅の祖と
いわれる栄西禅師が建仁寺建立にあたり、その鎮守として最初に
建てられたものです。
今日多くの方はゑびす様と言えば「商売繁盛の笹」をイメージされ
ますが、ゑびす信仰の象徴とも言える笹は元来京都ゑびす神社独自の
「御札」の形態が広まったものです。
笹は縁起物の松竹梅の竹の葉で「節目正しく真直に伸び」「弾力があり
折れない」「葉が落ちず常に青々と繁る」といった特徴から家運隆昌、
商売繁盛の象徴となりました。

巫女さんが舞っていた。


福笹を求める人で歩けないくらい。

建仁寺の摩利支尊天さんあたりから眺めたところ。
この先、人が多すぎて通り抜けできず。
摩利支尊天さんに戻ってきてしまった。

摩利支尊天さんにお参りすることにした。
狛猪で有名になった禅居庵の摩利支天は、特に開運、七難除けに
霊験があるとされる。


狛猪。


いたるところに猪さんがいる。
摩利支尊天さんをあとにして、同じく建仁寺の毘沙門天さんの
寅市に寄ってみることにした。

建仁寺の南門あたり。

毘沙門天堂は、建仁寺塔頭寺院両足院の鎮守さま。


狛虎。


こちらはお線香たての虎。
寅市でおみやげを買ってから、花見小路を通ってみた。

ここも観光客が多すぎて、撮った写真はこの1枚だけ。
疲れたので、帰りは京阪電車の祇園四条駅から乗ることにした。
道すがら以前から気になっていた「めやみ地蔵さん」にも寄って
みた。



本尊の地蔵菩薩像は大きく立派でびっくりした。
また今度じっくりとお参りしてみたい。
めやみ地蔵は京の町が大雨に見舞われ、鴨川が氾濫しそうになった
時に、この寺の地蔵菩薩に雨止みを祈ったところ効験が得られたこ
とから、いつしか「あめやみ地蔵」の「あ」の字がとれて「めやみ
地蔵」と呼ばれるようになったとのこと。
更に目の病に効験が有ったという縁起話が後世に付会されて、
「目疾地蔵」となった。
・・・・・
はじめて行った十日ゑびす大祭。
こんなに混雑しているとは思ってもみなかった。
帰りの京阪電車と叡山電鉄にも笹を持った人が多く乗っていた。
で、毘沙門天さんの寅市で買ったお土産はこれ。

樋屋さんが銅で折った折鶴と亀。
飾っておくと錆びて味が出るといっていた。
縁起物なので、いつも目に付くところに飾ることにする。
無かったので、どんなものかと夫婦で十日ゑびす大祭を
見てみることにした。
交通手段はいつものごとく健康歩き。

出町柳の橋の欄干に松が生えていると新聞に載っていたので、
探してみるとありました。
松ぼっくりも付いていた。
数年前にど根性大根が有名になったが、これはど根性松である。

四条通りを越えて、団栗橋から恵比寿神社へ向かうことにしたが、
こちらは逆コースだったみたい。
参拝を済ませた人がぞくぞくと神社から出てくる。

逆周りで申し訳なく入らしてもらった。
参拝者の列は大和大路通りが歩けないほどびっしりと並んでいた。
由緒:公式HPより
京都ゑびす神社は西宮・大阪今宮神社と並んで日本三大ゑびすと
称され、「えべっさん」の名で親しまれています。
その起源は約800年前土御門天皇の建仁2年(1202年)に禅の祖と
いわれる栄西禅師が建仁寺建立にあたり、その鎮守として最初に
建てられたものです。
今日多くの方はゑびす様と言えば「商売繁盛の笹」をイメージされ
ますが、ゑびす信仰の象徴とも言える笹は元来京都ゑびす神社独自の
「御札」の形態が広まったものです。
笹は縁起物の松竹梅の竹の葉で「節目正しく真直に伸び」「弾力があり
折れない」「葉が落ちず常に青々と繁る」といった特徴から家運隆昌、
商売繁盛の象徴となりました。

巫女さんが舞っていた。


福笹を求める人で歩けないくらい。

建仁寺の摩利支尊天さんあたりから眺めたところ。
この先、人が多すぎて通り抜けできず。
摩利支尊天さんに戻ってきてしまった。

摩利支尊天さんにお参りすることにした。
狛猪で有名になった禅居庵の摩利支天は、特に開運、七難除けに
霊験があるとされる。


狛猪。


いたるところに猪さんがいる。
摩利支尊天さんをあとにして、同じく建仁寺の毘沙門天さんの
寅市に寄ってみることにした。

建仁寺の南門あたり。

毘沙門天堂は、建仁寺塔頭寺院両足院の鎮守さま。


狛虎。


こちらはお線香たての虎。
寅市でおみやげを買ってから、花見小路を通ってみた。

ここも観光客が多すぎて、撮った写真はこの1枚だけ。
疲れたので、帰りは京阪電車の祇園四条駅から乗ることにした。
道すがら以前から気になっていた「めやみ地蔵さん」にも寄って
みた。



本尊の地蔵菩薩像は大きく立派でびっくりした。
また今度じっくりとお参りしてみたい。
めやみ地蔵は京の町が大雨に見舞われ、鴨川が氾濫しそうになった
時に、この寺の地蔵菩薩に雨止みを祈ったところ効験が得られたこ
とから、いつしか「あめやみ地蔵」の「あ」の字がとれて「めやみ
地蔵」と呼ばれるようになったとのこと。
更に目の病に効験が有ったという縁起話が後世に付会されて、
「目疾地蔵」となった。
・・・・・
はじめて行った十日ゑびす大祭。
こんなに混雑しているとは思ってもみなかった。
帰りの京阪電車と叡山電鉄にも笹を持った人が多く乗っていた。
で、毘沙門天さんの寅市で買ったお土産はこれ。

樋屋さんが銅で折った折鶴と亀。
飾っておくと錆びて味が出るといっていた。
縁起物なので、いつも目に付くところに飾ることにする。