初詣は伝統?
神前結婚式は伝統?
見合い結婚は伝統?
天皇現人神は伝統?
いいえ、み~~~んな明治以降のお話です。
いまのような初詣が始まったのは、ようやく明治も中期からですし、
神前結婚も明治30年代以降のことですし、
見合い結婚は、明治政府が、恋愛を邪なものとして明治中期から「見合い結婚」を強力に推進したもの。それまでの長~~~い日本の伝統は、ずっと恋愛結婚(男女の結び付きの自由)でした。
もちろん、天皇現人神などという思想は、江戸の後期国学や水戸学の思想で、一部の特殊な人のものでしかなく、ぜんぜん伝統などではありません。
靖国神社は、政府がつくった施設で、神社ですらありません(明治2年に明治政府がつくった「東京招魂社」を10年後に神社と改名)。古来の神社ではなく、明治政府のつくった新興宗教=政府神道の施設なのです。
みな、明治維新を成し遂げた志士たちが、自らの権力を正当化する必要から拵えた代物でしかないのです。
神道を排して仏教による国づくりをした聖徳太子とは正反対の廃仏毀釈が、明治維新政府のイデオロギーでした。
こういう類の話は、歴史家に聞けば山のようにあり、大論文になってしまいますが、
肝心なことは、安倍首相の一派や日本会議にあつまる人々の言う日本の伝統なる話は、元からデタラメで、みな明治維新政府の作成でしかない、という歴然たる事実を明晰に自覚することです。
ついでに言えば、大安とか仏滅などとカレンダーに書かれているのは、無根拠の俗信で明治政府により一度は廃止(=これは明治政府が正しい)されましたが、昭和のはじめにカレンダー会社の販売戦略で記載されたものでしかなく、お菓子会社よる「バレンタインデー」と同じです。
考えることなく従う、というのは、これまた明治維新以後の日本人の特徴ですが、
われわれ日本人も、そろそろ自分で考える=根拠を知るという脳作業を始めたいもの、と思います。
武田康弘
コメント
特に維新賛美の流れは司馬遼太郎の作風で司馬史観なる見方もあり、ノンフィクションのように受け入れている人も多いのではないでしょうか?
ノンフィクションとして見ているのは間違いないと思いますが、そもそも歴史とは何か、という問い自体がないので、歴史を「事実」の集まりとしてしか意識できない人が多数でしょう。
自分の目で見、自分の頭で考え、自分の心身で感じる人でないと、現実をよく知ることはできないでしょう。
理論に頼り、権威に頼り、ではなく、自分で調べ、自分で考える自由な人として生きたいですよね~~~
シェアされた先から、安倍首相の敬愛する祖父ー岸信介についてのコメントがありましたので、
以下にご紹介します。
『法学館憲法研究所』のホームページから。
“昭和の妖怪”岸信介―戦前との連続性
H.T.記
1957年は、東条内閣の重要閣僚として日米開戦の詔勅に署名し、戦後A級戦犯として逮捕された岸信介が首相になり、戦争の指導層が戦後も引き続いて日本の指導層となった象徴的な年となりました。特殊日本的な「戦前との連続性」です。ナチズムを生んだドイツでは、戦後に旧ナチの幹部が政界の指導者として復活することは決してありえないことでした。戦争国家体制と民主主義・人権の抑圧は不可分の関係にあります(治安維持法体制)。この体制の責任者が日本の指導者となったことは、現在に至るまで日本のあり方に多大な影響を与えています。
岸は山口県の官吏の家に生まれ、大資産家である実家・岸家の養子となりました。島根県令などの要職を務めた政治家である曽祖父の残像が幼い頃から色濃く刻み込まれたと言われます。東大時代は、当時の右翼のトップリーダーだった北一輝や大川周明に面会を申し入れ、深い影響を受けました。天皇制絶対主義を唱える憲法学者・上杉慎吉に見込まれ後継者にと誘われましたが、当時の農商務省に入り、戦時統制経済を立案・推進した「革新官僚」を代表する存在となります。間もなく、東条らと共に満州国の5大幹部の1人として植民地経営を指導、軍・財・官界にまたがる広範な人脈を作り、政治家としての活動の基礎を築きます。東条内閣では商工相、軍需次官を歴任し戦時経済を指導しました。
45年9月、岸はA級戦犯容疑者として逮捕され、巣鴨拘置所に収監されました。しかし、アメリカの対日政策が大きく転換(逆コース)、多くの戦犯と共に不起訴となり釈放されます。さらに、52年4月、単独講和条約の発効に伴って公職追放解除になりました。直後に復古的な「自主憲法制定」を最大の目標に掲げることを主導して「日本再建連盟」を設立、翌年には衆議院議員になりました。56年の自民党総裁選では巨額の資金をばらまき、金権総裁戦の原型を作りました。首相は60年の安保国会後に退陣しましたが、以後も田中角栄と並ぶキングメーカーとして、89年に90歳で没するまで政界に隠然たる影響力を及ぼし、「昭和の妖怪」と呼ばれました。岸の政治の最終的な目標は最初から最後まで「自主憲法の制定」でした。
岸は晩年のインタビューで語っています。「大東亜共栄圏は随分と批判があったけど、根本の考え方は間違っていません。日本が非常に野心を持ってナニしたように思われるけど、そうではなく…」(塩田潮著「『昭和の怪物』岸信介の真実」)。
戦前との連続性は今、戦争を知らない世代によって「日本の伝統・文化・歴史の尊重」というスローガンで語られています。
岸に代表される政治家については、①戦前との連続性の他、②戦前はファシズムに傾倒して国民を「鬼畜米英」に誘導したことと対照的に戦後は民主主義を標榜しアメリカへの従属を推進した無節操(非連続)、及び③戦争責任が話題になりました。日本国憲法については「押付け」が論じられています。しかし、GHQによる「逆コース」の支配(「逆押付け」)がなく、日本の民主化が促進されていたならば、戦争を指導・推進して内外に天文学的な犠牲者を出した政治家・官僚の政治的・道義的な免責はあり得たのか、問題となるところです。



























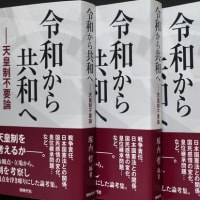

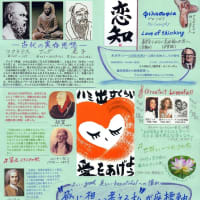







こんな話もあるようです。
http://www.bdeai.net/omiai/2.html
昔の日本は恋愛というより野合だったんじゃないかなぁ。女性の地位は低い時代ですからね。
バレンタインデーはありますよね、
創造したのはお菓子の方で、さすがにそれは知っていると思いますよ。
見合いが主流になったのは、明治の半ば以降のことです。富国強兵路線を固めた明治政府が政策として見合い結婚を強力に勧めたことは、風俗の歴史としても有名です。
バレンタインデーは、まったく意味の違う話で、日本では女性から男性へのチョコレートの日になりました(笑)。
知りませんでした。
http://www.be-takumi.jp/kae_oonishi_column/8
これにもあるんですが、盛んになったのは明治以降で、それ以前にも庶民の間でお見合い自体はありました・・というのしか見つかりませんでした。
興味あるので、参考にした文献とかあったら教えて頂きたいのですが、あと明治政府が強力に勧めたって何か通達とかあったんでしょうか?
バレンタインデーはチョコレート会社うまくやりましたよね~。
「高砂業(たかさごぎょう)」と呼ばれる「仲人業」があらわれたのは明治時代で、
1880年(明治13年)に山口吉兵衛が大阪で始めた「養子女婿嫁妻妾縁組中媒取扱所」がその元祖と言われ、1884年(明治17年)には、東京、日本橋に「渡辺結婚媒介所」が誕生しています。(『日本婚姻史』中山太郎著、『明治大正史・世相編』柳田邦男偏)
・・・・・・・・
そして1933年(昭和8)には、東京市に公立の結婚相談所が設けられました。
そして、戦前の日本では「お見合い結婚」が、一般的に行われるようになったのです。
当時、人口問題研究所が行った結婚調査によると、約70%の人がお見合いで結婚をしたという記録が残っています。
ーーーーーー
明治政府によ結婚をはじめとする個人生活への介入=強力な誘導は、枚挙に暇がありません。具体的には、岩波や小学館の「近代日本の歴史」や民俗学の書をお読みください。
なお、見合い結婚の勧めは、男女の個人間の性的自由の抑圧とセットです。性という人間性の根源領域への国家管理としての「見合い結婚」という意味です。
愛は人工物、恋は自然物だと思います。
そして、人工物は創作者に都合よく作られているが自然物は(存在するとして)神の意図の下に造られているのでは、ないかと思います。
そーいや、現人神だなんて… 古墳を調べるれば、科学的にちゃんと解るのになぁ~。困る連中がいるのかなU+2047
貴重なお話、ありがとうございます!
だから何?
初詣するなって事?見合い結婚はいけないの?
考えずに従うのは明治以降の日本人の傾向?
日本の礎となって命を落としたご先祖様達に頭を下げるのに、何でそんな解釈になるの?
よく事実を知り、なぜそういう風習ができたのかも知り、その上で、普遍性のある優れた判断ができる人間になることが、自他の徳と得を生むのです。
個々人が豊かで優れた人、魅力ある人になってはじめて、その社会ー国もよいものになります。
そういう話です。
「伝統は一世代、三十年で作られる」
私はただの歴史好きのノンポリですが、保守系右側の人が「伝統を守れ!」と‟何も知らず考えずに主張している時(特に「‟女性”天皇に反対。なぜなら天皇=男性は、日本古来の伝統だから」とTVで堂々と言い放った、街角インタビューに答えた50代のサラリーマン風の男性には恐れ入りました(笑))、このような「現代、あるいは戦後からの‟新興伝統”の例を挙げ」
「御存じのように、あなたたちの大嫌いな韓国は、『伝統は三十年で作られる』を実行する名手ですけどね。」と(笑)
まあ、これはリベラル左側の人も同じですけどね。
SEALDSの若い子たちとか、かつて左翼運動していた万年青年のジジババに煽られ、現実も理論も知らず考えないまま、青年らしい「己が個人的ルサンチマンの解消」に無意識に動かされ、さかりが来た動物のように騒いでただけに見えなくもないですし。
(ある意味、彼らは古代から続く「村落共同体のハレの日の祭り」「集団内の内輪盛り上がり(外部世界の現実と向き合わない)」と同じで、‟最も保守的”であったと言えるかもしれません)