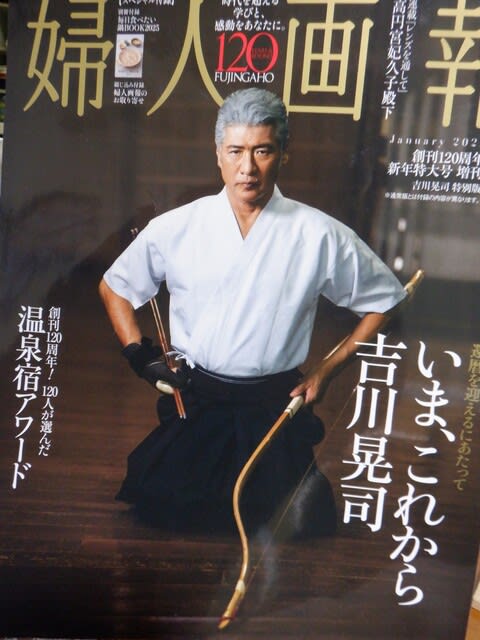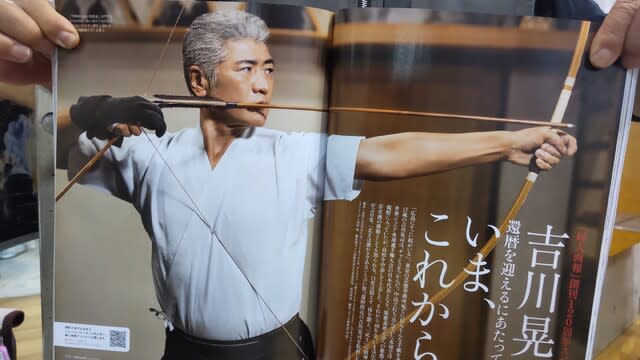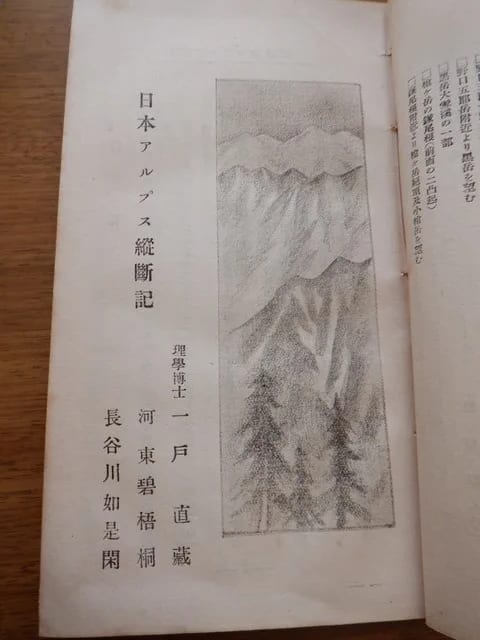時折、絵を描いて投稿するが、はがき投函後数日は新聞の発言欄をチェックしていて、1週間もすると不採用かなと勝手に決めて見なくなる。
友達が見つけてくれることもあるが、匿名「さゆり」で投稿すると誰にも見つけられないし自分でも見損なうことがある。
1か月後に新聞社から図書カードが送られてくる。
そこには「12月7日掲載」と書かれていて、あ~先週新聞を資源ごみに出してしまったわ~と、載ったのを確認できず後の祭り。
12月7日は、小松で講習会があったので、婆様の2日分の食事を作り、自分もバタバタと朝食を摂って出かけたので、新聞はお悔やみ欄のチェックだけしかしていない。
その日はホテル泊りで、翌日の朝食時にMちゃんとSちゃんと会長とテーブルを囲んでいた時に「新作発表!」と、スマホを見せたので、少なくとも3人には見てもらえたことになる。
翌日帰ってから、12月8日の新聞だけ見て廃棄したので、結局12月7日はスルーした。

この大判焼きは、通勤途上のタイ焼き屋さんで買った。
寒い日で、夕方道のわきに車を停めて、新聞紙に包まれたのを抱えて出てくる客を見たら急に自分も食べたくなった。
たったひとつ買うのは気が引けるので、めったに寄らないが。
父が寝たきりになって病院にいたときも、たった一つを買った。
「太鼓焼きが食いたいなぁ」と、言ったからだった。
流動食に近い食事になってから、看護師に内緒で少しずつ口に入れていたが、やはり喉につまらせないかと心配になって、ほんの一口しか食べさせられず。本当は、がぶりと食べたかったのではないだろうかと思ったことだった。
たったひとつを、白い小さな袋に入れてもらって冷めないうちにがぶっと食べるつもりだったが、何となく半分に割って、誰も相手がいないのに半分この言葉が浮かんで、皿に入れてから、「そうだ!描こう」と思った。
しかし、単純すぎてなかなかそれらしくならなくて、色を重ねていくうちに大判焼きはすっかり冷たくなったけれど、そのうち誰かと一緒に食べたような時間が持てたような気になった。
最後はお茶を入れて、電子レンジでチン。
今度はタイ焼きを買ってこよう!!