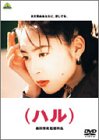人はどこまでも利己的で残酷だけれど・・・
* * * * * * * * * *
「このミステリがすごい!2012年版」国内編、
週刊文春ミステリーベスト10」国内部門、
双方において第1位。
そして第2回山田風太郎賞受賞で、3冠を達成したこの作品。
私は特に権威に弱いワケではありませんが、
こうなるとさすがに面白いのだろうと興味がそそられ、抗うことができません。
ジェノサイド―――つまり大量殺戮のことです。
何とも不穏な題名ですが、すばらしくスケールが大きく、冒険に満ちたストーリーで、
ハリウッド映画も真っ青。
だからといって単にエンタテイメント性だけが突出しているわけではありません。
私たち人間の"本性"に迫りつつ、科学に裏付けされたそのストーリーは、
読み始めたらやめられません。
イエーガーという男が、米政府の密命を受け、傭兵としてアフリカ、コンゴへ向かいます。
彼には難病で余命幾ばくもない息子がおり、
その治療費のために仕事を引き受けたのですが、
その仕事というのが、何とも過酷で非情・・・。
一方日本では、薬学を学ぶ研人という青年が、亡き父から不可解なメッセージを受け取ります。
一定期間内に極秘で、ある薬を完成させるようにと。
日本とコンゴ、同時進行でストーリーが進んでいきますが、
果たしてその接点とは・・・?
コンゴというのは、内乱で大変なことになっている地です。
ツチ族とフツ族の争いとはいいますが、
その背景には古くからの欧米大国との関係が深く絡んでいる。
いわばエゴ丸出しの大国に食い物にされているといってもいい。
あまりにも殺戮が繰り返されたために、兵士が不足し、
子供たちが誘拐されて、新たな兵に仕立てられているという・・・。
さて、そのコンゴの深い森の中に、ムブティという一族が住んでいます。
私たちには「ピグミー」として知られる独特の風貌をした一族です。
人類発祥の地といわれるこの地で、
いま、あらたな「新人類」が誕生しているという。
人間の引き起こす戦争や残虐性について、こんなセリフが書かれています。
「いいかね、戦争というのは形を変えた共食いなんだ。
そして人間は、知性を用いて共食いの本能を隠蔽しようとする。
政治、宗教、イデオロギー、愛国心といった屁理屈をこねまわしてな。
しかし根底にあるのは獣と同じ欲求だ。
領土をめぐって人間が殺し合うのと、
縄張りを侵されたチンパンジーが怒り狂って暴力を振るうのと、
どこが違うのかね?」
「善なる側面が人間にあるのもひていはしないよ。
しかし、善行というのは、ヒトとしての本性に背く行為だからこそ美徳とされるのだ―――。」
非常に悲観的な見方ではありますが、
このストーリー中、いくつも人間の残虐性を見せられた後では身にしみます。
けれども確かに、自分の身をなげうっても他人のために尽くす者はいるのです。
その一人が、日本の研人というわけで・・・。
日本のいかにもモテそうにないサエない青年が、
韓国青年と力を合わせてあることをやり遂げるのです。
ヒトはどこまでも利己的に残酷になれるけども、
また逆に人のために命を投げ出すこともできる。
それがあるからこそ、私たちは未来を信じられるのだなあ・・・と、
読後の虚脱感の中で思うのでした。
私たちが日頃「宇宙人」として認識している姿のイキモノは、
実はこの地球の「未来人」だったのかなあ・・・などと思ったりして。
「ジェノサイド」高野和明 角川書店
満足度★★★★★
 | ジェノサイド |
| 高野 和明 | |
| 角川書店(角川グループパブリッシング) |
* * * * * * * * * *
「このミステリがすごい!2012年版」国内編、
週刊文春ミステリーベスト10」国内部門、
双方において第1位。
そして第2回山田風太郎賞受賞で、3冠を達成したこの作品。
私は特に権威に弱いワケではありませんが、
こうなるとさすがに面白いのだろうと興味がそそられ、抗うことができません。
ジェノサイド―――つまり大量殺戮のことです。
何とも不穏な題名ですが、すばらしくスケールが大きく、冒険に満ちたストーリーで、
ハリウッド映画も真っ青。
だからといって単にエンタテイメント性だけが突出しているわけではありません。
私たち人間の"本性"に迫りつつ、科学に裏付けされたそのストーリーは、
読み始めたらやめられません。
イエーガーという男が、米政府の密命を受け、傭兵としてアフリカ、コンゴへ向かいます。
彼には難病で余命幾ばくもない息子がおり、
その治療費のために仕事を引き受けたのですが、
その仕事というのが、何とも過酷で非情・・・。
一方日本では、薬学を学ぶ研人という青年が、亡き父から不可解なメッセージを受け取ります。
一定期間内に極秘で、ある薬を完成させるようにと。
日本とコンゴ、同時進行でストーリーが進んでいきますが、
果たしてその接点とは・・・?
コンゴというのは、内乱で大変なことになっている地です。
ツチ族とフツ族の争いとはいいますが、
その背景には古くからの欧米大国との関係が深く絡んでいる。
いわばエゴ丸出しの大国に食い物にされているといってもいい。
あまりにも殺戮が繰り返されたために、兵士が不足し、
子供たちが誘拐されて、新たな兵に仕立てられているという・・・。
さて、そのコンゴの深い森の中に、ムブティという一族が住んでいます。
私たちには「ピグミー」として知られる独特の風貌をした一族です。
人類発祥の地といわれるこの地で、
いま、あらたな「新人類」が誕生しているという。
人間の引き起こす戦争や残虐性について、こんなセリフが書かれています。
「いいかね、戦争というのは形を変えた共食いなんだ。
そして人間は、知性を用いて共食いの本能を隠蔽しようとする。
政治、宗教、イデオロギー、愛国心といった屁理屈をこねまわしてな。
しかし根底にあるのは獣と同じ欲求だ。
領土をめぐって人間が殺し合うのと、
縄張りを侵されたチンパンジーが怒り狂って暴力を振るうのと、
どこが違うのかね?」
「善なる側面が人間にあるのもひていはしないよ。
しかし、善行というのは、ヒトとしての本性に背く行為だからこそ美徳とされるのだ―――。」
非常に悲観的な見方ではありますが、
このストーリー中、いくつも人間の残虐性を見せられた後では身にしみます。
けれども確かに、自分の身をなげうっても他人のために尽くす者はいるのです。
その一人が、日本の研人というわけで・・・。
日本のいかにもモテそうにないサエない青年が、
韓国青年と力を合わせてあることをやり遂げるのです。
ヒトはどこまでも利己的に残酷になれるけども、
また逆に人のために命を投げ出すこともできる。
それがあるからこそ、私たちは未来を信じられるのだなあ・・・と、
読後の虚脱感の中で思うのでした。
私たちが日頃「宇宙人」として認識している姿のイキモノは、
実はこの地球の「未来人」だったのかなあ・・・などと思ったりして。
「ジェノサイド」高野和明 角川書店
満足度★★★★★















 さて、イーストウッド監督作品なので、久しぶりにまた出てきました~。
さて、イーストウッド監督作品なので、久しぶりにまた出てきました~。 007よりはハリキリがいがある。
007よりはハリキリがいがある。 でも、実はこの作品を見るのは、あんまり乗り気ではなかったんだよね。
でも、実はこの作品を見るのは、あんまり乗り気ではなかったんだよね。 うん、ジャンル的に、政治ネタと言うか社会ネタがどうも苦手なんだなあ・・・。
うん、ジャンル的に、政治ネタと言うか社会ネタがどうも苦手なんだなあ・・・。 そう。けれどこの作品、フーバー長官と腹心の部下の秘められた愛も描かれている
そう。けれどこの作品、フーバー長官と腹心の部下の秘められた愛も描かれている
 ところがですね、そういう功績の一方で、
ところがですね、そういう功績の一方で、 すごい自己顕示欲だよね・・・
すごい自己顕示欲だよね・・・
 結局なんだかんだと言いながら、そういうフーバーをトルソンは愛したわけなんだな・・・。
結局なんだかんだと言いながら、そういうフーバーをトルソンは愛したわけなんだな・・・。 正直気色悪いわな・・・。
正直気色悪いわな・・・。 そうだねえ・・・。
そうだねえ・・・。