A sober colouring × 豊旗雲

謹厳の色彩― William Wordsworth×万葉集
The innocent brightness of a new-born Day Is lovely yet;
The Clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from an eye That hath kept watch o’er man’s mortality;
Another race hath been,and other palms are won.
Thanks to the human heart by which we live. Thanks to its tenderness,its joys,and fears,
To me the meanest flower that blows can give Thoughts that do often lie too deep for tears.
生まれた新たな陽の純粋な輝きは、今もまだ瑞々しい
沈みゆく陽をかこむ雲達に、
謹厳な色彩を読みとる瞳は、人の死すべき運命を見つめた瞳
時の歩みを経、もうひとつの掌に勝ちとれた
生きるにおける人の想いへの感謝 やさしき温もり、歓び、そして恐怖への感謝
慎ましやかに綻ぶ花すらも、私には涙より深く心響かせる
That hath kept watch o’er man’s mortality
生命の終わりを見つめた瞳は、太陽の生と眠りを見つめた瞳に同じ。
そんなふうに太陽と生命をリンクし謳う作者、ウィリアム・ワーズワスはイギリスの詩人です。
自然の風光に心理や摂理を詠みこんだ詩が特徴で、この一節は彼の真骨頂かなって思います。
The Clouds that gather round the setting sun Do take a sober colouring
荘厳ですね、雲と太陽の共鳴っていうのかな?
ソンナ感じの空が広がった今夕は、雲は幾層にも流れて陰翳の煌めきに満ちました。
落日や旭日は古来から尊ばれ、畏敬を籠めた歌や詩に詠まれています。
沈んで消えてしまう太陽、けれど必ず朝を輝かせる姿は「再生」のイメージ。
それは日本に限らず世界中で同じように象徴とされているなと、Wordsworthからも想います。

渡津神の 豊旗雲に入陽さし 今宵の月夜 清明けくありこそ 中大兄
海神が大海原に翻す豊穣呼ぶ雲の旌旗に今、夕陽が映えわたる
もう日は鎮まり夜は訪れるが、今宵の月下は清らかに明るくあってほしいが
海と雲と太陽、そして月。
黄昏の雄渾な光輝が静謐に明るむ夜へ繋がれと祈る、日夜の境界に予祝する叙情歌です。
これは『万葉集』巻一に納められる雑歌で作者の中大兄は中大兄皇子、後の天智天皇になります。
冒頭の「渡津神」は「わたつみ」と読み、海神または海原を指す言葉です。
この「津」は水の満ちる場所、または水辺を指す語で、地名にも「大津=琵琶湖畔」「沼津=駿河湾」などがあります。
満ちる水を渡る神=海神という意味で「渡津神」と表記していますが「綿津見」「海神」とも書いてワタツミと読みます。
綿津見という表記は、波が白く砕ける様子が真白い綿のよう見えるからでしょうね。
豊旗雲はドンナ雲なのか?
端午の節句に揚げる吹流しが風に棚引くような雲、旗のように長く延びた雲、など諸説あります。
いずれにしても「旗」のイメージがある雲で、この旗が古来は様々な形状が在った為に解釈も様々です。
雲、特に積乱雲などが包含する雷は「稲妻」とも書きますが古来、落雷=稲の豊作を齎すと考えられていました。
そして雲は万物潤す雨を降らせて豊穣を育みます、そんな所から「豊旗雲」という言葉は豊穣の力称える美称として訳しました。
また歌には「海神の豊旗雲」となっています、日本の海神では素戔嗚尊が有名ですが海が波立つよう好戦的なほど荒ぶる闊達な神です。
そんなイメージから旗=幟、勢いのある旗のイメージで「旌旗」とし、豊穣を呼び起こす力のある雲で作った海神の旗としました。
そして「月夜」が何を意味するのか?ってことですが、古来より月は生死を司ると言われています。
実際の統計データでも満月や新月など月の満ち欠けが、出生率や死亡率に関連するそうです。
そして海の満潮や干潮も月の運行や満ち欠けに関連することが、科学的にも知られています。
そう考えていくと主題の歌は、海と月の呼応が自然科学的にも読める面白さがありますね。
黄昏に海神の雲を見つめ謳いあげる想いは、訪れる月夜の清明に何を祈るのか?
それは連載中の短編「Lost article 天津風 act.3」にある雅人の想いかもしれません。
そして上段の詩「a new-born Day」「a sober colouring from an eye That hath kept watch o’er man’s mortality」と同じです。

【引用詩文:William Wordsworth「Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood」XI】
【引用詩歌:中大兄『万葉集』より】
blogramランキング参加中!
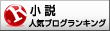
 にほんブログ村
にほんブログ村

謹厳の色彩― William Wordsworth×万葉集
The innocent brightness of a new-born Day Is lovely yet;
The Clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from an eye That hath kept watch o’er man’s mortality;
Another race hath been,and other palms are won.
Thanks to the human heart by which we live. Thanks to its tenderness,its joys,and fears,
To me the meanest flower that blows can give Thoughts that do often lie too deep for tears.
生まれた新たな陽の純粋な輝きは、今もまだ瑞々しい
沈みゆく陽をかこむ雲達に、
謹厳な色彩を読みとる瞳は、人の死すべき運命を見つめた瞳
時の歩みを経、もうひとつの掌に勝ちとれた
生きるにおける人の想いへの感謝 やさしき温もり、歓び、そして恐怖への感謝
慎ましやかに綻ぶ花すらも、私には涙より深く心響かせる
That hath kept watch o’er man’s mortality
生命の終わりを見つめた瞳は、太陽の生と眠りを見つめた瞳に同じ。
そんなふうに太陽と生命をリンクし謳う作者、ウィリアム・ワーズワスはイギリスの詩人です。
自然の風光に心理や摂理を詠みこんだ詩が特徴で、この一節は彼の真骨頂かなって思います。
The Clouds that gather round the setting sun Do take a sober colouring
荘厳ですね、雲と太陽の共鳴っていうのかな?
ソンナ感じの空が広がった今夕は、雲は幾層にも流れて陰翳の煌めきに満ちました。
落日や旭日は古来から尊ばれ、畏敬を籠めた歌や詩に詠まれています。
沈んで消えてしまう太陽、けれど必ず朝を輝かせる姿は「再生」のイメージ。
それは日本に限らず世界中で同じように象徴とされているなと、Wordsworthからも想います。

渡津神の 豊旗雲に入陽さし 今宵の月夜 清明けくありこそ 中大兄
海神が大海原に翻す豊穣呼ぶ雲の旌旗に今、夕陽が映えわたる
もう日は鎮まり夜は訪れるが、今宵の月下は清らかに明るくあってほしいが
海と雲と太陽、そして月。
黄昏の雄渾な光輝が静謐に明るむ夜へ繋がれと祈る、日夜の境界に予祝する叙情歌です。
これは『万葉集』巻一に納められる雑歌で作者の中大兄は中大兄皇子、後の天智天皇になります。
冒頭の「渡津神」は「わたつみ」と読み、海神または海原を指す言葉です。
この「津」は水の満ちる場所、または水辺を指す語で、地名にも「大津=琵琶湖畔」「沼津=駿河湾」などがあります。
満ちる水を渡る神=海神という意味で「渡津神」と表記していますが「綿津見」「海神」とも書いてワタツミと読みます。
綿津見という表記は、波が白く砕ける様子が真白い綿のよう見えるからでしょうね。
豊旗雲はドンナ雲なのか?
端午の節句に揚げる吹流しが風に棚引くような雲、旗のように長く延びた雲、など諸説あります。
いずれにしても「旗」のイメージがある雲で、この旗が古来は様々な形状が在った為に解釈も様々です。
雲、特に積乱雲などが包含する雷は「稲妻」とも書きますが古来、落雷=稲の豊作を齎すと考えられていました。
そして雲は万物潤す雨を降らせて豊穣を育みます、そんな所から「豊旗雲」という言葉は豊穣の力称える美称として訳しました。
また歌には「海神の豊旗雲」となっています、日本の海神では素戔嗚尊が有名ですが海が波立つよう好戦的なほど荒ぶる闊達な神です。
そんなイメージから旗=幟、勢いのある旗のイメージで「旌旗」とし、豊穣を呼び起こす力のある雲で作った海神の旗としました。
そして「月夜」が何を意味するのか?ってことですが、古来より月は生死を司ると言われています。
実際の統計データでも満月や新月など月の満ち欠けが、出生率や死亡率に関連するそうです。
そして海の満潮や干潮も月の運行や満ち欠けに関連することが、科学的にも知られています。
そう考えていくと主題の歌は、海と月の呼応が自然科学的にも読める面白さがありますね。
黄昏に海神の雲を見つめ謳いあげる想いは、訪れる月夜の清明に何を祈るのか?
それは連載中の短編「Lost article 天津風 act.3」にある雅人の想いかもしれません。
そして上段の詩「a new-born Day」「a sober colouring from an eye That hath kept watch o’er man’s mortality」と同じです。

【引用詩文:William Wordsworth「Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood」XI】
【引用詩歌:中大兄『万葉集』より】
blogramランキング参加中!



















