名も知らぬまま、けれど輝きは

正午の初夏、皐月―万葉集×William Wordsworth
正午の初夏は青空やわらかい、今日のこの辺です。
この時期は光が透けるよう明るくて綺麗、草も木も光って見える。
瓦屋根きらめくトコなんて、アノ五月の歌の通りだなって思います。笑
写真は近場の森にある花木です、で、この名前を未だに知りません。笑
卯の花と似た白い星型が可愛いんですけど、持っている山野草ハンドブックに載ってない。
ちょっとビジターセンターに行ってみたら良いのかもしれないけど、なんか行きそびれてます。
どなたかご存知の方いらしたら是非、教えてくれませんか?

宇の花も いまだ咲かねば霍公鳥 佐保の山辺に 来鳴き響もす 大伴家持
卯の花もまだ咲かず夏は来ない、
だから時鳥も春の女神が坐ます山に来て、時告げ鳴く聲を響かす。
夏を待ち切れないと、佐保姫のようなあなたと逢瀬する時を今だと言ってるけど?
昨日も卯の花と霍公鳥=ホトトギス・時鳥のこと書きましたけど。
この歌はすこし早い時期に鳴きだした時鳥に、恋逸る気持を解釈してみました。
時ならず 玉をぞ貫ける宇の花の 五月を待たば久しくあるべみ 詠み人知らず
まだ時は訪れない、
けれど皐月玉に縫う卯の花が咲く五月を待つと、待ち遠しくて。
この心の玉緒を貫くあなたのこと、早く逢いたくて待ち遠しくて、早月の初夏を待ち兼ねて。
この「玉」は薬玉のことで、卯の花を用いて五月に作るものを皐月玉ともいいます。
薬玉は今でも工芸品でありますが、綿を色糸でかがった美しいもので女の子の魔除けになる装飾品です。
ですが昔は老若男女すべてが用いたもので、綿の中に薬=薬草や木の実などを詰めて糸でかがり玉に作りました。
その表面を色糸や花を挿して綺麗に作りあげると贈物として、恋する相手へも歌を添え贈ることもあったようです。
たしか『源氏物語』にも光源氏が花散里へ薬玉を贈るシーンがあったかな?ちょっと曖昧な記憶ですみませんが、笑
ソンナ意味のある「玉」なので相聞歌に解釈してみました。
また、歌には5月=サツキを「五月」と書いていますが、解釈は三種に書き分けてみました。
古い字を用いる「皐月」を古来伝統の薬玉に、早く逢いたい想いに「早月」と掛けてあります。
5月を日本ではこんなふう三つの表記があることは、解釈を広げるのに楽しいです。
二つの歌とも共通するのが卯の花咲く季節への心弾みです。
五月の時を待ち兼ねて、卯の花や時鳥に早く時を告げてほしいと願う。
そんな五月という季節に籠めた人の想いが謳われているなって想います。

Then sing, ye Birds, sing, sing a joyous song!
And let the young Lambs bound
As to the tabor’s sound!
We in thought will join your throng,
Ye that pipe and ye that play,
Ye that through your hearts to-day
Feel the gladness of the May!
歌ってよね、鳥たちよ、歓びの歌を詠い、謳おう
子羊たちは踊り跳ねてよ、
小太鼓の音に合わせるよう楽しく。
私たちは愉しげな君たちに想いを馳せ、
笛を吹き遊ぶ君たちよ、
今日という日に君たちの心に想い馳せる、
皐月の輝ける歓び満ちる君たちに。
William Wordsworth「Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood」X
もうまんま五月の喜びを謳っちゃっています。
昨日掲載したIIIに続く一節ですが、イギリスでも五月はイイ季節なんですね。
昨今では五月病なんて日本ではありますけど。
そんな憂鬱になったら外を歩いてみることも良いかなって思います。
どっか公園なり森なりを歩いてみると、光も風も涼やかで明るいまんま心誘ってくれるかなと。
そういう時期だからでしょうか?ここんとこ森も人をよく見かけます、やっぱり考えることは同じなんでしょうね、笑

昨日UP「Lettre de la memoire、暁光の斎 act.9―side K2」加筆ほぼ終わり、校正ちょっとします。
一昨日の第65話「序風act.3―side story」も校正を少しやったら続きを今日UP予定です。
取り急ぎ、
blogramランキング参加中!
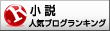
 にほんブログ村
にほんブログ村

正午の初夏、皐月―万葉集×William Wordsworth
正午の初夏は青空やわらかい、今日のこの辺です。
この時期は光が透けるよう明るくて綺麗、草も木も光って見える。
瓦屋根きらめくトコなんて、アノ五月の歌の通りだなって思います。笑
写真は近場の森にある花木です、で、この名前を未だに知りません。笑
卯の花と似た白い星型が可愛いんですけど、持っている山野草ハンドブックに載ってない。
ちょっとビジターセンターに行ってみたら良いのかもしれないけど、なんか行きそびれてます。
どなたかご存知の方いらしたら是非、教えてくれませんか?

宇の花も いまだ咲かねば霍公鳥 佐保の山辺に 来鳴き響もす 大伴家持
卯の花もまだ咲かず夏は来ない、
だから時鳥も春の女神が坐ます山に来て、時告げ鳴く聲を響かす。
夏を待ち切れないと、佐保姫のようなあなたと逢瀬する時を今だと言ってるけど?
昨日も卯の花と霍公鳥=ホトトギス・時鳥のこと書きましたけど。
この歌はすこし早い時期に鳴きだした時鳥に、恋逸る気持を解釈してみました。
時ならず 玉をぞ貫ける宇の花の 五月を待たば久しくあるべみ 詠み人知らず
まだ時は訪れない、
けれど皐月玉に縫う卯の花が咲く五月を待つと、待ち遠しくて。
この心の玉緒を貫くあなたのこと、早く逢いたくて待ち遠しくて、早月の初夏を待ち兼ねて。
この「玉」は薬玉のことで、卯の花を用いて五月に作るものを皐月玉ともいいます。
薬玉は今でも工芸品でありますが、綿を色糸でかがった美しいもので女の子の魔除けになる装飾品です。
ですが昔は老若男女すべてが用いたもので、綿の中に薬=薬草や木の実などを詰めて糸でかがり玉に作りました。
その表面を色糸や花を挿して綺麗に作りあげると贈物として、恋する相手へも歌を添え贈ることもあったようです。
たしか『源氏物語』にも光源氏が花散里へ薬玉を贈るシーンがあったかな?ちょっと曖昧な記憶ですみませんが、笑
ソンナ意味のある「玉」なので相聞歌に解釈してみました。
また、歌には5月=サツキを「五月」と書いていますが、解釈は三種に書き分けてみました。
古い字を用いる「皐月」を古来伝統の薬玉に、早く逢いたい想いに「早月」と掛けてあります。
5月を日本ではこんなふう三つの表記があることは、解釈を広げるのに楽しいです。
二つの歌とも共通するのが卯の花咲く季節への心弾みです。
五月の時を待ち兼ねて、卯の花や時鳥に早く時を告げてほしいと願う。
そんな五月という季節に籠めた人の想いが謳われているなって想います。

Then sing, ye Birds, sing, sing a joyous song!
And let the young Lambs bound
As to the tabor’s sound!
We in thought will join your throng,
Ye that pipe and ye that play,
Ye that through your hearts to-day
Feel the gladness of the May!
歌ってよね、鳥たちよ、歓びの歌を詠い、謳おう
子羊たちは踊り跳ねてよ、
小太鼓の音に合わせるよう楽しく。
私たちは愉しげな君たちに想いを馳せ、
笛を吹き遊ぶ君たちよ、
今日という日に君たちの心に想い馳せる、
皐月の輝ける歓び満ちる君たちに。
William Wordsworth「Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood」X
もうまんま五月の喜びを謳っちゃっています。
昨日掲載したIIIに続く一節ですが、イギリスでも五月はイイ季節なんですね。
昨今では五月病なんて日本ではありますけど。
そんな憂鬱になったら外を歩いてみることも良いかなって思います。
どっか公園なり森なりを歩いてみると、光も風も涼やかで明るいまんま心誘ってくれるかなと。
そういう時期だからでしょうか?ここんとこ森も人をよく見かけます、やっぱり考えることは同じなんでしょうね、笑

昨日UP「Lettre de la memoire、暁光の斎 act.9―side K2」加筆ほぼ終わり、校正ちょっとします。
一昨日の第65話「序風act.3―side story」も校正を少しやったら続きを今日UP予定です。
取り急ぎ、
blogramランキング参加中!







































