第二段落〈 6~9段落 〉 中間領域の存在
6 自然との結びつきという点では、日本の建築そのものが構造的に自然に向かって開かれている。建物の内部と外部が連続しているため、しばしば〈 その間 〉の境界があいまいとなり、内部とも外部ともつかない、いわば中間領域とでも言うべき場所が生まれてくる。軒下と呼ばれる部分などその代表的なものである。
Q12「その間」とはどことどこの間か。10字で記せ。
A12 建物の内部と外部の間
日本の建築 … 自然に向かって開かれた構造
∥
建物の内部と外部が連続
↓
中間領域の存在 (例)軒下
7 日本の伊勢神宮とアテネのアクロポリスの丘にあるパルテノンの神殿とは、外観上よく似た形状を見せている。もちろん、一方は木造で他方は石造という素材の違いがあるし、スケールの上でも大きな差があるが、柱を主要な支持材としてその上に横材を渡し、三角形の断面を見せる切妻型の屋根をかけるという構造は基本的に同一であり、したがって形状も似たようなものとなる。だがそこには、一つだけ〈 大きな違い 〉がある。パルテノン神殿の屋根は建物の平面を覆うところで終わっているが、伊勢神宮の場合、軒先がさらに大きく伸びている点である。その結果、ギリシア神殿には見られない軒下という空間が生じる。このことは、伊勢神宮だけに限らず、一般に日本建築の大きな特徴である。(中国の建物にも軒下部分があるが、日本の場合ほど深くはない。)
8 〈 このこと 〉は、日本には雨が多いという風土的特性に由来するものであろうが、そのようにして生まれてきたこの空間が内部か外部かというと、そのあたりが微妙なのである。それは家の中から見れば一応外部空間ということになるであろうが、そこが物置代わりに使われていたりするのを外から見れば、むしろ内部空間に付属するものとしてとらえられる。現に、庭師たちは、軒下のことを「軒内」と呼ぶ。外部空間で働く庭師たちにとっては、それは内部に属するものなのである。
9 このような〈 中間領域 〉として、ほかにもたとえばぬれ縁、渡り廊下のようなものがある。〈 壁 〉という強固な物理的遮蔽物によって内部と外部を明確に区分する西欧建築とは違って、日本の建築では、これらの中間領域を媒介として、内部は自然に外部へつながっているのである。
Q13 「大きな違い」とあるが、具体的にどうちがうのか。35字以内で記せ。
A13 伊勢神宮には、パルテノン神殿にはない軒下という空間が存在すること。
Q14 「このこと」とは何か。20字以内で記せ。
A14 日本建築には軒下という空間があること。
Q15 「壁」の役割を20字以内で記せ。
A15 建物の内部と外部を明確に区分する役割。
アテネのパルテノン神殿の屋根 … 建物の範囲まで
↑
↓
日本の伊勢神宮 … 大きく伸びている → 軒下
軒下 … 風土的特性(多雨)に由来
↓
内部にも外部にもなる空間
∥
中間領域
西欧建築 壁という強固な物理的遮蔽物によって
↑ 内部と外部を明確に区分する
↓
日本の建築 中間領域を媒介として、
内部は自然に外部へつながっている
∥
(具)軒下・ぬれ縁・渡り廊下
Q16 「中間領域」とはどのようなものか、60字以内で説明せよ。
A16 内部とも外部ともなりうる日本建築の一空間を指し、
内部と外部とが自然につながるように媒介する役割を果たしているもの。
西欧建築 内部 / 壁〈区分〉 / 外部(自然)
↑
↓
日本建築 内部 … 中間領域〈媒介〉 … 外部(自然)










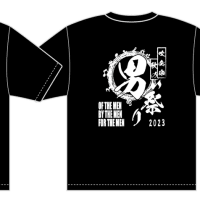






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます