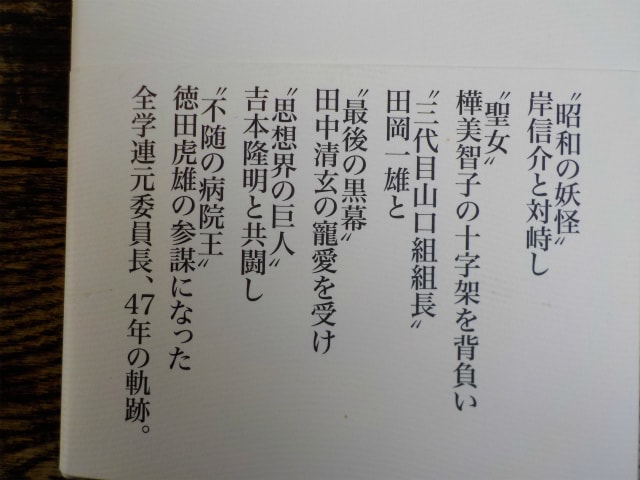夏場は小説どころかね、習慣的に買う週刊誌さえ目を通しかねることさえある。
でも、その代わりというか冬は飢えたように本を読んでいる。
最近はネットで注文すると、早いと翌々日には届くから便利といえば便利です。
ジャンルは特に問わず、読みたい本、面白そうな本を新聞、週刊誌などの書評で探したりする。
この「真剣師小池重明」は週刊誌の書評「徹夜で読みたい本」で見つけ読みたくなったもの。
モデルの「小池重明」は将棋愛好家には知られた名前で、真剣師はプロはプロでも賭けのプロの事。
そして、その実録を著したのが将棋好きで知られる作家「団鬼六」です。
「団鬼六」というと怪しげな官能ものやSМ小説で有名だけれど将棋愛好家としても知られている。
さて、破天荒な生涯を送った真剣師「小池重明」の実録はやはりこの人しか書く適任者はない。
次々とプロの棋士を破る話なんてすごいですね。高段者さえ打ち負かす妖刀使いです。
対戦者が一様に言うのは、アマのような序盤から、入り中盤からは対戦者に異様な感を持たせる。
そして、いつの間にか術中に陥るというか、序盤の優勢がいつの間にか敗勢に陥るというパターン。
プロとして最初から修行したら大成したかというと、物事はそう簡単なものではない。
生まれにも曰くが有るのだが、生き方が半端ではない破天荒な生き方。
酒と女で失敗ばかりし続ける生活は、破滅の方向へと向かうしかなかったのだ。
人妻と奔走したり、借金をし続けたり、人の信頼を裏切って逃げたりと転落一方の暮らし。
しかし、どんな境遇にいても将棋だけは怪しい強さを持ち続ける。
不始末から遁走し肉体労働で命をつなぎ、それでも何年も駒を握ってなくても勝つのですから。
かって、「東海の鬼」と呼ばれ、真剣師からプロになった有名な「花村元司」という棋士がいた。
しかし、「小池重明」は花村元司とはまた違う怪しげな強さがあったのだろう。
もう何十年も駒に触っていないけれど、スベルべも小学生のうちに将棋を覚えている。
今でも、日曜日のテレビ対局も時々見ています。やはり、多少将棋がわからないと面白くないかな。
とにかく、囲碁の藤沢秀行さんや、この小池重明など何故か無頼にもあこがれてしまう。
困ったことだけれども、自分など絶対になし得ないが、憧れる気持ちもどこかにあるのでしょう。