《社説①・01.18》:阪神大震災30年 教訓忘れず命守る社会に
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:《社説①・01.18》:阪神大震災30年 教訓忘れず命守る社会に
多くの命と当たり前の暮らしが一瞬で失われた。現代の防災体制の原点となった大地震の教訓を忘れてはならない。
阪神大震災の発生から30年が過ぎた。神戸市など兵庫県南部で国内初となる震度7を記録し、6434人が亡くなった。
阪神大震災で橋脚部分から横倒しになった阪神高速神戸線=神戸市東灘区深江本町で1995年1月17日、本社ヘリから撮影
耐震化が不十分だった建物が次々と倒壊し、住宅被害は約64万棟に達した。高速道路や鉄道の高架がなぎ倒され、街が炎に包まれる光景に、人々は言葉を失った。被害総額は約10兆円に上った。
巨大災害に対して、現代社会がいかに脆弱(ぜいじゃく)か。重い課題を突き付けられた。
発災当初、被害の深刻さを伝える情報が政府に届かなかった。所管の国土庁をはじめ官僚レベルでは的確な指示を出せず、自衛隊の災害派遣も遅れた。これらの反省を踏まえ、政府の防災体制は抜本的に見直された。
<picture><source srcset="https://cdn.mainichi.jp/vol1/2025/01/18/20250118k0000m040020000p/9.webp?1" type="image/webp" />

</picture>
自衛隊の災害派遣は、知事の要請がなくても出動できるよう基準を見直した。救援物資も、要請を待たずに届ける「プッシュ型」支援が実施されるようになった。
住宅や公共施設の耐震診断や基準の強化が進み、現在、耐震化された住宅は9割近い。
被災者の生活再建支援の転換点にもなった。自宅が全壊や半壊となった場合の公費支援を可能にする法整備がなされた。それまでは私有財産が損害を受けても被災者個人への現金給付はなかった。
ただ、いまだに解決されない課題は多い。
避難所の劣悪な環境は、昨年起きた能登半島地震でも改めて問題になった。被災者が学校の体育館などで雑魚寝を強いられ、プライバシーも守られない。政府は昨年末、環境改善を目指す指針をまとめたが、自治体任せでは実効性は担保できない。
避難生活のストレスなどが原因となる「災害関連死」も後を絶たない。仮設住宅での孤立化対策も十分とは言えない。何よりも優先されなければならないのは、被災者の命や健康を守る取り組みだ。
政府は2026年度中の防災庁の発足を目指す。自治体などと連携し、残された課題を解決へ導く組織にすることが求められる。
ただ、11年の東日本大震災や能登半島地震では、自治体が十分に機能しない事態に直面した。行政に頼るだけでない自助や共助の大切さが再確認された。
阪神大震災の際には、全国から延べ約140万人のボランティアが集まり、「ボランティア元年」と呼ばれた。防災NPO「レスキューストックヤード」常務理事の浦野愛さん(48)も学生ボランティアの一人だった。その後も各地の被災地支援に取り組む。
◆被災者視点を忘れない
当初は行政との調整に手間取り、被災者のニーズをすくい上げたり問題解決につなげたりするのに苦労した。徐々にノウハウが蓄積され、効果的な活動が可能になってきているという。
<picture><source srcset="https://cdn.mainichi.jp/vol1/2025/01/18/20250118k0000m040022000p/9.webp?1" type="image/webp" />

</picture>
能登半島地震では、石川県穴水町で、在宅の被災者も含めた幅広い支援を実施し、行政や関係機関との連携の枠組みを構築した。内閣府が実施する災害時の支援人材の研修などにも協力する。
30年間大切にしているのが、被災者一人一人の生の声を聞くことだ。表面は元気そうな人も深い悩みを持つ。高齢者や障害者のような弱い立場の人ほど「しんどい」思いを抱え込んでしまう。個々の事情はさまざまだ。
<picture><source srcset="https://cdn.mainichi.jp/vol1/2025/01/18/20250118k0000m040021000p/9.webp?1" type="image/webp" />

</picture>
ボランティアだけで、すべての被災者へきめ細かな支援を届けることは難しい。住民一人一人が日ごろから地域の活動に参加し、顔見知りを増やしておくことが重要になる。暮らしやすい地域づくりにもつながるはずだ。
阪神大震災で被災し、東日本大震災の復興計画を検討する会議のトップを務めた政治学者の五百旗頭真さんは生前、こう記した。
「この列島の住人は『連帯と分かち合い』をもって支え合うより外に、大災害を克服することはできないのだ。共助の手を差し伸べ合う以外にない」
いつどこで災害が起きてもおかしくない。都市部を中心に伝統的な共同体が失われる中、新たな時代に合わせた共助の形を模索し、命を守る社会を構築したい。
元稿:毎日新聞社 東京朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2025年01月18日 02:01:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。










:quality(40)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/WMC5OZQA75NWTI732RBZNU4IJA.jpg)



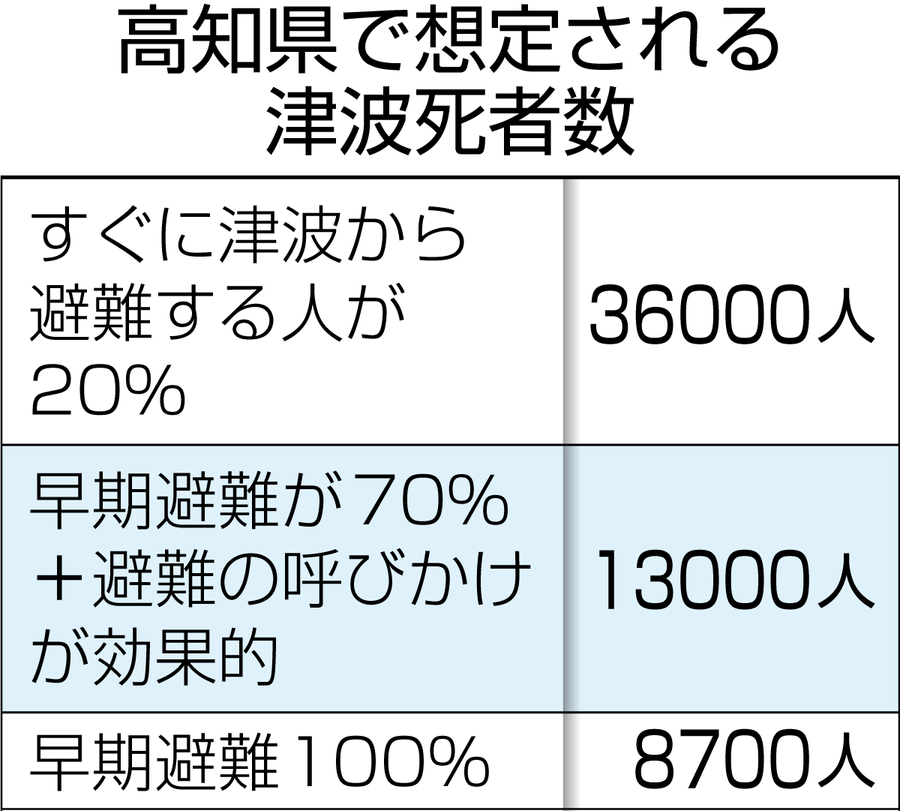

 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>






