【兵庫県】:斎藤知事のパワハラを断定、立花孝志氏のマスコミ叩きに便乗…①デマを指摘する「ファクトチェック団体」の欠陥
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【兵庫県】:斎藤知事のパワハラを断定、立花孝志氏のマスコミ叩きに便乗…①デマを指摘する「ファクトチェック団体」の欠陥
SNSなどで拡散されるデマや誤情報を検証する「ファクトチェック」を行っている団体がある。フリー記者の渡辺一樹さんは「日本ファクトチェックセンター(JFC)という団体が配信している記事には問題がある。専門家もJFCの記事に危機感をあらわにしており、専門機関としての適性が問われている」という――。
<button class="article-image-height-wrapper expandable article-image-height-wrapper-new" data-customhandled="true" data-t="{">![兵庫県議会の百条委員会で証人尋問に応じ、宣誓する斎藤元彦知事=2024年12月25日午後、神戸市内[代表撮影] 兵庫県議会の百条委員会で証人尋問に応じ、宣誓する斎藤元彦知事=2024年12月25日午後、神戸市内[代表撮影]](https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1wFo9t.img?w=768&h=511&m=6&x=141&y=123&s=1051&d=155) </button>
</button>
兵庫県議会の百条委員会で証人尋問に応じ、宣誓する斎藤元彦知事=2024年12月25日午後、神戸市内[代表撮影]© PRESIDENT Online
◆SNSが大きな影響を持った兵庫県知事選
民間調査会社ネットコミュニケーション研究所の調査によると、この選挙では斎藤氏を応援した立花孝志氏が「デマを流すマスメディアvs真実を伝えるネット」という対立構図を描き、その発信がYouTubeやXなどで拡散したことが、投票結果に大きな影響を与えたという。
同社の分析によると、立花氏関連チャンネルの動画は1500万回近くも再生され、インフルエンサーや切り抜きチャンネルなどが立花氏の発信を大きく取り上げていた。
ここで問題だったのは、そうして発信・拡散された内容の中に、自殺した元県民局長のプライバシーに関わる情報や、確たる証拠もなく斎藤知事のパワハラを全否定するといった「真偽不明」の情報が含まれていたことだ。
◆情報の拡散源となった有力プラットフォーム
ネットコミュニケーション研究所の調査によると、立花氏や支援者たちの発信する情報が拡散したのは、YouTubeやXなどのプラットフォームを通じてだ。そのプラットフォーム上で、どのユーザーにどんな情報を届けるかについては、「アルゴリズム」が大きな役割を果たす。アルゴリズムの中身は非公開で、その仕組みはプラットフォーム側が自在に変更できるものだ。
クイーンズランド工科大学のティモシー・グラハムとマーク・アンドレイェヴィッチの研究によると、イーロン・マスク氏のXでの投稿は、彼がトランプ大統領支持を表明したタイミングで起きたXのアルゴリズム変更により、表示回数が138%増加していた。マスク氏はXのオーナーで、アルゴリズムの中身を決定できる立場にある。
当然の帰結として、プラットフォーム側は、アルゴリズムを作り出した責任からは逃れられない運命にある。国際的にみると、YouTubeやXは誤情報や偽情報を垂れ流すプラットフォームだとして強く非難されている。
「ソーシャルメディアには誤情報が溢れている。特にXには多い」という指摘や、「イーロン・マスクとXは米国選挙の誤情報の震源地」といった分析は後を絶たない。米国のIT企業であるMozillaの大規模な調査においてもYouTubeは誤情報への対応が甘いと追及されており、米国のジャーナリズム教育機関であるポインターメディア研究所からは「特に英語でない言語の誤情報には対応が甘い」と批判されている
◆「日本ファクトチェックセンター」の不可解な記事
プラットフォーム上に真偽不明の情報がはびこる状況では、それが事実かを調査する「ファクトチェック」の取り組みが貴重だ。
ファクトチェックとは、一言でいうと「世間で事実であるかのように言われていることが、本当に事実かどうかを確かめること」だ。国際ファクトチェック団体のIFCNは、加盟団体に「中立性」「公平性」「情報源をできるかぎり明らかにする」「資金調達と組織の透明性」「ファクトチェック手法の公開と一貫性」「ミスがあった場合に誠実に訂正する」ことなどを求めている。
日本にもIFCN加盟団体が3つあり、なかでも最も頻繁に記事配信をしているのが「日本ファクトチェックセンター(JFC)」だ。運営委員長は京都大学教授で憲法学者の曽我部真裕氏が務めており、編集長は朝日新聞記者、バズフィード編集長やGoogle News Labティーチングフェローなどを歴任し、業界のオピニオンリーダーとしてテレビにも多数出演している古田大輔氏だ。
こうしたファクトチェック団体の存在は、大いに歓迎すべきだ。しかし、今回の兵庫県知事選について、JFCが出した記事は、国際的なファクトチェック記事や、IFCNの倫理基準と照らし合わせてみれば、疑問を感じざるを得ない点がいくつもあった。
◆「パワハラの定義にあてはまる行動」としているが…
それでは、JFCが配信した兵庫県知事選に関する記事の問題点を具体的に見ていこう。
まず、斎藤知事のパワハラ問題を扱ったこの記事では、次のような結論を出している。
兵庫県議会の不信任決議で失職した斎藤前知事はパワハラはしていないといった言説が拡散したが、根拠不明。県職員へのアンケートでは実際に目撃などで知っている人が140件、間接的に聞いて知っているという回答も含めると回答の4割を超える。本人も「厳しい叱責」「机を叩いた」ことなどを認めており、「必要な指導だと思っていた」と述べているが、パワハラの定義にあてはまる行動だ。
県職員のアンケートや百条委員会の証言などで告発された以上、「パワハラはしていない」と決めつける言説が根拠不明だというところまでは妥当だろう。しかし、斎藤氏の行為が「パワハラの定義にあてはまる行動」だったという点については疑問が残る。
◆パワハラ問題については、まだ結論が出ていない
JFCの記事は、パワハラの定義について厚生労働省の「パワーハラスメントの定義について」という資料をもとに次のように論じている。
「精神的な攻撃」として「大勢の前で叱責する」「ものを机に叩きつけるなど威圧的な態度をとる」などをあげている。
しかし、資料の該当箇所を読むと、資料には「これらの行為が全てパワーハラスメントに当たることを示すものではない」と注釈がついている。厚労省にも確認取材をしたがやはり「机を叩けば、それだけで自動的にパワハラになるわけではない」という。
また、斎藤氏が自ら認めた「机を叩いた」行為とは、本人による百条委員会での再現によると、机を平手で二回ポンポンと叩いた程度だ。これは、斎藤氏の言い分に過ぎないが、「本人が認めた範囲」で即パワハラ判定ができるかどうかというと、議論の余地があるだろう。
もちろん、きちんとした議論の結果、やはり「パワハラだった」という結論が出る可能性は十分にある。しかし、地元紙の神戸新聞が2024年11月15日に配信した記事では「百条委や第三者委の調査が続いており、結論は出ていない」としている。また、12月25日に行われた県議会の百条委員会においても、斎藤知事のパワハラ問題については最終的な結論は出ておらず、来年2月の定例県議会で証言などを取りまとめた報告を行うとしている。
「文書問題に関する第三者調査委員会」についても、報告書の提出目標を来年3月上旬としておりまだ結論は出ていない状況にある。
◆政治家の発言に対して“裏とり”ができていない
また、こちらの記事では「兵庫県知事選挙に立候補している稲村和美氏について、『当選すると外国人の地方参政権が成立する』『外国人参政権推進派』という言説が拡散したが、誤り。稲村氏は外国人参政権を公約にしておらず、この言説を否定している」と結論付けている。
しかし、そもそも記事が示した投稿の表現は「(地方参政権が成立する)かもしれない」となっている。もともと「かもしれない」だったのを、断定的な「成立」という言葉にすりかえて評価するのは、果たして適切なのだろうか。
また、稲村氏の発言について、まったく裏とりをせずに信用している点も気になる。筆者は政治団体「みどりの未来」が、稲村氏が共同代表だった時期に、外国人参政権を推進する政策を打ち出していたと思われる資料を、「緑の党」と同じドメイン名(greens.gr.jp)の下で公開されているサイトで発見した。筆者は12月4日、電話や公式サイトの問い合わせフォーム経由で稲村氏の事務所に事実確認の質問を送ったが、2週間経っても返信はない。
こうしたJFCの記事は、「証拠を多角的に検証する」という、IFCNの倫理規定が求めている基準を満たしていないのではないか。
◆ファクトチェックの専門家も記事を疑問視
これら2本の記事について、専門家はどう捉えるだろうか。国内ファクトチェック団体の草分け「FIJ」の設立メンバーで、『ファクトチェックとは何か』(岩波書店)の共著者でもある楊井人文弁護士は、検証手法に重大な問題があると指摘する。
「斎藤知事の行為を『パワハラの定義に当てはまる行為だ』と断言した記事には、大きな問題がある。どんな行為があったかどうかの事実認定や、それが定義に当てはまるかどうかは、専門家でも意見が分かれることのある難しい問題だ。それなのにJFCは独自判断で、斎藤知事の行為を事実認定して、それが『パワハラの定義に当てはまる行為だ』と断言した。専門家に取材をした様子もない。いつからJFCはパワハラ認定機関になったのか」
もう一つの記事についても、楊井氏は次のように話す。
「稲村さんが『外国人参政権推進派』ではないとしたファクトチェックにも問題がある。『公約に書いていない=推進する可能性がない』と結論づけるのは短絡的すぎる。私自身もXで指摘したが、少し調べれば見つかる情報に言及はせず、それを本人に問い合わせた形跡もない。確認不足だろう」
楊井氏は「ファクトチェックはそもそも『報道』の一手法だ。国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)も、これは『ジャーナリズムの実践だ』と明確に示している」と指摘。「そうであれば、最低限やるべき取材調査は尽くして、スキのない記事、読者にとって納得感のある記事を書かなければいけない。JFCがこのレベルの記事を作り続ければ、『ファクトチェック』という手法そのものの信頼まで損なわれかねない」と危機感をあらわにした。
◆「SNS対伝統的メディア」という図式を煽っている
JFCが配信した記事で問題があるのはファクトチェック記事だけではない。
筆者がさらに根深い問題があると考えているのは、兵庫県知事選が終わった直後、JFCは「SNSや動画」の影響力が新聞やテレビを上回ったというテーマの記事(前編・後編)である。
この記事は、NHKの出口調査で、投票する際に最も参考にした情報として、「SNSや動画サイト」が30%となり、テレビ(24%)や新聞(24%)を上回っていたことを受けて書かれた記事だ。出口調査の結果を見る限り、テレビや新聞の選挙報道が、有権者の期待に十分応えられる内容でなかったということは言えるだろう。
だが、それを「解説する」はずのJFC記事を読むと、そこには筆者の意見や主観が強く反映されており、実質的にはオピニオン記事と言うべき内容だった。
具体的に記事を見ていこう。前編の見出しは「斎藤氏再選の裏にSNSや動画 投票の参考情報で新聞・テレビ上回る」となっており、この解説は最初から「SNS 対 新聞テレビ」という構図で書かれていることがわかる。続けて見ていくと、「今回の選挙では『ソーシャルメディア』か『新聞やテレビ=伝統的メディア』かという分断が発生していました。」という記述がある。自然にできた分断のように書いているが、これは立花氏の主張そのものだ。
記事後編でも、冒頭に生成AIで作ったという「テレビと新聞が燃える画像」と「マスメディアが情報の権威だった時代の終焉」という文字が目に付く。これを見れば、多くの人が「マスメディアの終わり」というような印象を持つのではないか。イメージ画像による印象操作をするのは、ファクトチェック団体の取るべき手法とは言い難い。
燃えている新聞とテレビの画像には、“マスメディアが「情報の権威」だった時代の終焉”という見出しが付いている。生成AIにこのような画像を作らせた意図はどこにあるのだろうか。
◆プラットフォームの問題点をほとんど指摘していない
また、冒頭でも指摘したように、FacebookやXなどの有力プラットフォームはフェイスニュースの拡散源となっているが、JFCはこれらの問題点にほとんど触れていない。
JFCは2024年11月までに「ファクトチェック記事」以外に解説記事22本、ファクトチェック講座記事20本、メディアリテラシー講座記事5本を出していた。すべてをチェックしたが、そのうちプラットフォームの責任論が語られていたのは1本だけで、その記事はPoynterの記事を和訳したものだった。
たとえば、さきほどの解説記事では、YouTubeなどのプラットフォームについて「自分では選べない情報洪水の中で、アルゴリズムが適切に情報を取捨選択してくれる」などと利便性を強調する一方で、運営者の責任を語っていない。
解説記事の前編では「情報洪水の中でアルゴリズムが情報を取捨選択(便利)」「プラットフォームが便利だからこそ人・情報が集まる」と、1つの図で「便利」という言葉が2回も使われている。
YouTubeやTikTokなどの動画配信サイトが、アルゴリズムによって情報を取捨選択しユーザーに届けていることを説明した図。「便利」というワードが二度も登場する。
◆収入源のほとんどがプラットフォームからの助成金
JFCがこうした主張記事を出すことには、大きな問題があると筆者は考えている。なぜなら、JFCが公開している「JFCへの支援と会計」によると、運営費の99%はGoogleなどのプラットフォーム企業が出しているからだ。内訳は、Googleから7367万円、LINEヤフーから500万円、Metaから400万円となっており、Googleからの助成金は8割以上を占めている。
古田編集長自身も2020年から2022年までGoogle News Labのティーチングフェローを務めていた。そして、YouTubeはGoogleの動画プラットフォームである。
つまり、JFCや古田氏は、この問題について「第三者」というより、当事者に極めて近い立場なのである。資金源についての情報はJFCのサイト上を探せば見つかるが、記事中にはそうした注意書きがまったくない。解説記事を読んだ人が、いちいちJFCの収支報告を調べるとは考えにくい。
JFCは自らのガイドラインでも「非党派性」や「透明性」を打ち出している。JFCの監査委員長である東京大学大学院教授の宍戸常寿氏に対するインタビュー記事によると、JFCは2022年にGoogleから150万ドル(2億1700万円)の運営資金を得て、ネット関連事業者でつくる一般社団法人・日本セーファーインターネット協会(SIA)の一部門として立ち上げられた組織だ。
しかし、後述するがJFCに問い合わせたところ、編集部をチェックするという運営委員会は完全非公開であり、2024年8月に公開されたさきほどのインタビュー記事によると、監査委員会は発足後からその時点まで、過去一度も開催されたことがなかったという。このような状況では、「非党派性」や「透明性」という言葉も疑わざるを得ない。
◆Googleとの関係性は本当に中立なのか
JFCの「解説」記事では、マスメディアを批判する一方で、誤情報拡散に対するYouTubeやGoogleの責任は一切語られていない。Googleとマスメディアの間には競合関係があり、OECDの報告によるとGoogleなどのプラットフォーム側が圧倒的に優位な立ち位置にいる。
つまり、JFCはGoogleから多額の資金をもらって、Googleが利害関係者である誤情報の問題について、中立を装って、YouTubeやSNSの影響力拡大やマスメディアの凋落を強調するオピニオン記事を書いているように見える。
これは、ジャーナリズムの倫理にも反するのではないか?
たとえば、海外の有名ファクトチェックメディア「Politifact」はMeta社から資金提供を受けているが、Facebook投稿の検証過程でMeta社のシステムを使っただけでも、毎回次のような断り書きを入れている。
このFacebook投稿は、ニュースフィード上の偽ニュースや誤情報に対抗するMetaの取り組みの一環として要確認とされた。(Facebook、Instagram、Threadを所有するMeta社とPolitifactの関係性についてはこちらをご覧ください)
先のJFCの記事で筆者が論評している対象は、テレビ局といい、インフルエンサーといい、Googleと利害関係がある人たちばかりだ。そして、GoogleとJFCとの関係性を念頭に置いて記事を読んでいくと、メディアを批判する一方で、YouTubeの番組やインフルエンサーには「甘い」姿勢が見えてくる。
◆デマを拡散する人物を説明なしで紹介
たとえば、YouTubeなどのプラットフォーム上で活躍するインフルエンサーについては、解説記事の後編に次のような一文がある。
2024年のアメリカ大統領選は「ポッドキャスト選挙」とも呼ばれました。コメディアンの「The Joe Rogan Experience」などの有力ポッドキャストが大きな影響を与えたからです。
ここで紹介されているポッドキャストの配信者であるジョー・ローガン氏は、YouTubeのチャンネルに1870万人の登録者がいるほどの人気コメディアンだが、同時にCNNやBBC、NewYork Times、AP通信、Newsweek、AFP通信など、数多くのメディアからファクトチェックの対象とされている要注意人物でもある。
JFCの記事は、ローガン氏を紹介する際、こうした注意点に一切触れていない。数多くのメディアから発言の信憑性を疑われている人物の番組を「有力ポッドキャスト」とだけ説明するのは、ファクトチェック団体として不適正だと言わざるを得ない。
こうした「解説」記事やファクトチェック記事は、IFCNの倫理憲章(和訳)や、JFCのガイドラインや指針と照らしても問題があると思われる。
IFCN倫理憲章の「非党派性と公正性」には、「私たちは、ファクトチェックの対象とする問題について、特定の政策的立場に立ったり擁護したりすることはしません」とある。また、「資金源と組織の透明性」の項目では、「他の組織から資金を受け入れても、資金拠出者がファクトチェックの調査で達した結論に対して全く影響を与えないことを確約します」とうたっている。
Googleからの資金提供を前提にすると、これらの記事内容には、「非党派性と公正性」「資金源と組織の透明性」に課題があると言わざる得ないだろう。
◆国際団体もGoogleから資金提供を受けているが…
JFCのガイドラインには「当センターにおいてファクトチェック記事の作成に従事する者は、正確性と透明性の問題を除き、当センターがファクトチェックを行う可能性のある政策課題について、合理的な一般市民が当センターの活動を偏ったものと見なす恐れがあるかたちで、自らの見解を提言又は公表してはならない。」と書いてある(14条)。
プラットフォーム規制が、日本でも話し合われている「政策課題」であることは間違いない。そして、もちろんGoogleやYouTube、LINEヤフー、Metaはその最大の対象だ。繰り返しになるがJFCの資金源は99%がそのプラットフォーム3社からである。
実は、ファクトチェックの国際団体IFCN自身も、Googleから1300万ドル以上の資金提供を受けている。しかし、メンバーの多くはGoogleなどの巨大プラットフォームを公然と「フレネミー(フレンドであり、同時にエネミーでもある)」と呼んでいる。資金提供を受けていても、その下請けや代弁者となり下がらないために、意識して距離を保とうとしているのだ。
彼らはYouTubeの批判もしている。2022年にはYouTubeのCEO(当時)宛てに公開質問状を出している。80以上のファクトチェック団体が署名したこの質問状の冒頭には、次のような強烈な言葉が綴られている。
「YouTubeは、悪意のある人たちがそのプラットフォームを武器として使い、他者を操り、搾取し、組織化し、収益を上げることを許容してしまっている」
◆JFCから回答が来たが…
Googleからの資金が、編集方針に影響を与えているのではないか。その疑念について、筆者は12月4日にJFCに質問を送った。JFCからは12月19日に「当センターはファクトチェックガイドライン第2条に基づき、非党派的かつ公平公正なファクトチェックを実施しており、プラットフォームとの関係もこうした原則に基づいております」という返信があった。
筆者が送った質問内容とJFCからの回答全文は、別途掲載するが、筆者がガイドラインの条文まで挙げて具体的な質問をしているのにもかかわらず、JFC事務局は「ご参考までに下記もご覧下さい」として、そのガイドラインのリンクを送ってきた。
また、筆者は「アルゴリズムについて『便利』という言葉を2回も使った図」を例に挙げ、こうした説明をする意図を質問した。事務局は、その質問には直接回答せず、「参考までに」としたうえで、このような返答があった。
SNS、アルゴリズム、エコーチェンバーなどの問題につきましては、ご連絡いただいた記事の他にも下記の講座理論編でも取り上げさせていただき、多くの方にご視聴いただいております。
■フェイクニュースとアルゴリズム YouTubeやTikTokが便利で危険な理由【JFCファクトチェック講座 理論編3】
これには驚かされた。この記事は質問状で「チェックした」と伝えたものに含まれているうえ、そこには筆者が質問したのと実質的に同じ図が使われているからだ。「なぜこんな図を使ったのか」という質問に対して、「図そのもの」の確認を求められるとは思わなかった。
◆「透明性」は担保されているのか
また、返信には「なお、運営委員会は、委員間で自由闊達な意見交換を行い、適切な意思決定を図る場としております。その性質上、詳細な日時や議事録等は非公開とさせていただいております」とも書かれていたが、この点にも違和感を覚えた。
開催日時すらも非公開なのだとすれば、運営委員会が実際に開催されているのかどうかも、外部からはわからない。これでは「完全な秘密会議」と言わざるをえない。JFCは「ファクトチェック」という、本来なら極めて高い倫理性と真摯(しんし)な姿勢が求められる活動を行うはずの組織だが、これでいいのだろうか。自ら掲げる「透明性」の大義はどこへ行ったのか。
こうしたJFCの姿勢をIFCNの姿勢と比べながら、なぜファクトチェック団体が、プラットフォームと適切な距離を保つべきなのかについて、さらに論じてみよう。
IFCNは「YouTubeへの公開質問状から2年経つが状況は良くなっていない」という趣旨の続報記事も出している。そのなかでも、下記の指摘は重要だ。
巨大テック企業のアルゴリズムは、ファクトチェッカーによる検証記事よりも、虚偽情報の作り手によるコンテンツの方を優先して表示しがちだ。
ファクトチェッカーには巨大テックカンパニーからの資金が必要だ。しかし、そもそも資金がいる理由の一つは、テックカンパニーが問題をどんどん深刻にしてしまっているからだ。
実際、Googleを運営するAlphabet社が公表した2023年度第4四半期の会計資料によると、Googleは3000億ドル以上を売り上げ、その純利益は738億ドルに及んでいる。それに比べれば、IFCNへの寄付(1300万ドル)は微々たるものだ。
---------- 渡辺 一樹(わたなべ・かずき) 記者/編集者 1976年生まれ。奈良県出身。早稲田大学法学部卒。信濃毎日新聞記者、月刊誌などを経てネットメディアへ。弁護士ドットコムニュース副編集長、BuzzFeed記者、ハフポストニュース統括マネジャーなどを経てフリーに。テクノロジーや社会問題全般について幅広く執筆している。 ----------
元稿:プレジデント社 主要出版物 PRESIDENT Online 社会 【話題・地方自治体・兵庫県・県知事選挙におけるSNSなどで拡散されるデマや誤情報が拡散された事象】 2024年12月30日 08:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。












 </picture>
</picture> </picture>
</picture>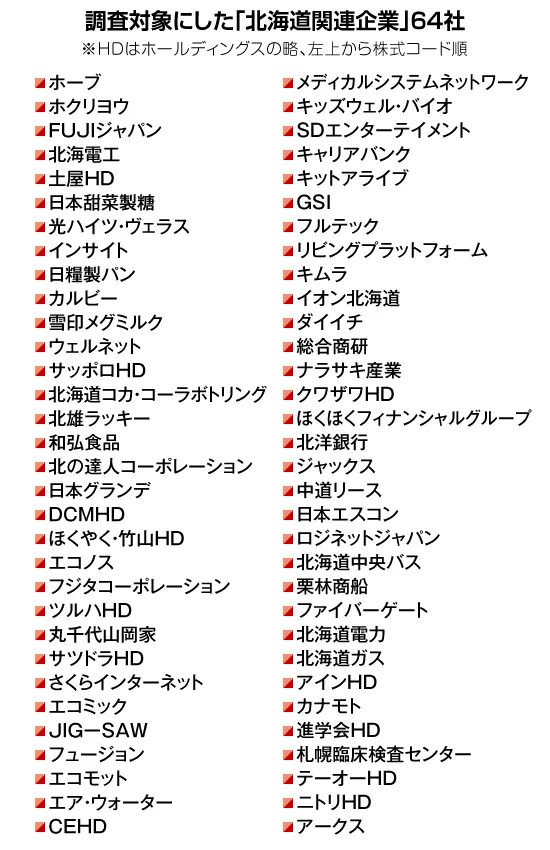


 </button>
</button>![兵庫県議会の百条委員会で証人尋問に応じ、宣誓する斎藤元彦知事=2024年12月25日午後、神戸市内[代表撮影] 兵庫県議会の百条委員会で証人尋問に応じ、宣誓する斎藤元彦知事=2024年12月25日午後、神戸市内[代表撮影]](https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1wFo9t.img?w=768&h=511&m=6&x=141&y=123&s=1051&d=155) </button>
</button> </picture>
</picture>
 </button>
</button>




