《社説①・01.06》:戦後80年 多様化する家族 生き方尊重し合う社会に
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:《社説①・01.06》:戦後80年 多様化する家族 生き方尊重し合う社会に
家族のかたちは多様化している。個人の自由な選択が尊重される社会の実現が求められる。
結婚に関する制度が壁となり、家族として法的に認められず、不利益を被っている人たちがいる。
婚姻前の姓のまま夫婦になりたいカップルが典型例だ。同じ姓を名乗ることが義務づけられているのは日本だけとされる。
「夫婦別姓も選べる社会へ!」と書いた幕を持ち、東京地裁に向かう原告たち=東京都千代田区で2024年6月27日午後1時54分、菅野蘭撮影
<picture><source srcset="https://cdn.mainichi.jp/vol1/2025/01/06/20250106ddm005070104000p/9.webp?1" type="image/webp" />

</picture>
<picture><source srcset="https://cdn.mainichi.jp/vol1/2025/01/06/20250106ddm005070105000p/9.webp?1" type="image/webp" />

</picture>


同性婚を認めない現行制度の違憲性を問う訴訟の控訴審判決で東京高裁に入る原告たち=東京都千代田区で2024年10月30日午前9時29分、宮間俊樹撮影
長野県の内山由香里さん(57)と小池幸夫さん(67)は、同姓か別姓かを選べる選択的夫婦別姓制度の実現を求め、活動している。
2人は事実婚の状態にある。内山さんは、かつて法律上の結婚をし、改姓を強いられた時のことを「不快感や喪失感を突き付けられていた」と振り返る。
職場では旧姓を通称として使えたが、公的な書類などでは「小池」姓を求められた。慣れ親しんできた名字が、自分の名前ではなくなったと痛感した。
◆変わらない意識と制度
各種世論調査では選択的夫婦別姓制度に賛成する声が多数を占める。だが、政治の動きは鈍い。法制審議会が29年前に導入を答申したが、たなざらしにされている。
男女が一つの「家」をつくって同一の姓を名乗り、子を産み育てる。そんな家族観を日本の伝統と見なす意識が根強く残るためだ。
人々が当たり前だと考えてきた家族像について、家族社会学が専門の落合恵美子・京都産業大教授は「近代化の中、特に戦後に形づくられたものだ」と指摘する。
1898年に施行された明治民法で、戸主の男性が家族を統率する家制度が採用された。
戦後、法の下の平等や個人の尊重をうたう現憲法が制定され、民法も改正された。家制度は廃止され、男女の権利は平等となったが、夫婦同姓制度は残った。
落合教授によると、近代より前の日本は女性の就労率が高かったが、工業化が進展した近代社会になると、夫が外で稼ぎ、妻が家事や育児を担うという性別分業が生まれたという。
高度成長期には、都市部で製造業やサービス業に従事する人が増加し、地方からの人口移動が加速した。核家族化が進み、男女の役割分担が定着した。
しかし、その後に家族のありようは大きく変化している。
女性たちの意識が変わり、社会進出が拡大した。背景には、地位向上を目指す世界的な運動の広まりもあった。
バブル崩壊後は賃金が伸び悩み、家計を支えるために働かざるを得ない女性も増えた。
1980年代までは専業主婦世帯が多かったが、2023年には夫婦共働き世帯がその約3倍となった。
ただ、働く女性の半数以上は非正規雇用だ。家庭の切り盛りに追われ、パートタイム労働を余儀なくされる人が多い。給与が男性より低く抑えられる傾向もある。
落合教授は、子育てや介護などの「ケア」は本来、社会も関与すべきことなのに、女性に押しつけられてきたと解説する。その重要性についての認識が社会で共有されず、「ひずみのしわ寄せを女性が被ってきた」と話す。
◆個人の選択を支えたい
さまざまな制度も時代の変化に追いついていない。専業主婦がいる家庭をモデルに整えられた年金や税控除などの仕組みは、実態にそぐわなくなっている。
「夫婦と子ども」という一般的とされてきた家族の枠組みに当てはまらない人も増えている。
20年の世帯構成では「単身」が38%に上り、「夫婦と子ども」を上回っている。50年には44%を占めると予測される。
急速な高齢化で、1人暮らしのお年寄りが多くなっている。生活苦や将来への不安を抱えたり、結婚を望まなかったりして、非婚を選ぶ人も少なくない。
孤立するリスクがあり、血縁に頼らない人間関係の構築や、居場所づくりが課題となっている。
LGBTQなど性的少数者も、新しい家族のかたちを求めて声を上げている。
性的指向や性自認は自らの意思で変えられるものではない。人権に関わる問題である。
同性カップルの訴えに対し、同性婚を認めない現行制度を「違憲」「違憲状態」とする司法判断が相次いでいる。
家族のあり方は時代や社会の動きとともに変化する。さまざまな生き方が広く認められ、支えられる仕組みの構築が欠かせない。
元稿:毎日新聞社 東京朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2025年01月06日 02:07:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。












 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture> </picture>
</picture>


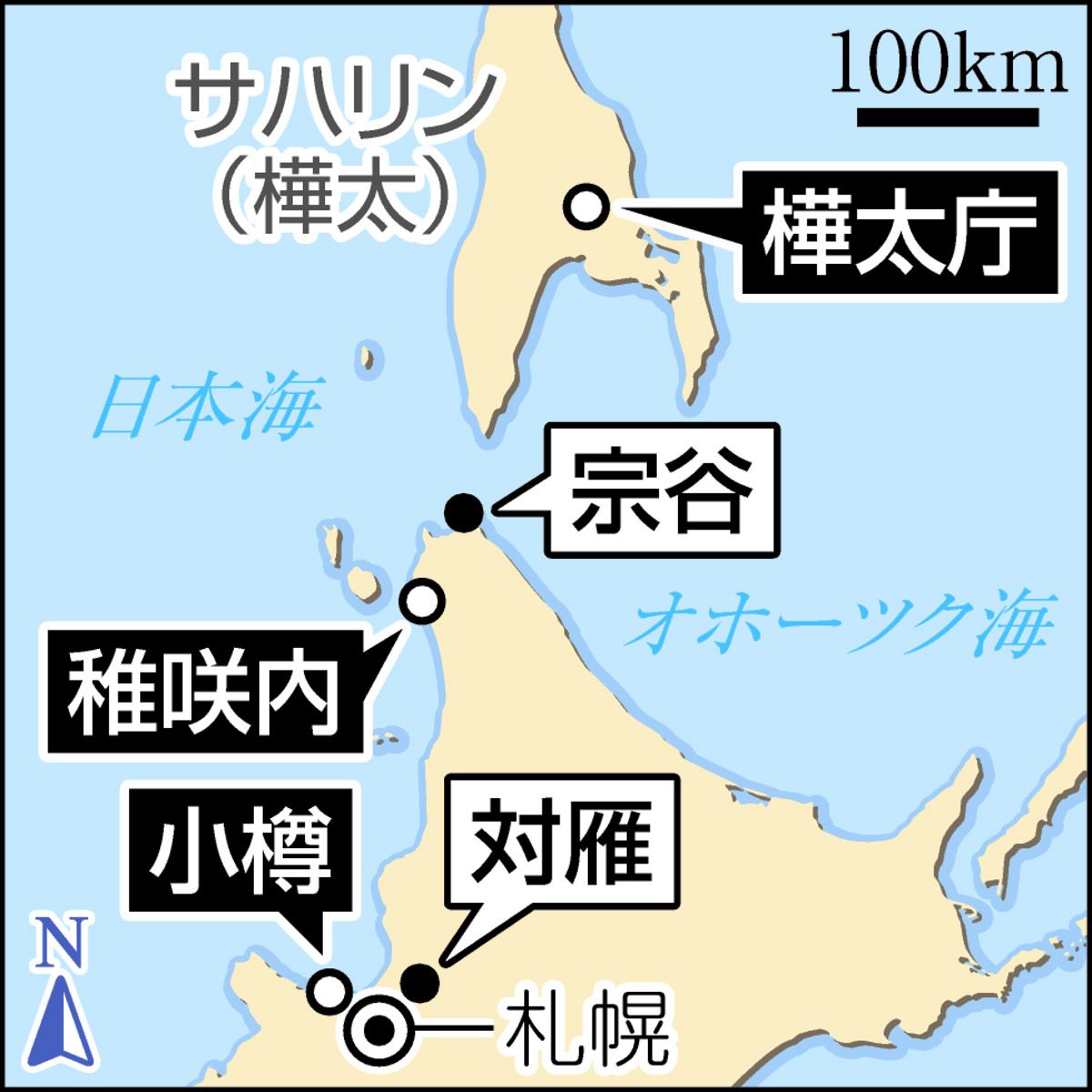


:quality(70)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/EMRVGFGWDFJIJKO3XGA26XZLDM.jpg)
 </picture>
</picture>




