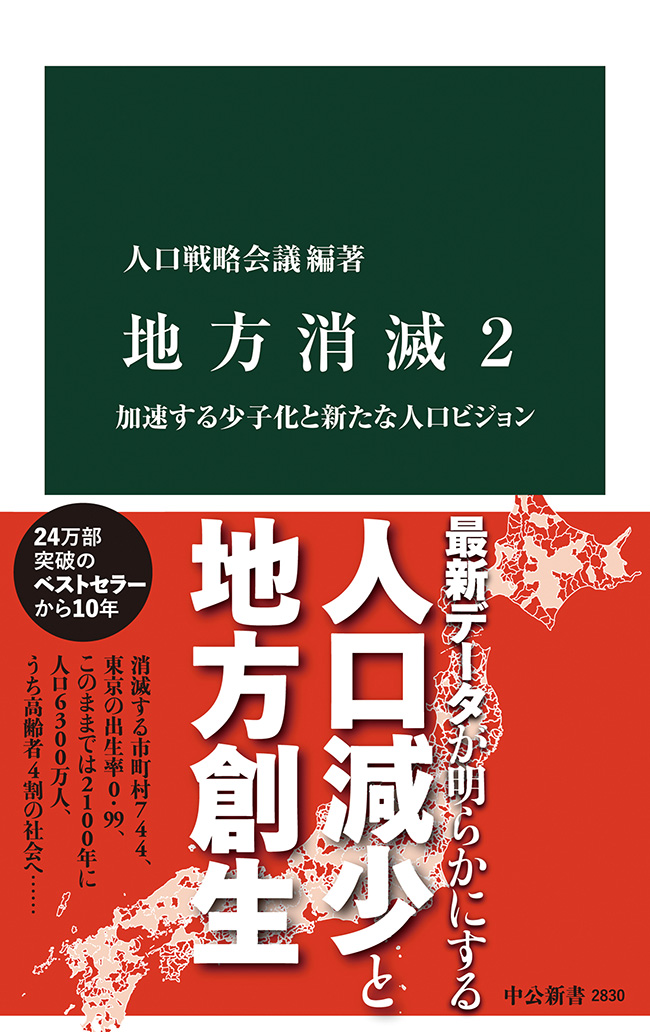【社説①・01.12】:実家じまい 親子で事前に話し合いたい
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①・01.12】:実家じまい 親子で事前に話し合いたい
離れて住む両親が亡くなった後、実家をどうすべきか、途方に暮れる人は少なくない。親子で家の処分や活用の方法を、あらかじめ話し合っておくようにしたい。
親が死去したり、施設に入所したりした後、家族が残った家を整理する作業は「実家じまい」と呼ばれる。最大の問題は、家屋と土地の取り扱いではないか。
東京の不動産会社が実家を売却した人を対象に、処分にかかった期間を調査したところ、6か月未満が7割を占めた。その際の苦労や後悔を尋ねると、「思うような価格で売れなかった」という回答が4割に上ったという。
実家をどうするのか考えていない状況で親が亡くなり、相続税の納付期限を念頭に、急いで売却する人が多いのだろう。相続の際、権利関係を巡って親族間でトラブルになることもある。
実家から離れて暮らす人は、実家じまいにかかる手間や費用の負担が特に大きい。全国の空き家は900万戸に上り、30年前から倍増した。このうち、385万戸は、用途が決まらないまま放置されている可能性があるとされる。
家は構造や築年数のほか、立地が都市か地方かによって資産価値に幅がある。賃貸に出したり、セカンドハウスとして活用したりする選択肢もあろう。事前に親の意向も確認し、きょうだい間で共有しておくことが重要だ。
とはいえ、不動産の知識のない人が家や土地の処分や活用の方法を検討するのは難しい。多くの自治体が、司法書士や税理士らによる無料相談会を開いている。まずは専門家に相談し、どのような方法があるかを知っておきたい。
実家じまいの際には、家具や衣類、食器のほか、車や農機具などをどうするかも悩みのタネだ。実際に片付ける段になると、どこから手を付けたらいいか分からないという人もいるに違いない。
処分の方法を決める際には、親の意見に耳を傾けることも大事だ。実家にある品々は、親の生きた証しであり、家族の思い出も詰まっている。「本当に必要なの?」などと詰問すれば、親の心をむやみに傷つけかねない。
話し合いの結果、手元に置いて残すものと、廃棄するものを書き留め、少しずつ段ボールに仕分けしておくことも一案である。
年末年始に帰省した人もいるだろう。自分が生まれ育ち、今も親が暮らす実家の処分となると、決断も容易ではないはずだ。新しい年に時間をかけて考えたい。
元稿:読売新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2025年01月12日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。