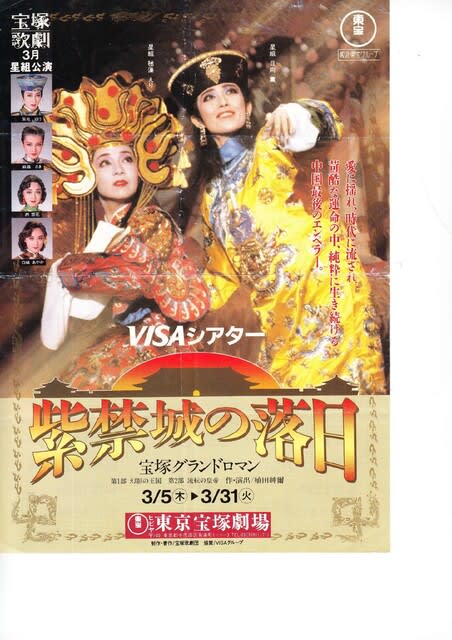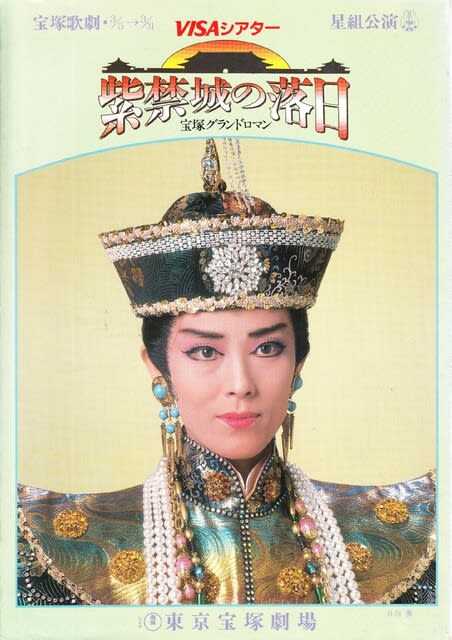2023年1月7日週刊SPA、
https://nikkan-spa.jp/1881332
「世界で最も餓死者が出る国
―― 鈴木さんは新著『世界で最初に飢えるのは日本』(講談社+α新書)で、日本が飢餓に陥るリスクに警鐘を鳴らしています。
鈴木宣弘氏(以下、鈴木) 先日、朝日新聞(2022年8月20日)が「核戦争後の『核の冬』食料不足で世界の50億人犠牲」という衝撃的な記事を掲載しました。米国ラトガース大学が5段階で核戦争の被害を試算し、核攻撃による死者よりも「核の冬」による餓死者のほうが多くなるという研究成果を発表したという内容です。
この研究によれば、5段階のうち最も小規模な想定でも、局地的な核戦争が勃発した場合、核攻撃による死者は約2700万人ですが、「核の冬」による食糧生産の減少と物流停止による2年後の餓死者は2億5500万人、そのうち日本の餓死者は7200万人(全体の3割)になると推定しています。米ロ全面核戦争が勃発した場合は死者3.6億人、餓死者53億人、そのうち日本の餓死者は1.25億人で全滅です。なお、「核の冬」とは核爆発によって大気中に巻き上がる煤や煙が太陽光を遮り、地球規模で気温が低下する現象のことです。
つまり、世界的な飢餓が起きた場合、世界の餓死者は日本に集中するということです。日本は世界で最も食料安全保障が脆弱な国であり、それゆえ最も飢餓のリスクが高い国なのです。
問題は、核戦争が起きなくても食料生産の減少や物流停止が起きれば、日本は飢餓に陥るということです。そして、食料生産の減少と物流停止のリスクは現実に高まっているのです。
いま、世界の食料システムは「クワトロショック」(四つの危機)に直面しています。一つめは異常気象です。毎年のように記録的な異常気象や自然災害が起こり、食料が作りにくくなっています。
二つめはコロナです。コロナの影響で国際的な物流が一時滞り、食料が運びにくくなっています。
三つめは中国の爆買いです。近年、中国は国内需要に対応するため大量の食料を爆買いしており、食料が買いにくくなっています。
四つめはウクライナ戦争です。ウクライナとロシアは世界の小麦3割を輸出している国々ですが、戦争の影響でウクライナ産小麦の生産量・輸出量が激減しています。一方、ロシアは食料を武器として扱い、日本をはじめとする非友好国への輸出を制限しています。戦争で食料が作れず、運べず、買えなくなっている。
また、戦争の影響で石油価格が高騰したため、バイオ燃料の需要が増えて穀物価格も高騰しています。2022年3月にはシカゴの小麦先物相場が2008年の世界食料危機の時の最高値を超えたという出来事がありました。
さらに、こうした事態をうけて、20数か国が食料などの輸出を制限するようになっています。世界有数の食料輸出国であるインドはすでに小麦、砂糖、コメの輸出制限に踏み切っています。
一連の危機から世界では食料争奪戦が始まり、飢餓のリスクが高まっています。WFP(国連世界食糧計画)やFAO(国連食糧農業機関)は2022年6月に、コロナやウクライナ戦争の影響で世界20か国以上で深刻な飢餓が発生すると警告しています。すでに世界的な食料危機は始まっており、「お金があっても食べ物が買えない」という時代がすぐそこまで来ているのです。
―― 世界の食料システムが機能しなくなりつつある。
鈴木 現在の食料システムは少数の食料生産国と多数の食料輸入国から成り立っており、もともと脆弱な仕組みなのです。その背景にはアメリカの食糧戦略があります。アメリカは「食料は武器より安い武器である」として他国がアメリカの食料に依存する仕組みを作ってきたのです。
アメリカは自国の農業を手厚く保護しており、穀物3品目(大豆・トウモロコシ・小麦)について生産額と輸出額の差額を全額補填するために多い年には1兆円規模の予算を支出しています。その一方で、アメリカはIMFや世界銀行を使いながら貿易相手国に輸出規制の緩和を要求してきました。その結果、アメリカは「補助金漬け」の作物を輸出して相手国の農業を弱体化してきたのです。
たとえば、ハイチは1995年にIMFから融資をうける条件としてコメの関税を3%まで引き下げさせられました。その結果、ハイチのコメ生産が減少してしまい、2008年の世界食料危機ではコメ不足から暴動が起きて死者が出ました。
―― 世界の食料生産も限界に近づいているといいます。
鈴木 現代では化学肥料と水を大量に使用する大規模農業が主流になっています。いうまでもなく農業には大量の水が必要です。しかし化学肥料を大量に投入した結果、土壌が劣化して作物が育ちにくくなり、これまで以上に大量の水が必要になっているのです。
つまり、化学肥料農業は土壌を劣化させ、水不足に拍車をかけているということです。FAOの発表によれば、すでに世界の3分の1の表土が失われ、2050年には世界の90%以上の土壌が劣化するといわれています。また地球上の水のうち淡水は2.5%しかなく、近年は干ばつが相次いで水不足が深刻化しています。このまま化学肥料農業を続けることは難しいでしょう。
また、化学肥料の原料はリンやカリウム、石油などです。しかし、リン鉱石やカリウム鉱石は数十年以内に枯渇するのではないかといわれています。石油もいつか枯渇します。
人類はそう遠くない将来に化学肥料農業を持続できなくなり、持続可能な循環型農業へ転換せざるをえなくなるということです。
本末転倒な安全保障政策
―― 日本の食料安全保障はどういう状況になっているのですか。
鈴木 戦後日本は世界の食料システムの中で海外から食料を輸入してきました。しかし、その前提が崩れつつあるいま、日本が飢餓に陥るリスクは高まっています。
まず日本は食料を海外に依存していますが、日本向けの物流は不安定化しています。日本の食料自給率は先進国最低レベルの37%ですが、「真の自給率」はもっと低い。野菜の種や家畜のエサ、鶏のヒナは90%以上、化学肥料の原料であるリンやカリもほぼ100%海外に依存しているからです。しかし、コロナやウクライナ戦争、中国の爆買いの影響で食料や原料の輸入が難しくなっています。
たとえば、日本は大豆の94%を海外に依存していて300万トンを輸入していますが、中国は1億トンです。日本の輸入量は中国の端数にすぎず、中国がもう少し買い足せば日本の分はなくなってしまいます。すでに牧草は中国に買い負けていて、日本の酪農家はアメリカまで直接買い付けに行かざるをえないような状況になっています。
食料や原料だけではなく、農業人材も海外に依存しています。近年、日本の農家や酪農家では主に外国人労働者(技能実習生)が働いていますが、コロナの影響で技能実習生の来日がストップした結果、少なくない農家や酪農家が廃業を余儀なくされています。
そもそも日本向けの物流は縮小傾向にあります。近年、コンテナ船は巨大化していますが、大きくなりすぎて日本の港湾には停泊できなくなってきています。そのため、巨大コンテナ船は中国の大連で荷下ろしをして、日本向けの物品は大連から小分けして運ぶという状況になっています。日本は物流のメインストリームから外れつつあるのです。
コロナやウクライナ戦争の影響で離農も加速しています。ロシアの輸出規制や石油価格の高騰により、肥料や飼料は2倍、燃料は1.3倍になり、生産コストが増大しています。その結果、畜産業を中心に農家の廃業が増えているのです。
先日、日本農業新聞(12月5日)は「酪農家離農加速」という記事を掲載して、飼料価格の高騰によって4月からの半年間で酪農家400戸(3.4%)が離農したと報じています。これは去年の1.4~2倍のペースだといいます。私自身、今年は酪農家が経営難から自殺してしまったという話を何度も聞いています。
ところが、政府はこうした現状を放置しています。政府は物価高対策として30兆円規模の補正予算を組みましたが、農家を救済するための予算はほとんどありません。
飢餓のリスクは高まっているが、食料自給率はさらに下がろうとしている、これが日本の現実です。
―― 日本はどうすべきですか。
鈴木 日本は独立国として国民を守るために飢餓に備えなければなりません。コロナやウクライナ戦争を機に食料輸入国としてのあり方を見直した上で、食料安全保障を強化して食料自給率の向上に取り組むべきです。
喫緊の課題は農家の救済です。政府は3兆円規模の予算を組み、農家の赤字補填に踏み切るべきです。
また、食料の増産・備蓄も重要です。すでに世界の飢餓人口は8億人であり、日本国内でも貧困家庭の子どもをはじめ国民が飢えています。政府は国内外の飢餓に対応すべきです。
さらに、化学肥料農業の限界を踏まえて、いまのうちから有機農業を中心とする循環型農業へのシフトチェンジを進めるべきです。
―― 政府は食料安全保障に取り組んでいるのですか。
鈴木 現在、政府は中国の脅威を念頭に、「国民の生命を守る」ために安全保障政策を進めていますが、食料安全保障の観点がすっかり抜け落ちています。たとえば、政府はGDP比2%まで防衛費を拡大する方針ですが、農水予算を拡大する気はないようです。新たに省庁横断型の「総合防衛費」も創設する方針ですが、食料安全保障に関連する予算は入っていません。また、政府はミサイルをはじめとする軍備を増強しようとしていますが、「武器より安い武器」である食料を増産する意思は見られません。
これでは「国民の命を守る」ことはできず、中国の脅威に対抗することもできません。日本は中国から大量の食料を輸入しています。だから、仮に台湾有事が起きてシーレーンが封鎖されれば、あるいは中国から食料の輸出を制限されて「兵糧攻め」に遭えば、それだけでお手上げです。日本は中国と戦う前に飢えます。「腹が減っては戦はできぬ」のです。
反対論に答える
―― 農業政策の議論では「食料自給率をあげる必要はない」という反対論も根強くあります。たとえば、食料自給率をあげると日本が不作に見舞われた時に食料が確保できなくなるため、食料の輸入先をより多角化すべきだという声があります。
鈴木 海外に依存していても不作のリスクは同じです。少数の食料生産国が不作になれば、多数の食料輸入国が飢えることになります。また、輸入先を多角化しても、緊急時には輸送が停止したり中国に買い負けるリスクがあります。
そもそも「お金があっても食料が買えない事態にどう備えるか」を議論しているところで、「色んなところから食料を買えばいい」というのはナンセンスです。
―― 日本は農業生産額世界第10位の「農業大国」だという指摘もあります。
鈴木 農家の方々の経営努力は素晴らしいと思います。ただ、農業生産「額」と農業生産「量」は全く別の議論です。
確かに日本の農業生産額は世界トップクラスですが、カロリーを生む穀物自給率は28%で先進国最低レベルです。高級サクランボが売れれば生産額はあがりますが、飢餓が起きた時にサクランボばかり食べるというわけにはいきません。農業生産額が高いからといって、農業生産量が低くてもいいということにはならないのです。
―― 政府が農業を保護するのは統制経済だという批判もあります。
鈴木 それをいうなら、欧米こそ統制経済です。欧米は表向き自由経済を掲げていますが、現実には政府が介入して農業を手厚く保護し、補助金漬けの農産品を輸出しまくっているのです。日本もそうすべきです。
―― 農水省は予算を取るために危機を煽っているといわれています。
鈴木 その指摘が正しいならば、コロナやウクライナ戦争の影響で離農が加速しているいまこそ、農水省は予算を取りにいくはずです。しかし、そうした動きは全く見られません。
すでに食料危機が始まっているのだから、むしろ農水省はきちんと危機感を喚起して食料安全保障のための予算を取りにいくべきです。
―― 有機農業は生産性が低いため、既存の人口を養うことができないともいわれます。
鈴木 化学肥料農業から有機農業へ転換すると生産量が半減するとよくいわれます。しかし、日本には有機農業のノウハウが蓄積されており、化学肥料農業と同じかそれ以上の生産量をあげている有機農家も少なくありません。そうした知見を集めれば、有機農業の生産性を高めることは十分可能だと思います。化学肥料農業が限界に近付いている以上、その可能性を追求していくべきです。
―― 私たちにできることは何でしょうか。
鈴木 食料安全保障を支えるのは農家です。日本の農家は過保護だと批判されますが、実際には政府の支援がほとんどない中で生き残ってきた精鋭揃いです。そして、その農家を支えるのは私たち消費者です。私たち一人一人が危機感を共有して「何を買って食べるのか」という行動を変えれば、現在の状況も必ず変えることができます。
私が希望を感じたのは、新著の読者から「自分たちに何ができるのかのヒントを見つけることができた」という声が沢山届いたことです。本誌の読者にも、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
(12月2日 聞き手・構成 杉原悠人)」