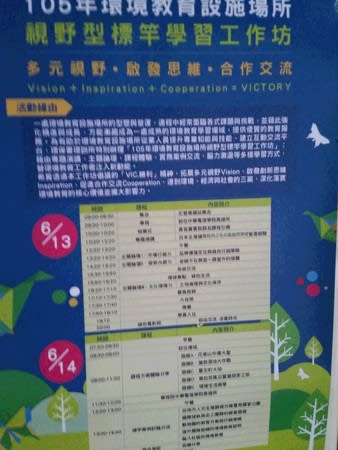中国杭州へ18日間の長旅をして来ました。 何をして来のか、話が前後してしまうかもしれませんが、記録がてらの日記を順次アップしてゆきます。
10月27ー28日
杭州と新千歳空港の間に海南航空の直通便が就航し、5時間かからずに渡航することができるようになりました。杭州というと日本人にはあまり馴染みが薄いかもしれませんが、上海のちょっと北西側かな。 ここに天目山という場所があり、日本の仏教・臨済宗の発祥の地であり、栄西が何度も訪れて、開祖に至ったようだ。西天目山には禅浄寺という立派がお寺があるが、天目山には東天目山と呼ばれる地域もあり、そちらにも大きなお寺があるらしい。2度目の訪問なのだが、今回も天目地域の全貌が掴めていないので、このあたりの歴史はまだまだ、勉強不足で怪しいが・・・、日本とも関わりの深い場所だ。 この地の保全と観光開発を大華グループという不動産開発会社が政府から70年の借地権をもって進めている。 その大華財閥の子会社として、2年前にこの地に大地之野自然学校が開校しました。
その創設者が2年続けて、北海道に自然学校視察ツアーに来た関係から親しくなり、スタッフ研修などをすることに。なりました。今回は、杭州で開催される全国自然教育フォーラム、大地之野が主催するアジア自然教育連盟フォーラムの二箇所での講演と大地之野自然学校主催のセミナーのファシリテーターとして訪中しました。
ちこと午後の便で千歳空港発。夕方に杭州空港着。大地之野自然学校の現代表のマンゴー(ネイチャーネーム、キャンプネーム)の出迎えを受け、全国自然教育フォーラムの会場となる杭州市内の大きなホテルへ移動。
このフォーラムは、中国の大手IT企業(楽天みたいな企業)ARIBABAがCSR活動として全面バックアップし、大地之野自然学校が実行部隊の中核としてし切っていました。翌28日、中国全土から700名の自然教育関係者が参集している大きな大会でした。ARIBABAや中国環境省から挨拶があり開式。当地浙江省の環境保全局のお役人さんの挨拶では、「ここ杭州を生態文明の拠点としたい」との高らかな開催祝辞がありました。 フォーラムは28日一日だけなので、27日前夜が参加者の交流会のような感じでしたが、こういった大きなフォーラム運営についてのノウハウはまだまだの感じでした。 せっかくこれだけの人々が集まっているのに、情報交換や交流の仕掛けが少なくてもったいないなと感じました。
まったく別ルートからの招聘で、くりこま自然学校の佐々木さんや、環境教育事務所の森さんもゲストスピーカーとして参加しており、私と3者の関係者で夕食会食をしました。

翌28日、基調講演は、ネイチャーゲームの創始者である、コーネルさんでした。 その後、複数の分科会会場にわかれ、事例報告の形式のフォーラムでした。 私は、日本の自然学校全体のざっくりとした動向と黒松内ぶなの森自然学校のレポートをしました。 大地之野から若い通訳の女性が配置されましたが、自然環境教育には精通していないのでこの通訳はさすがに荷が重い・・・。 幸いにして日中市民ネットワークの朱さん(ファンシー)も参加していたので、急遽、通訳の代役をお願いして、なんとか無事に役割を果たせました。

















 2週間の旅も最終夜。明日は早朝5時半出発で新潟経由で帰松だ。新潟に一泊してゆっくりと振り返ってから帰りたいとも思うが、飛行機の関係で直帰します。
2週間の旅も最終夜。明日は早朝5時半出発で新潟経由で帰松だ。新潟に一泊してゆっくりと振り返ってから帰りたいとも思うが、飛行機の関係で直帰します。