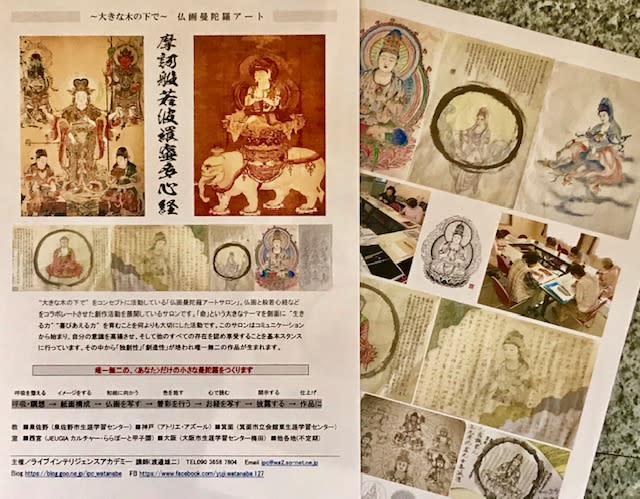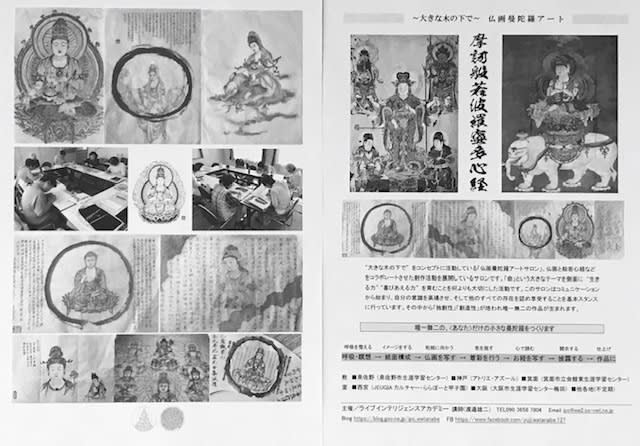刺繍打敷の工房で、日本刺繍の製作現場を観せていただいた。お寺でよく見かける、卓の天板の下にはさむ敷物。この敷物の修復している、京都ならではの工房、和光舎の三条店におじゃました。
大きなモノはパーツごとに刺し、それを一枚の厚めの布地にまとめる。写真のものがそうである。同工房は修復がメイン、長年使うと糸が擦れ切れてしまうのでお寺からの修復がひっきりなしという。たまに祇園祭などの美術品などの修復も手がけている。
ひと針ひと針刺す作業は気が遠くなる。それをコツコツと丁寧に仕上げていく。昔も今も変わらない匠の技があって伝統が受け継がれていく。