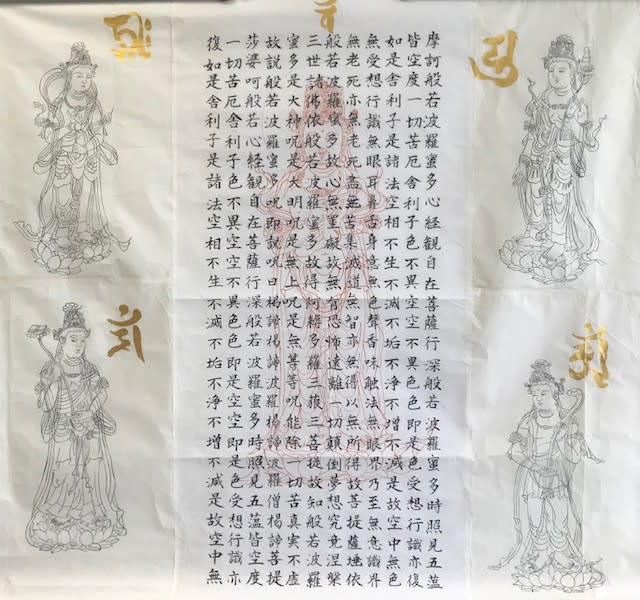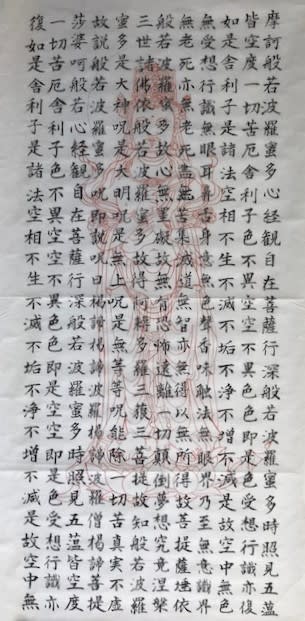尾道。瀬戸内で有数の観光地として人気を博している。観光に訪れるのは女性が多い。女性にとって見どころが多い町なのだろう。昔と今が適度に混在し “オシャレなまち” として心に響いているようだ。女性に限らず、男性にも魅力的な町として存在が高まっている。
それは、アクティブな活動から芸術文化の探訪、そして自然の恵による尾道グルメと郷土料理のコラボ。それに情緒観あふれる瀬戸内風景などあらゆる観光要素がつまっている。とくに女性の心を捉えてやまないのが「猫ちゃん」。狭い坂道に猫の風景が女性の “かわい~” の琴線を響かせている。
観光名所・名物にこと欠かない尾道であるが、おやじの切れかけた琴線を揺らすのが「港の風景」。むかしと変わらない風景にどうも引き寄せられてゆく。思い出に浸ることができる昔のままの風景を、時をへて楽しむのも観光の目玉になるような気もしたが・・・。





小津安二郎監督作品の「東京物語」の尾道ロケの写真が塀に
リポート&写真/ 渡邉雄二
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/