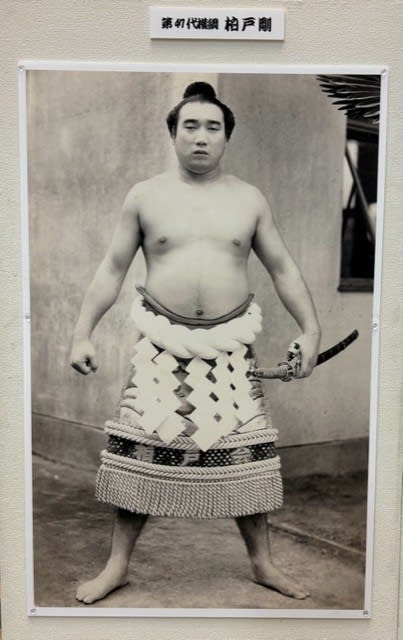日本で外国人に喜ばれるのは、独特のコトやモノを見る学ぶことに加えやはり体験することのようだ。今回のヨーロッパ南武道のセミナーの合間を利用していくつかの体験が人気だった。
そのひとつが「日本酒のテイスティング」。左京区の松井酒造が行っている酒蔵見学が彼らに印象深く残ったようだ。蔵を実際に見学しながら酒造りの概要を聞く。そして松井酒造がつくる最高の酒をテイスティングし日本の味を体感する。全員が口をそろえ “旨い” と絶賛する。外国人の口に合うものかと少々不安であったが、これほど喜ぶものか、といささかびっくり。
そして、四季堂での抹茶体験。茶筅で混ぜ、飲む作法を体験したが、あの味はやはり抵抗があるようだ。でも、これが日本の抹茶なんだと納得していた。日本をより理解するよき材料になったのではと勝手に思っている。
さらに、日本体験の定番である「たこ焼きづくり」は、実に楽しそうだった。料理ではなくお菓子作り感覚で面白さを体験。なんでタコを入れるの? という質問があったが、それには関西人の筆者でも頭を抱えた。 “日本は食材が豊富だから、たまたま近くにあったタコを入れたのでは” といい加減な回答で笑いを誘った。
日本には大雑把なものから繊細なものまで、楽しむ領域が広いし深い。これが日本の魅力になっている。古いものに今の時代のストーリーを織り交ぜた日本文化の魅力をさらに向上させている。それを求め外国の人たちは日本をめざす。




文・写真/ 渡邉雄二
#南武道 #ヨーロッパ南武道 #楽しい体験 #日本酒テイスティング #抹茶体験 #たこ焼きづくり #日本の魅力 #日本文化の魅力