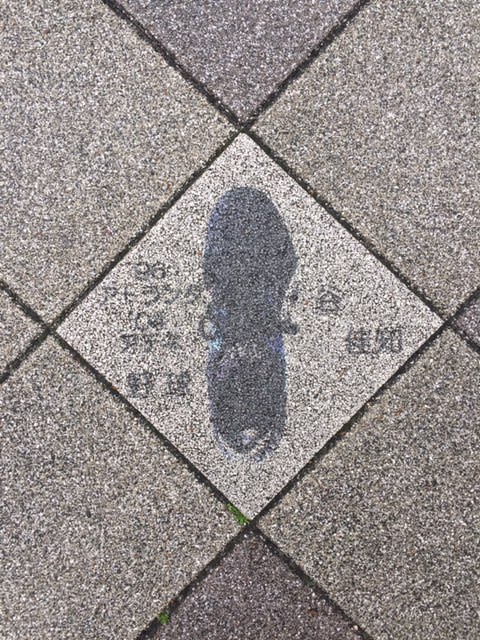長い間、テレビ番組等で「ビートたけし」というお笑い芸人を観てきた。
若いときから、人を蹴散らし毒舌をを吐いてテレビ業界のバラエティ分野でのし上がり"殿"といわれ君臨している。
ビートたけしのイメージは、"無鉄砲""我侭"破天荒"という言葉がぴったりあう人物像として映っている。
だから、テレビ界や映画界等で活躍できている、という想いをもつ人たちも多いはずである。
ただ才能や力だけで、テレビ番組の看板として続くわけでもないだろう。
なにか極められた能力を持ち合わせているはずなのだが、あのイメージが強すぎてなかなか我々、視聴者には見えてこない。
しかしながら、あのビートたけしが書いたとは想像もつかない文章の一節をネットで見つけた。
それが下記のタイトルのものだった。
【 作法と気遣い 】
作法というのは、
突き詰めて考えれば、
他人への気遣いだ。
具体的な細かい作法を
いくら知っていても、
本当の意味で、
他人を気遣う気持ちがなければ、
何の意味もない。
その反対に、
作法なんかよく知らなくても、
ちゃんと人を
気遣うことができれば、
大きく作法を外すことはない。
駄目な奴は、
この気遣いが
まったくできていない。
人の気持ちを考えて
行動するという発想を、
最初から持っていないのだ。
他人への気遣いで大切なのは、
話を聞いてやることだ。
人間は歳を取ると、
どういうわけかこれが
苦手になるらしい。
むしろ、
自分の自慢話ばかり
したがるようになる。
だけど、
自慢話は
一文の得にもならないし、
その場の雰囲気を悪くする。
それよりも、
相手の話を聞く方がずっといい。
料理人に会ったら料理のこと、
運転手に会ったらクルマのこと、
坊さんに会ったら
あの世のことでも何でも、
知ったかぶりせずに、
素直な気持ちで
聞いてみたらいい。
自慢話なんかしているより、
ずっと世界が広がるし、
何より場が楽しくなる。
例え知っていたとしても、
一応ちゃんと聞くのだ。
そうすれば、
専門家というものは、
きっとこちらの
知らないことまで
話してくれる。
井戸を掘っても、
誘い水をしないと
水が湧いてこないように、
人との会話にも
誘い水が必要なのだ。
~ ビート たけし ~
若いときから、人を蹴散らし毒舌をを吐いてテレビ業界のバラエティ分野でのし上がり"殿"といわれ君臨している。
ビートたけしのイメージは、"無鉄砲""我侭"破天荒"という言葉がぴったりあう人物像として映っている。
だから、テレビ界や映画界等で活躍できている、という想いをもつ人たちも多いはずである。
ただ才能や力だけで、テレビ番組の看板として続くわけでもないだろう。
なにか極められた能力を持ち合わせているはずなのだが、あのイメージが強すぎてなかなか我々、視聴者には見えてこない。
しかしながら、あのビートたけしが書いたとは想像もつかない文章の一節をネットで見つけた。
それが下記のタイトルのものだった。
【 作法と気遣い 】
作法というのは、
突き詰めて考えれば、
他人への気遣いだ。
具体的な細かい作法を
いくら知っていても、
本当の意味で、
他人を気遣う気持ちがなければ、
何の意味もない。
その反対に、
作法なんかよく知らなくても、
ちゃんと人を
気遣うことができれば、
大きく作法を外すことはない。
駄目な奴は、
この気遣いが
まったくできていない。
人の気持ちを考えて
行動するという発想を、
最初から持っていないのだ。
他人への気遣いで大切なのは、
話を聞いてやることだ。
人間は歳を取ると、
どういうわけかこれが
苦手になるらしい。
むしろ、
自分の自慢話ばかり
したがるようになる。
だけど、
自慢話は
一文の得にもならないし、
その場の雰囲気を悪くする。
それよりも、
相手の話を聞く方がずっといい。
料理人に会ったら料理のこと、
運転手に会ったらクルマのこと、
坊さんに会ったら
あの世のことでも何でも、
知ったかぶりせずに、
素直な気持ちで
聞いてみたらいい。
自慢話なんかしているより、
ずっと世界が広がるし、
何より場が楽しくなる。
例え知っていたとしても、
一応ちゃんと聞くのだ。
そうすれば、
専門家というものは、
きっとこちらの
知らないことまで
話してくれる。
井戸を掘っても、
誘い水をしないと
水が湧いてこないように、
人との会話にも
誘い水が必要なのだ。
~ ビート たけし ~