経済政策総点検 骨太方針と成長戦略 ⑥ ジェンダー平等 「女性活躍」言うが
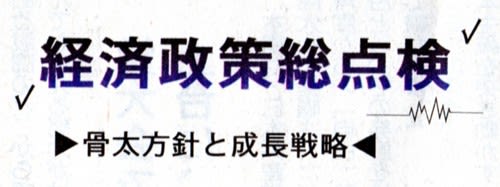
2024年の日本人の出生数が70万人を切るとの予測がでるなど急速な少子化が社会問題化しています。岸田文雄政権は、少子化・人口減少をくい止めるため「我が国の持てる力を総動員」するとし、骨太方針でも「政府一丸」となって取り組むと明記しました。
子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人持つかは、それぞれの女性やカップルが決めることです。国連人口基金は、人口が多すぎる、少なすぎるという問題設定を「有害」だと批判。問うべきは「一人ひとりが性と生殖に関する自己決定権を含め、基本的人権を行使する術を持っているかどうか」だと強調します。(23年版「世界人口白書」)
岸田政権も露骨な出産奨励は言葉にせず、骨太方針でも▽仕事と子育ての両立支援▽女性活躍▽男女賃金格差是正▽ジェンダー格差解消―などを進め、「結果として出生率が向上する社会を構築する」といいます。
ゆがんだ刺激策
問題はスローガンと骨太方針に盛り込まれた政策の落差です。骨太方針には、医療や介護など公的サービスの縮小が女性の「性と生殖に関する権利」を阻害するという視点がなく、むしろ社会保障の給付抑制や利用者負担増を経済成長の柱と位置づけています。社会保障給付の抑制などによって社会保険料を低く抑えれば、現役世代の消費が活性化し経済の好循環が生まれるという理屈です。
典型が、介護の利用者負担割合の引き上げです。骨太方針は、原則1割の利用者負担が2割になる所得要件を引き下げ、2割負担の対象者を拡大する方向性を示しています。利用者負担の引き上げは経済的理由による利用控えを生み、家族介護を増やします。厚生労働省の「国民生活基礎調査」(22年)によれば、家族介護の「主な介護者」の7割を女性が占めます。
■介護の利用者負担が2割になったときの負担額
―単身世帯が居宅サービスを利用限度額まで利用した場合―
※介護保険給付の利用料には所得に応じて上限額(高額介護サービス費)が決まっているものの、上限を超えた分も含めていったん払ったうえで、数カ月後に償還される仕組みです。負担の上限額が4万4400円となるのは前年所得が市町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収770万円)来満の場合
格差解消に逆行
公的介護の縮小は女性の家族介護をさらに増やすことになり、「女性活躍」や「ジェンダレ格差解消」に反します。
岸田政権は、女性が多く働くケア労働の公的価格(人件費)を低く抑える歴代自公政権の方針を踏襲しています。4月には訪問介護の基本報酬を大幅に引き下げました。これも政府に言わせれば保険料負担抑制による景気刺激策です。一方、介護事業所にとっては減収になるため、労働者の賃金を抑制する要因になります。
介護職員の7割、特に訪問介護職員の8割を女性が占めます。看護師や保育士の女性比率は9割超です。介護報酬の引き下げをはじめ、ケア労働の公的価格抑制は「男女賃金格差是正」に逆行しています。
骨太方針は、非正規労働者の正規転換を掲げますが、政治の責任で直ちに実施できる非正規公務員の正規化には背を向けています。約9万人いる国家公務員の非常勤職員の3分の2、74万人いる自治体の非正規公務員の4分の3を女性が占めます。日本共産党の田村智子参院議員事務所の調査では、国の機関の男性正規職員を100とした場合、女性非正規職員の賃金は37・1です。
骨太方針に盛り込まれた政策が実行されれば、ジェンダー格差や、子どもを産みづらく育てにくい状況はいっそう強まる危険性があります。
(佐久間亮)(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年7月25日付掲載
子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人持つかは、それぞれの女性やカップルが決めること。国連人口基金は、人口が多すぎる、少なすぎるという問題設定を「有害」だと批判。問うべきは「一人ひとりが性と生殖に関する自己決定権を含め、基本的人権を行使する術を持っているかどうか」だと強調します。(23年版「世界人口白書」)
骨太方針は、原則1割の利用者負担が2割になる所得要件を引き下げ、2割負担の対象者を拡大する方向性を示しています。利用者負担の引き上げは経済的理由による利用控えを生み、家族介護を増やします。
約9万人いる国家公務員の非常勤職員の3分の2、74万人いる自治体の非正規公務員の4分の3を女性が占めます。日本共産党の田村智子参院議員事務所の調査では、国の機関の男性正規職員を100とした場合、女性非正規職員の賃金は37・1。
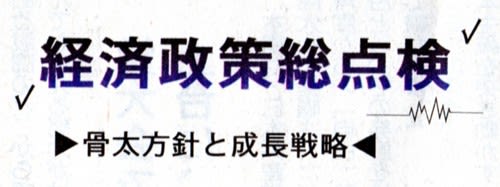
2024年の日本人の出生数が70万人を切るとの予測がでるなど急速な少子化が社会問題化しています。岸田文雄政権は、少子化・人口減少をくい止めるため「我が国の持てる力を総動員」するとし、骨太方針でも「政府一丸」となって取り組むと明記しました。
子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人持つかは、それぞれの女性やカップルが決めることです。国連人口基金は、人口が多すぎる、少なすぎるという問題設定を「有害」だと批判。問うべきは「一人ひとりが性と生殖に関する自己決定権を含め、基本的人権を行使する術を持っているかどうか」だと強調します。(23年版「世界人口白書」)
岸田政権も露骨な出産奨励は言葉にせず、骨太方針でも▽仕事と子育ての両立支援▽女性活躍▽男女賃金格差是正▽ジェンダー格差解消―などを進め、「結果として出生率が向上する社会を構築する」といいます。
ゆがんだ刺激策
問題はスローガンと骨太方針に盛り込まれた政策の落差です。骨太方針には、医療や介護など公的サービスの縮小が女性の「性と生殖に関する権利」を阻害するという視点がなく、むしろ社会保障の給付抑制や利用者負担増を経済成長の柱と位置づけています。社会保障給付の抑制などによって社会保険料を低く抑えれば、現役世代の消費が活性化し経済の好循環が生まれるという理屈です。
典型が、介護の利用者負担割合の引き上げです。骨太方針は、原則1割の利用者負担が2割になる所得要件を引き下げ、2割負担の対象者を拡大する方向性を示しています。利用者負担の引き上げは経済的理由による利用控えを生み、家族介護を増やします。厚生労働省の「国民生活基礎調査」(22年)によれば、家族介護の「主な介護者」の7割を女性が占めます。
■介護の利用者負担が2割になったときの負担額
―単身世帯が居宅サービスを利用限度額まで利用した場合―
| いったん払う 利用者負担額 | 最終的な利用者負担額 (償還払い後) | ||
| 1割 | 2割 | 2割(1割からの負担増) | |
| 要支援1 | 5032円 | 1万64円 | 1万64円(5032円) |
| 要支援2 | 1万531円 | 2万1062円 | 2万1062円(1万531円) |
| 要介護1 | 1万6765円 | 3万3530円 | 3万3530円(1万6765円) |
| 要介護2 | 1万9705円 | 3万9410円 | 3万9410円(1万9705円) |
| 要介護3 | 2万7048円 | 5万4096円 | 4万4400円(1万7352円) |
| 要介護4 | 3万938円 | 6万1876円 | 4万4400円(1万3462円) |
| 要介護5 | 3万6217円 | 7万2434円 | 4万4400円(8183円) |
格差解消に逆行
公的介護の縮小は女性の家族介護をさらに増やすことになり、「女性活躍」や「ジェンダレ格差解消」に反します。
岸田政権は、女性が多く働くケア労働の公的価格(人件費)を低く抑える歴代自公政権の方針を踏襲しています。4月には訪問介護の基本報酬を大幅に引き下げました。これも政府に言わせれば保険料負担抑制による景気刺激策です。一方、介護事業所にとっては減収になるため、労働者の賃金を抑制する要因になります。
介護職員の7割、特に訪問介護職員の8割を女性が占めます。看護師や保育士の女性比率は9割超です。介護報酬の引き下げをはじめ、ケア労働の公的価格抑制は「男女賃金格差是正」に逆行しています。
骨太方針は、非正規労働者の正規転換を掲げますが、政治の責任で直ちに実施できる非正規公務員の正規化には背を向けています。約9万人いる国家公務員の非常勤職員の3分の2、74万人いる自治体の非正規公務員の4分の3を女性が占めます。日本共産党の田村智子参院議員事務所の調査では、国の機関の男性正規職員を100とした場合、女性非正規職員の賃金は37・1です。
骨太方針に盛り込まれた政策が実行されれば、ジェンダー格差や、子どもを産みづらく育てにくい状況はいっそう強まる危険性があります。
(佐久間亮)(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年7月25日付掲載
子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人持つかは、それぞれの女性やカップルが決めること。国連人口基金は、人口が多すぎる、少なすぎるという問題設定を「有害」だと批判。問うべきは「一人ひとりが性と生殖に関する自己決定権を含め、基本的人権を行使する術を持っているかどうか」だと強調します。(23年版「世界人口白書」)
骨太方針は、原則1割の利用者負担が2割になる所得要件を引き下げ、2割負担の対象者を拡大する方向性を示しています。利用者負担の引き上げは経済的理由による利用控えを生み、家族介護を増やします。
約9万人いる国家公務員の非常勤職員の3分の2、74万人いる自治体の非正規公務員の4分の3を女性が占めます。日本共産党の田村智子参院議員事務所の調査では、国の機関の男性正規職員を100とした場合、女性非正規職員の賃金は37・1。



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます