独占パワー④ 低下する労働分配率
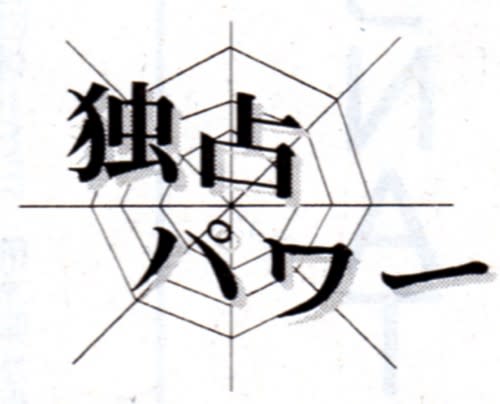
政治経済研究所 合田寛主任研究員
大企業の独占パワーの増大は、生み出された富を労働者・消費者・中小企業からかすめとり、企業のオーナーへ分配する力として働いています。
CEO報酬急増
巨大企業の最高経営責任者(CEO)への報酬や株主への配当が急増しています。米国350社の大企業を対象とした調査によれば、賃金に対するCEO報酬の比率は、21倍(1965年)から344倍(2022年)へと大幅に増えています。
これは経営者のスキルや生産性の反映ではなく、自らの報酬を決める経営者のパワーの増大を示すものです。また、「会社は株主のもの」と考える株主資本主義の下で、株主目線の経営を求める大株主の意向を反映して、経営者への株式報酬が増やされた結果です。日本の大企業でも、経営者への株式報酬や株主配当が顕著に増加し、米国式の株主資本主義が強まっています。
他方、独占パワーを強めた大企業は、労働者に対して賃金を抑制し、労働分配率を引き下げてきました。
独占パワーが強まればマークアップが高まる一方、労働分配率が低下することは多くの実証研究によって確かめられています。国際通貨基金(IMF)のスタッフ、アグスチン・ベラスケス氏の研究(23年)は、アメリカ製造業の労働分配率低下の76%はマーケット・パワーの増大で説明できるとしています。大企業のマーケット・パワーの増大は、利潤への配分を高める一方、労働者への配分を低下させ、労働分配率を低下させたと分析しています。
物価が上がれば賃上げ政策が必要であったにもかかわらず、賃金が抑制されてきたために、実質賃金は大幅に引き下げられてきたのです。

アップルのCEOティム・クック氏(ロイター)
実質賃金の低下
国際労働機関(ILO)の「世界賃金報告2022―23」は、52カ国を対象とした調査結果として、賃金の伸びと労働生産性の伸びのギャップは一方的に拡大し、22年には21世紀の初め以来、最も大きくなったことを指摘しています。
低い実質賃金は、とくに女性や非正規労働者、移民労働者など、差別された労働者を苦しめ、その生活を圧迫しており、貧困を生み出す原因となっています。
実質賃金の低下はとりわけ日本で深刻です。ニッセイ基礎研究所の最近のリボート(「日米欧の実質賃金推移とその特徴」24年5月30日)は、日本、米国、欧州の1999年から2023年までの実質賃金の上昇率とその内訳の比較をしています。
それによると、1人当たりの実質賃金の上昇率は米国で34・0%、英国で42・0%、ユーロ圏平均でも10・0%であるのに対して、日本はマイナス2・0%と、極端に低い結果となっています。1人当たりの生産性が上昇しているにもかかわらず、実質賃金が下落しているのは世界の主要国の中で日本だけです。
米国、ユーロ圏など、労働分配率が下がっている国でも実質賃金は上がっているのに対して、日本では労働分配率も実質賃金も下がっています。労働分配率の長期的な低下が実質賃金の引き下げにつながっていることを示しています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年7月13日付掲載
米国350社の大企業を対象とした調査によれば、賃金に対するCEO報酬の比率は、21倍(1965年)から344倍(2022年)へと大幅に増えています。
「会社は株主のもの」と考える株主資本主義の下で、株主目線の経営を求める大株主の意向を反映して、経営者への株式報酬が増やされた結果。
国際労働機関(ILO)の「世界賃金報告2022―23」は、52カ国を対象とした調査結果として、賃金の伸びと労働生産性の伸びのギャップは一方的に拡大し、22年には21世紀の初め以来、最も大きくなったことを指摘。
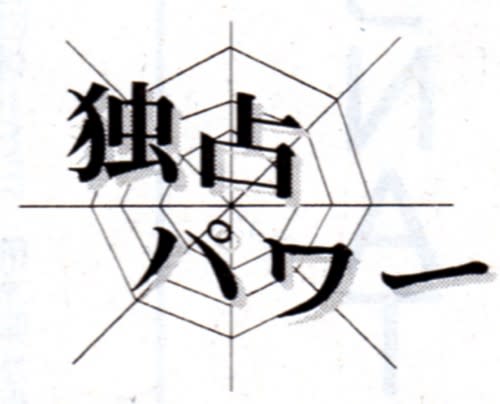
政治経済研究所 合田寛主任研究員
大企業の独占パワーの増大は、生み出された富を労働者・消費者・中小企業からかすめとり、企業のオーナーへ分配する力として働いています。
CEO報酬急増
巨大企業の最高経営責任者(CEO)への報酬や株主への配当が急増しています。米国350社の大企業を対象とした調査によれば、賃金に対するCEO報酬の比率は、21倍(1965年)から344倍(2022年)へと大幅に増えています。
これは経営者のスキルや生産性の反映ではなく、自らの報酬を決める経営者のパワーの増大を示すものです。また、「会社は株主のもの」と考える株主資本主義の下で、株主目線の経営を求める大株主の意向を反映して、経営者への株式報酬が増やされた結果です。日本の大企業でも、経営者への株式報酬や株主配当が顕著に増加し、米国式の株主資本主義が強まっています。
他方、独占パワーを強めた大企業は、労働者に対して賃金を抑制し、労働分配率を引き下げてきました。
独占パワーが強まればマークアップが高まる一方、労働分配率が低下することは多くの実証研究によって確かめられています。国際通貨基金(IMF)のスタッフ、アグスチン・ベラスケス氏の研究(23年)は、アメリカ製造業の労働分配率低下の76%はマーケット・パワーの増大で説明できるとしています。大企業のマーケット・パワーの増大は、利潤への配分を高める一方、労働者への配分を低下させ、労働分配率を低下させたと分析しています。
物価が上がれば賃上げ政策が必要であったにもかかわらず、賃金が抑制されてきたために、実質賃金は大幅に引き下げられてきたのです。

アップルのCEOティム・クック氏(ロイター)
実質賃金の低下
国際労働機関(ILO)の「世界賃金報告2022―23」は、52カ国を対象とした調査結果として、賃金の伸びと労働生産性の伸びのギャップは一方的に拡大し、22年には21世紀の初め以来、最も大きくなったことを指摘しています。
低い実質賃金は、とくに女性や非正規労働者、移民労働者など、差別された労働者を苦しめ、その生活を圧迫しており、貧困を生み出す原因となっています。
実質賃金の低下はとりわけ日本で深刻です。ニッセイ基礎研究所の最近のリボート(「日米欧の実質賃金推移とその特徴」24年5月30日)は、日本、米国、欧州の1999年から2023年までの実質賃金の上昇率とその内訳の比較をしています。
それによると、1人当たりの実質賃金の上昇率は米国で34・0%、英国で42・0%、ユーロ圏平均でも10・0%であるのに対して、日本はマイナス2・0%と、極端に低い結果となっています。1人当たりの生産性が上昇しているにもかかわらず、実質賃金が下落しているのは世界の主要国の中で日本だけです。
米国、ユーロ圏など、労働分配率が下がっている国でも実質賃金は上がっているのに対して、日本では労働分配率も実質賃金も下がっています。労働分配率の長期的な低下が実質賃金の引き下げにつながっていることを示しています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年7月13日付掲載
米国350社の大企業を対象とした調査によれば、賃金に対するCEO報酬の比率は、21倍(1965年)から344倍(2022年)へと大幅に増えています。
「会社は株主のもの」と考える株主資本主義の下で、株主目線の経営を求める大株主の意向を反映して、経営者への株式報酬が増やされた結果。
国際労働機関(ILO)の「世界賃金報告2022―23」は、52カ国を対象とした調査結果として、賃金の伸びと労働生産性の伸びのギャップは一方的に拡大し、22年には21世紀の初め以来、最も大きくなったことを指摘。



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます