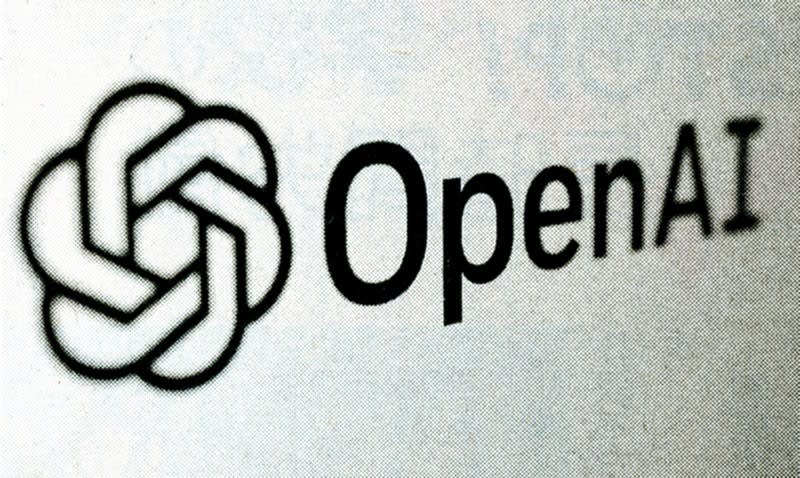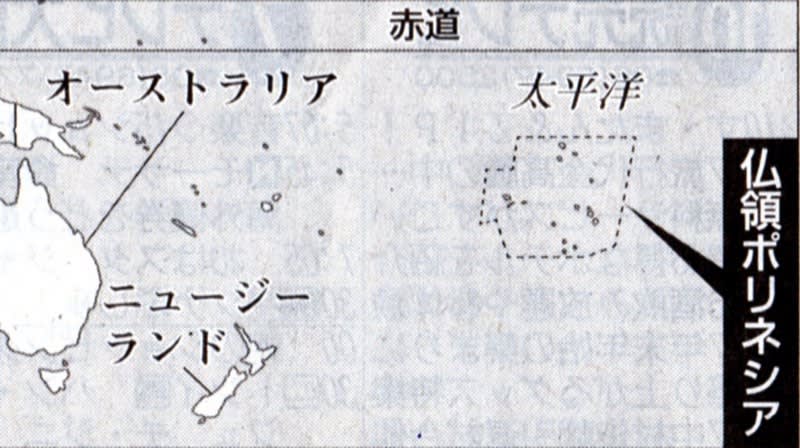AIとルール④ 兵器利用禁止交渉に逆流

経済研究者 友寄英隆さん(寄稿)
国連のアントニオ・グテレス事務総長は10月26日、人工知能(AI)のリスク、機会、国際ガバナンスに関する新たな諮問機関を国連に設置すると発表しました。この機関は、AIの開発・利用のあり方を国際的に見守り、支援するのが目的です。
グテレス事務総長は、「将来に目を向けると、気候危機とデジタル変革という二つの地殻変動が21世紀を形作ることになるだろう」(20年7月18日、ネルソン・マンデラ記念講演)と述べたことがあります。同事務総長は、以前から「AIには驚くべき可能性と潜在的な危険性がある」と指摘していました。
デジタル格差
国連になぜAIの諮問機関を設置するのか。事務総長は会見で次のように述べています。
―現在、AIの専門知識は一握りの企業や一部の国に集中しており、それが「グローバルな不平等を深刻化させ、デジタル格差を亀裂へと変えてしまう」おそれがある。引き起こされるおそれのある損害には、誤情報や偽情報の拡散の加速化、偏見や差別の定着、監視やプライバシーの侵害、詐欺、その他の人権侵害などがあげられる。AIなどのデジタル技術が一部の諸国に独占されることによって、地球的規模で格差と分断がいっそう拡大・固定する―。
AIに関する諮問機関は、世界各国から選ばれた39人の専門家で構成されています。発表されたメンバーは、ジェンダーのバランスがとれており、地理的にも多様で、年齢的にも多世代にわたっています(日本からは江間有沙東京大学准教授、北野宏明ソニーグループ最高技術責任者の2人が選ばれています)。
国連のAIとのかかわりを考えるときに忘れることができないのは、AIの軍事的利用(たとえば無人戦闘機や殺人ロポットなど)を禁止する国際的ルールを作る活動です。
すでに13年から、国連はAI兵器についての議論を行ってきました。具体的には、国際連合軍縮拡大委員会、専門家会合、政府間パネルなどの枠組みを通じて、AI兵器の使用に関する議論や交渉がすすめられています。(年表)しかし、この10年間、AI兵器を禁止する国際条約作りは、米国、ロシアなど軍事大国の思惑のために、たいへん難航してきました。
国連でのAI兵器交渉
米国の新提案
23年に入って、米国政府は、AI兵器の国際交渉のなかで、まったく新たな提案を行いました。米国務省が23年2月16日に発表した「AIと自律化技術の責任ある軍事利用に関する政治宣言」と呼ばれる文書に、西側諸国の同意を取り付けはじめたのです。
この米国提案の「政治宣言」では▽軍事AIは国際法に従って開発すること▽各国のAI兵器の技術の原理について透明性を確保すること▽AIシステムの性能を検証する高い基準を設定すること―などが盛り込まれています。つまり、AI兵器を禁止するのでなく、「責任ある軍事利用」をはかるというものです。国連のこれまでの国際交渉にとっては、まったくの「逆流」と言うべき「宣言」です。この米国提案の「宣言」には、23年11月時点で、日本を含め「西側」の46カ国・地域が賛同(外務省資料)しています。
こうしたAI兵器をめぐる複雑な情勢のもとで、23年7月に国連安全保障理事会は、AIに関する初の会合を開きました。
AI兵器をめぐる国際環境は、新たな重要局面を迎えています。(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年12月22日付掲載
AIに関する諮問機関は、世界各国から選ばれた39人の専門家で構成。発表されたメンバーは、ジェンダーのバランスがとれており、地理的にも多様で、年齢的にも多世代に。
23年に入って、米国政府は、AI兵器の国際交渉のなかで、まったく新たな提案。AI兵器を禁止するのでなく、「責任ある軍事利用」をはかるというもの。AI兵器をめぐる国際環境は、新たな重要局面を。

経済研究者 友寄英隆さん(寄稿)
国連のアントニオ・グテレス事務総長は10月26日、人工知能(AI)のリスク、機会、国際ガバナンスに関する新たな諮問機関を国連に設置すると発表しました。この機関は、AIの開発・利用のあり方を国際的に見守り、支援するのが目的です。
グテレス事務総長は、「将来に目を向けると、気候危機とデジタル変革という二つの地殻変動が21世紀を形作ることになるだろう」(20年7月18日、ネルソン・マンデラ記念講演)と述べたことがあります。同事務総長は、以前から「AIには驚くべき可能性と潜在的な危険性がある」と指摘していました。
デジタル格差
国連になぜAIの諮問機関を設置するのか。事務総長は会見で次のように述べています。
―現在、AIの専門知識は一握りの企業や一部の国に集中しており、それが「グローバルな不平等を深刻化させ、デジタル格差を亀裂へと変えてしまう」おそれがある。引き起こされるおそれのある損害には、誤情報や偽情報の拡散の加速化、偏見や差別の定着、監視やプライバシーの侵害、詐欺、その他の人権侵害などがあげられる。AIなどのデジタル技術が一部の諸国に独占されることによって、地球的規模で格差と分断がいっそう拡大・固定する―。
AIに関する諮問機関は、世界各国から選ばれた39人の専門家で構成されています。発表されたメンバーは、ジェンダーのバランスがとれており、地理的にも多様で、年齢的にも多世代にわたっています(日本からは江間有沙東京大学准教授、北野宏明ソニーグループ最高技術責任者の2人が選ばれています)。
国連のAIとのかかわりを考えるときに忘れることができないのは、AIの軍事的利用(たとえば無人戦闘機や殺人ロポットなど)を禁止する国際的ルールを作る活動です。
すでに13年から、国連はAI兵器についての議論を行ってきました。具体的には、国際連合軍縮拡大委員会、専門家会合、政府間パネルなどの枠組みを通じて、AI兵器の使用に関する議論や交渉がすすめられています。(年表)しかし、この10年間、AI兵器を禁止する国際条約作りは、米国、ロシアなど軍事大国の思惑のために、たいへん難航してきました。
国連でのAI兵器交渉
| 年 | 月 | 動き |
| 2013 | 11 | 国連軍縮拡大委員会 |
| 2015 | 5 | 初の専門家会合 |
| 2017 | 11 | 特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の枠組みで専門家会合 |
| 2018 | 3 | 国連CCW締約国会議 |
| 2019 | 3 | ジュネーブ専門家会議 |
| 8 | 政府間パネル設置 | |
| 2020 | 国際人道法への適用 | |
| 2021 | 11 | CCWでの議論の本格化 |
| 2023 | 2 | 米国が「AIと自律化技術の責任ある軍事利用に関する政治宣君」を提案 |
| 7 | 国連安保理でAIを初の議題に(AI兵器も議論) |
米国の新提案
23年に入って、米国政府は、AI兵器の国際交渉のなかで、まったく新たな提案を行いました。米国務省が23年2月16日に発表した「AIと自律化技術の責任ある軍事利用に関する政治宣言」と呼ばれる文書に、西側諸国の同意を取り付けはじめたのです。
この米国提案の「政治宣言」では▽軍事AIは国際法に従って開発すること▽各国のAI兵器の技術の原理について透明性を確保すること▽AIシステムの性能を検証する高い基準を設定すること―などが盛り込まれています。つまり、AI兵器を禁止するのでなく、「責任ある軍事利用」をはかるというものです。国連のこれまでの国際交渉にとっては、まったくの「逆流」と言うべき「宣言」です。この米国提案の「宣言」には、23年11月時点で、日本を含め「西側」の46カ国・地域が賛同(外務省資料)しています。
こうしたAI兵器をめぐる複雑な情勢のもとで、23年7月に国連安全保障理事会は、AIに関する初の会合を開きました。
AI兵器をめぐる国際環境は、新たな重要局面を迎えています。(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年12月22日付掲載
AIに関する諮問機関は、世界各国から選ばれた39人の専門家で構成。発表されたメンバーは、ジェンダーのバランスがとれており、地理的にも多様で、年齢的にも多世代に。
23年に入って、米国政府は、AI兵器の国際交渉のなかで、まったく新たな提案。AI兵器を禁止するのでなく、「責任ある軍事利用」をはかるというもの。AI兵器をめぐる国際環境は、新たな重要局面を。