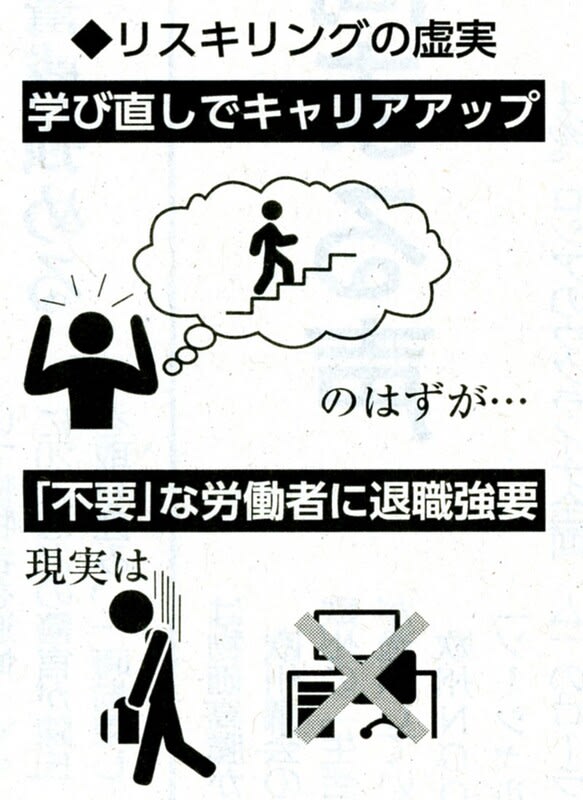賃金の上がる国へ③ 3者構成の原則を敵視

ジャーナリスト 昆弘見さん
政府の「三位一体の労働市場改革」は、決定過程に重要な問題があります。労働分野の政策は政府(公益)、労働者、使用者の3者対等の構成によって検討するというルールを無視してすすめられたことです。
「三位一体改革」の指針をまとめた「新しい資本主義実現会議」は、21人のメンバーのうち岸田文雄首相を含む大臣が6人、財界関係者が12人、学者が2人、連合会長が労働者代表で1人だけという構成で、過半数が財界関係者です。
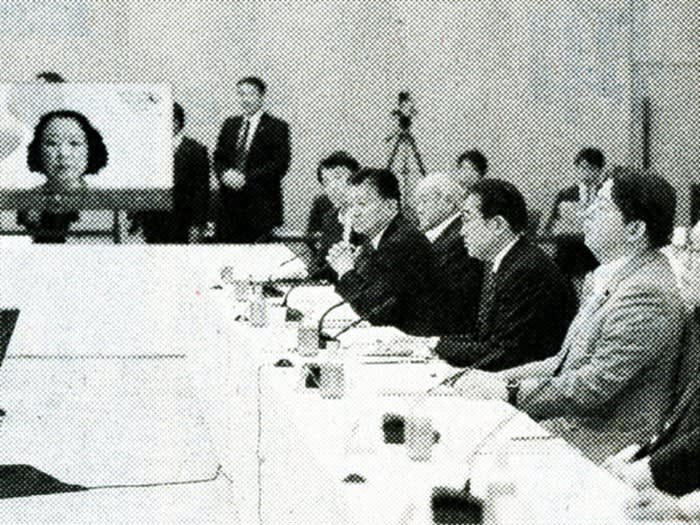
「新しい資本主義実現会議」に出席する岸田首相ら=5月9日(官邸ホームページから)
◆新しい資本主義実現会議の財界系構成員
◆同会議の労働組合代表の構成員
国際基準を逸脱
委員の1人、冨山和彦氏(経営共創基盤グループ会長)が「日本型ホワイトカラーは市場価値がない」と会議で暴言を吐いたことを前回紹介しましたが、彼はもっとひどい発言もしています。
「三位一体改革」を労政審(厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会)にもっていったら「5年~10年大きな変化はないと思ったほうがいい」「(なぜなら)3者構成の中身の問題」とのべています。労働者代表を対等に扱う労政審では、財界の思う通りに事が運ばないという意見です。
首相を議長とする政府の会議で、本来の審議ルールを攻撃するのは言語道断というべきです。3者構成の労政審を毛嫌いし、排除をとなえるこういう議論が財界や一部学者から相次いでいますが、軽視せずに批判していくことが大事だと思います。
日本では、労働政策の重要事項の審議は、労政審で行うと定められています(厚労省設置法第9条)。その委員は「労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する」(労働政策審議会令第3条)とされ、明確に3者同数と定められています。こういう原則をとっているのが政府内の他の審議会と大きく異なる点です。
3者構成原則はILO(国際労働機関)が定めている国際労働基準(第144号条約)です。日本は2002年に批准しています。なぜこういう原則があるかといえば、労働問題は労働者と使用者の利害が対立するので、使用者から一方的に不利な条件が労働者に押し付けられることがないようにするためです。
財界主導へ変質
ところがいまこれが形骸化され、財界主導へと変質しているのが実態です。転機になったのは、01年の省庁再編で官邸主導の政治にするという目的で内閣府が新設され、そのもとに経済財政諮問会議と規制改革会議(何度も名称変更)がつくられたことです。小泉純一郎政権は、財界主導で労働者代表がいないこの二つの組織で労働法制の改悪や規制緩和をすすめ、閣議決定で固めたあとに労政審の形式的な追認を求める方式をとりました。
安倍晋三政権では、所管の厚労省があるのにわざわざ働き方担当相を任命し、そのもとに財界中心の「働き方改革実現会議」を設置するという露骨な“労政審外し”のやり方をとりました。そこでの一方的な結論を経済財政諮問会議で確認して閣議決定にする手法です。今回の岸田政権の「三位一体改革」はそのやり方をまねたものといえます。
利害の一方の当事者である労働者の声を無視し、財界いいなりで事を運ぶ労働市場改革に批判の声をあげることが重要です。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年6月6日付掲載
「三位一体改革」の指針をまとめた「新しい資本主義実現会議」は、21人のメンバーのうち岸田文雄首相を含む大臣が6人、財界関係者が12人、学者が2人、連合会長が労働者代表で1人だけという構成で、過半数が財界関係者。
日本では、労働政策の重要事項の審議は、労政審で行うと定められています(厚労省設置法第9条)。その委員は「労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する」(労働政策審議会令第3条)とされ、明確に3者同数と定められています。こういう原則をとっているのが政府内の他の審議会と大きく異なる点。
安倍晋三政権では、所管の厚労省があるのにわざわざ働き方担当相を任命し、そのもとに財界中心の「働き方改革実現会議」を設置するという露骨な“労政審外し”のやり方を。今回の岸田政権の「三位一体改革」はそのやり方をまねたもの。

ジャーナリスト 昆弘見さん
政府の「三位一体の労働市場改革」は、決定過程に重要な問題があります。労働分野の政策は政府(公益)、労働者、使用者の3者対等の構成によって検討するというルールを無視してすすめられたことです。
「三位一体改革」の指針をまとめた「新しい資本主義実現会議」は、21人のメンバーのうち岸田文雄首相を含む大臣が6人、財界関係者が12人、学者が2人、連合会長が労働者代表で1人だけという構成で、過半数が財界関係者です。
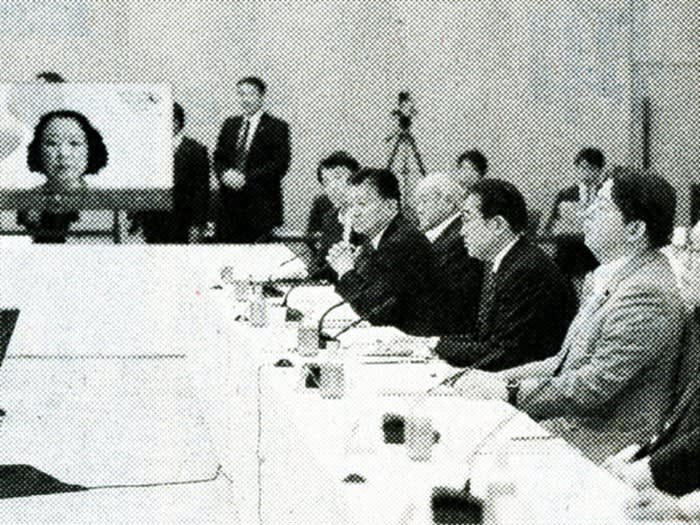
「新しい資本主義実現会議」に出席する岸田首相ら=5月9日(官邸ホームページから)
◆新しい資本主義実現会議の財界系構成員
| 翁 百合 | 日本総合研究所理事長 |
| 川邊健太郎 | LINEヤフー代表取締役会長 |
| 小林 健 | 日本商工会議所会頭 |
| 澤田 拓子 | 塩野義製薬副会長 |
| 渋澤 健 | シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役 |
| 諏訪 貴子 | ダイヤ精機社長 |
| 十倉 雅和 | 経団連会長 |
| 冨山 和彦 | 経営共創基盤グループ会長 |
| 新浪 剛史 | 経済同友会代表幹事 |
| 平野 未来 | シナモン共同最高経営責任者 |
| 村上由美子 | MPower Partnersゼネラルパートナー |
| 米良はるか | READYFOR最高経営責任者 |
| 芳野 友子 | 連合会長 |
国際基準を逸脱
委員の1人、冨山和彦氏(経営共創基盤グループ会長)が「日本型ホワイトカラーは市場価値がない」と会議で暴言を吐いたことを前回紹介しましたが、彼はもっとひどい発言もしています。
「三位一体改革」を労政審(厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会)にもっていったら「5年~10年大きな変化はないと思ったほうがいい」「(なぜなら)3者構成の中身の問題」とのべています。労働者代表を対等に扱う労政審では、財界の思う通りに事が運ばないという意見です。
首相を議長とする政府の会議で、本来の審議ルールを攻撃するのは言語道断というべきです。3者構成の労政審を毛嫌いし、排除をとなえるこういう議論が財界や一部学者から相次いでいますが、軽視せずに批判していくことが大事だと思います。
日本では、労働政策の重要事項の審議は、労政審で行うと定められています(厚労省設置法第9条)。その委員は「労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する」(労働政策審議会令第3条)とされ、明確に3者同数と定められています。こういう原則をとっているのが政府内の他の審議会と大きく異なる点です。
3者構成原則はILO(国際労働機関)が定めている国際労働基準(第144号条約)です。日本は2002年に批准しています。なぜこういう原則があるかといえば、労働問題は労働者と使用者の利害が対立するので、使用者から一方的に不利な条件が労働者に押し付けられることがないようにするためです。
財界主導へ変質
ところがいまこれが形骸化され、財界主導へと変質しているのが実態です。転機になったのは、01年の省庁再編で官邸主導の政治にするという目的で内閣府が新設され、そのもとに経済財政諮問会議と規制改革会議(何度も名称変更)がつくられたことです。小泉純一郎政権は、財界主導で労働者代表がいないこの二つの組織で労働法制の改悪や規制緩和をすすめ、閣議決定で固めたあとに労政審の形式的な追認を求める方式をとりました。
安倍晋三政権では、所管の厚労省があるのにわざわざ働き方担当相を任命し、そのもとに財界中心の「働き方改革実現会議」を設置するという露骨な“労政審外し”のやり方をとりました。そこでの一方的な結論を経済財政諮問会議で確認して閣議決定にする手法です。今回の岸田政権の「三位一体改革」はそのやり方をまねたものといえます。
利害の一方の当事者である労働者の声を無視し、財界いいなりで事を運ぶ労働市場改革に批判の声をあげることが重要です。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年6月6日付掲載
「三位一体改革」の指針をまとめた「新しい資本主義実現会議」は、21人のメンバーのうち岸田文雄首相を含む大臣が6人、財界関係者が12人、学者が2人、連合会長が労働者代表で1人だけという構成で、過半数が財界関係者。
日本では、労働政策の重要事項の審議は、労政審で行うと定められています(厚労省設置法第9条)。その委員は「労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する」(労働政策審議会令第3条)とされ、明確に3者同数と定められています。こういう原則をとっているのが政府内の他の審議会と大きく異なる点。
安倍晋三政権では、所管の厚労省があるのにわざわざ働き方担当相を任命し、そのもとに財界中心の「働き方改革実現会議」を設置するという露骨な“労政審外し”のやり方を。今回の岸田政権の「三位一体改革」はそのやり方をまねたもの。