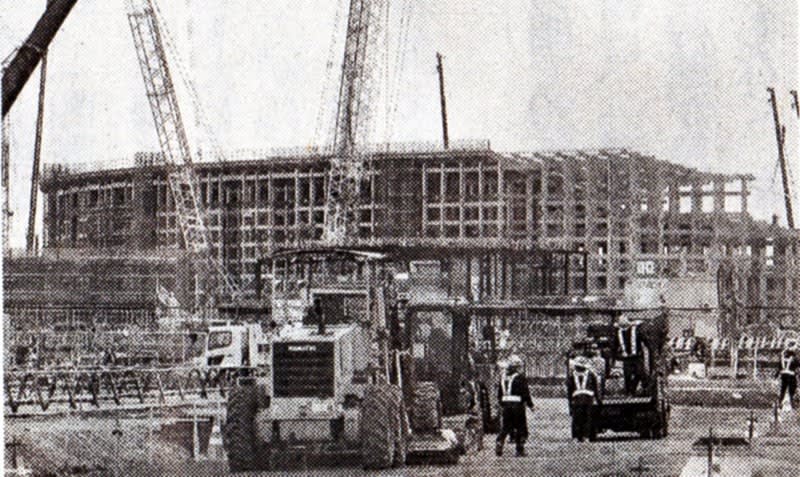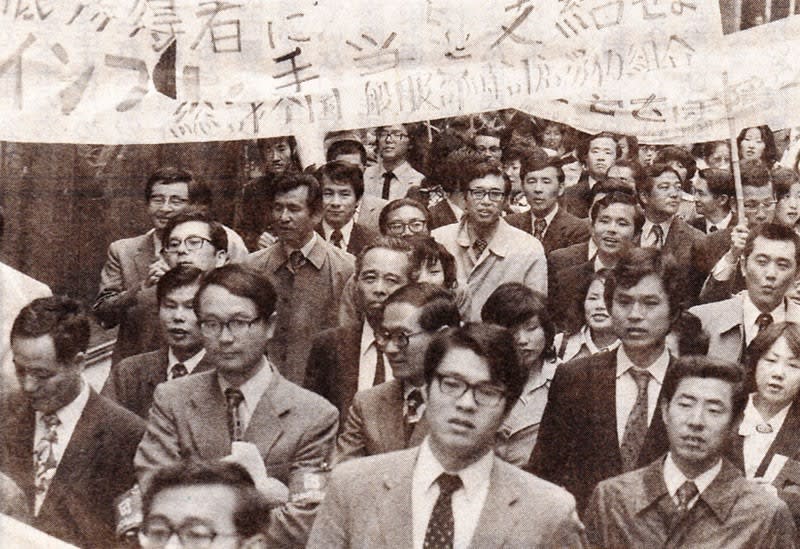関西財界と万博カジノ~その狙い③ 規制緩和の「実験場」に

「インフラ整備」とともに、「連名要望書」が強く求めたのは、「ソフト事業と大胆な規制改革」です。関西財界や維新府・市政にとって必要な「インフラ整備」への財政負担、支援を求めるとともに、彼らにとってじゃまな「規制」を「万博を実験場」にして取り除いてほしいというものです。
ソフト事業大胆に
「インフラ整備」が1回目の要望一発で「満額回答」を得たことから、2回目の「連名要望書」以後、もっぱら「ソフト事業と大胆な規制改革」に狙いを定めます。
「ソフト事業」では横文字だらけですが、「ライフサイエンス・ヘルスケア分野の研究開発等による健康長寿社会の実現」「大阪・関西万博を脱炭素社会のトップモデルケースとすることで、万博後の脱炭素ドミノに」「先端技術を駆使した『スマートシティ』の実現」などの文言が並びます。
そして、「ヘルスケアサービス創出」のためには「万博会場における生体認証やバイタルデータの取得に向けた制度整備等を進める必要」があるとか、「パビリオン内で取得したヘルスケアデータを基に、個人最適化された健康プログラムを提案」、「『空飛ぶクルマ』の万博会場内外における実証に向けた、各種規制緩和や手続きの簡素化・迅速化」など、あらゆる分野で徹底した「規制改革」を求めます。それこそ「未来社会の実験場」というわけです。

「空飛ぶ車」関連見学会で吉村府知事(左)と横山大阪市長(右)=2023年12月13日、大阪市此花区(大阪市HPから)
海外の規制も対象
「規制改革」は日本国内だけに限りません。今年1月の「連名要望書」では、「個人情報取扱に関して、海外規制のうち特に、強力とされるEUの規制について、適用除外や要件緩和などのためにEU規制当局との交渉」も求めています。
こうした関西財界の要望に対して、政府は2020年末に決めた「基本方針」で、「(空飛ぶクルマなど)実証プロジェクトにおいて、阻害要因となる規制があれば、大阪・関西万博を新たな技術及び新たなチャレンジを生み出す場とするために規制緩和等を積極的に進めていく」とうたいました。この点でも呼吸はぴったりです。
この「規制改革」のなかでも、おぞましいのが医療分野です。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年6月12日付掲載
2回目の「連名要望書」以後、もっぱら「ソフト事業と大胆な規制改革」に狙いを定めます。
「ヘルスケアサービス創出」のためには「万博会場における生体認証やバイタルデータの取得に向けた制度整備等を進める必要」があるとか、「パビリオン内で取得したヘルスケアデータを基に、個人最適化された健康プログラムを提案」、「『空飛ぶクルマ』の万博会場内外における実証に向けた、各種規制緩和や手続きの簡素化・迅速化」など、あらゆる分野で徹底した「規制改革」などなど。

「インフラ整備」とともに、「連名要望書」が強く求めたのは、「ソフト事業と大胆な規制改革」です。関西財界や維新府・市政にとって必要な「インフラ整備」への財政負担、支援を求めるとともに、彼らにとってじゃまな「規制」を「万博を実験場」にして取り除いてほしいというものです。
ソフト事業大胆に
「インフラ整備」が1回目の要望一発で「満額回答」を得たことから、2回目の「連名要望書」以後、もっぱら「ソフト事業と大胆な規制改革」に狙いを定めます。
「ソフト事業」では横文字だらけですが、「ライフサイエンス・ヘルスケア分野の研究開発等による健康長寿社会の実現」「大阪・関西万博を脱炭素社会のトップモデルケースとすることで、万博後の脱炭素ドミノに」「先端技術を駆使した『スマートシティ』の実現」などの文言が並びます。
そして、「ヘルスケアサービス創出」のためには「万博会場における生体認証やバイタルデータの取得に向けた制度整備等を進める必要」があるとか、「パビリオン内で取得したヘルスケアデータを基に、個人最適化された健康プログラムを提案」、「『空飛ぶクルマ』の万博会場内外における実証に向けた、各種規制緩和や手続きの簡素化・迅速化」など、あらゆる分野で徹底した「規制改革」を求めます。それこそ「未来社会の実験場」というわけです。

「空飛ぶ車」関連見学会で吉村府知事(左)と横山大阪市長(右)=2023年12月13日、大阪市此花区(大阪市HPから)
海外の規制も対象
「規制改革」は日本国内だけに限りません。今年1月の「連名要望書」では、「個人情報取扱に関して、海外規制のうち特に、強力とされるEUの規制について、適用除外や要件緩和などのためにEU規制当局との交渉」も求めています。
こうした関西財界の要望に対して、政府は2020年末に決めた「基本方針」で、「(空飛ぶクルマなど)実証プロジェクトにおいて、阻害要因となる規制があれば、大阪・関西万博を新たな技術及び新たなチャレンジを生み出す場とするために規制緩和等を積極的に進めていく」とうたいました。この点でも呼吸はぴったりです。
この「規制改革」のなかでも、おぞましいのが医療分野です。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年6月12日付掲載
2回目の「連名要望書」以後、もっぱら「ソフト事業と大胆な規制改革」に狙いを定めます。
「ヘルスケアサービス創出」のためには「万博会場における生体認証やバイタルデータの取得に向けた制度整備等を進める必要」があるとか、「パビリオン内で取得したヘルスケアデータを基に、個人最適化された健康プログラムを提案」、「『空飛ぶクルマ』の万博会場内外における実証に向けた、各種規制緩和や手続きの簡素化・迅速化」など、あらゆる分野で徹底した「規制改革」などなど。