独占パワー② 高利潤狙う強欲インフレ
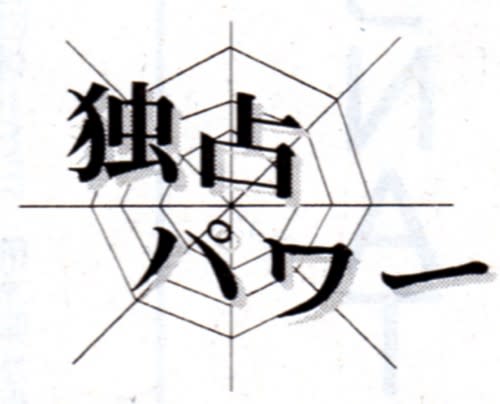
政治経済研究所 合田寛主任研究員
ひとたび独占パワーを獲得した巨大企業は、競争の圧力を受けないので、原価に対して高い利潤を上乗せした商品価格を設定することができます。いわゆる独占価格です。
主因は供給側に
原価に加えられる利潤のことをマークアップと言い、原価に対するその比率はマークアップ率と呼ばれます。マークアップ率の動きは独占化の程度を表す代表的な指標です。
1980年代以来、多くの国でマークアップ率の増大傾向が検証されています。米国の経済学者ジョセブ・スティグリッツ氏の最近の研究によると、60~80年にはマークアップ率はコストに対して平均で26%上回る水準を示していました。それ以降ゆっくりとコンスタントに上がり、2021年には72%に達しています。とくにコロナパンデミック以降、急激な上昇がみられます。
マークアップの引き上げは生産、流通、小売りの各段階で起こります。天然資源採掘部門(石油やガス)や農業部門(小麦やトウモロコシ)など、経済の上流部門で起きたマークアップの引き上げは、消費者に近い下流部門ではコストの引き上げとなって波及していきます。独占企業による市場支配率が高い部門ではコストを上回る値上げが起こります。
コロナパンデミックやロシアのウクライナ侵攻などによって、グローバルな供給ルートにボトルネック(障害)が生じました。それに便乗した値上げが、ボトルネック解消後まで続いているケースもあります。
いま世界で進行しているインフレーションの主な要因は、需要側の超過需要ではなく、供給側のマークアップの引き上げだと考えられます。それは「売り手インフレ」あるいは、もうけを増やすために価格を引き上げることから「グリードインフレ(強欲インフレ)」とも呼ばれています。
供給側の要因としては、利潤だけでなく賃金コストもあります。しかし、現在進行しているインフレーションについては、賃金要因よりも利潤要因が大きいことが多くの研究によって確かめられています。

米ニューヨーク州メルビルにあるアマゾンの倉庫で忙しく働く人たち=2023年7月11日(ロイター)
寄与比率が逆転
マサチューセッツ大学のイザベラ・ウェーバー氏らの研究によると、米国では粗付加価値に占める利潤と賃金の比率は、パンデミック以前の長い間、およそ44対56で安定していました。しかしパンデミック以降は比率が逆転し、利潤の寄与度が50台に上昇して、40台に低下した賃金を上回る事態となっています。
米国だけではありません。日本でも「強欲インフレ」が指摘されています。今年3月に発表された政策投資銀行のリポート(「『強欲インフレ』にみる賃上げへの期待」)は、インフレの要因を日本、米国、欧州に分けて分析しています。
リポートは、インフレの要因を賃金要因と企業収益要因に分解すると、近年、日、米、欧ともに企業収益要因が目立っており、企業の利潤拡大行動がインフレの持続性を高めていると指摘しています。とくに日本では23年以降、上昇要因のほとんどが企業収益の増加によるものだと分析しています。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年7月10日付掲載
原価に加えられる利潤のことをマークアップと言い、原価に対するその比率はマークアップ率と呼ばれます。マークアップ率の動きは独占化の程度を表す代表的な指標。
いま世界で進行しているインフレーションの主な要因は、需要側の超過需要ではなく、供給側のマークアップの引き上げだと考えられます。それは「売り手インフレ」あるいは、もうけを増やすために価格を引き上げることから「グリードインフレ(強欲インフレ)」とも。
マサチューセッツ大学のイザベラ・ウェーバー氏らの研究によると、米国では粗付加価値に占める利潤と賃金の比率は、パンデミック以前の長い間、およそ44対56で安定していました。しかしパンデミック以降は比率が逆転し、利潤の寄与度が50台に上昇して、40台に低下した賃金を上回る事態。
こういうのを便乗値上げって言うんですよね。
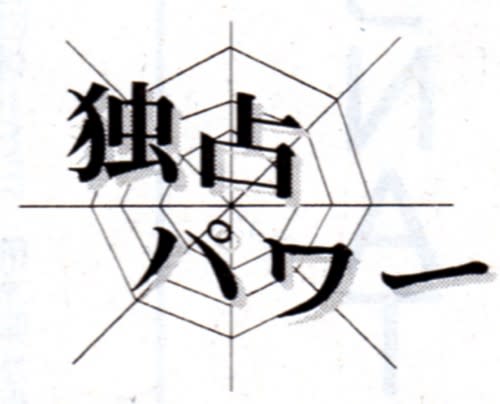
政治経済研究所 合田寛主任研究員
ひとたび独占パワーを獲得した巨大企業は、競争の圧力を受けないので、原価に対して高い利潤を上乗せした商品価格を設定することができます。いわゆる独占価格です。
主因は供給側に
原価に加えられる利潤のことをマークアップと言い、原価に対するその比率はマークアップ率と呼ばれます。マークアップ率の動きは独占化の程度を表す代表的な指標です。
1980年代以来、多くの国でマークアップ率の増大傾向が検証されています。米国の経済学者ジョセブ・スティグリッツ氏の最近の研究によると、60~80年にはマークアップ率はコストに対して平均で26%上回る水準を示していました。それ以降ゆっくりとコンスタントに上がり、2021年には72%に達しています。とくにコロナパンデミック以降、急激な上昇がみられます。
マークアップの引き上げは生産、流通、小売りの各段階で起こります。天然資源採掘部門(石油やガス)や農業部門(小麦やトウモロコシ)など、経済の上流部門で起きたマークアップの引き上げは、消費者に近い下流部門ではコストの引き上げとなって波及していきます。独占企業による市場支配率が高い部門ではコストを上回る値上げが起こります。
コロナパンデミックやロシアのウクライナ侵攻などによって、グローバルな供給ルートにボトルネック(障害)が生じました。それに便乗した値上げが、ボトルネック解消後まで続いているケースもあります。
いま世界で進行しているインフレーションの主な要因は、需要側の超過需要ではなく、供給側のマークアップの引き上げだと考えられます。それは「売り手インフレ」あるいは、もうけを増やすために価格を引き上げることから「グリードインフレ(強欲インフレ)」とも呼ばれています。
供給側の要因としては、利潤だけでなく賃金コストもあります。しかし、現在進行しているインフレーションについては、賃金要因よりも利潤要因が大きいことが多くの研究によって確かめられています。

米ニューヨーク州メルビルにあるアマゾンの倉庫で忙しく働く人たち=2023年7月11日(ロイター)
寄与比率が逆転
マサチューセッツ大学のイザベラ・ウェーバー氏らの研究によると、米国では粗付加価値に占める利潤と賃金の比率は、パンデミック以前の長い間、およそ44対56で安定していました。しかしパンデミック以降は比率が逆転し、利潤の寄与度が50台に上昇して、40台に低下した賃金を上回る事態となっています。
米国だけではありません。日本でも「強欲インフレ」が指摘されています。今年3月に発表された政策投資銀行のリポート(「『強欲インフレ』にみる賃上げへの期待」)は、インフレの要因を日本、米国、欧州に分けて分析しています。
リポートは、インフレの要因を賃金要因と企業収益要因に分解すると、近年、日、米、欧ともに企業収益要因が目立っており、企業の利潤拡大行動がインフレの持続性を高めていると指摘しています。とくに日本では23年以降、上昇要因のほとんどが企業収益の増加によるものだと分析しています。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年7月10日付掲載
原価に加えられる利潤のことをマークアップと言い、原価に対するその比率はマークアップ率と呼ばれます。マークアップ率の動きは独占化の程度を表す代表的な指標。
いま世界で進行しているインフレーションの主な要因は、需要側の超過需要ではなく、供給側のマークアップの引き上げだと考えられます。それは「売り手インフレ」あるいは、もうけを増やすために価格を引き上げることから「グリードインフレ(強欲インフレ)」とも。
マサチューセッツ大学のイザベラ・ウェーバー氏らの研究によると、米国では粗付加価値に占める利潤と賃金の比率は、パンデミック以前の長い間、およそ44対56で安定していました。しかしパンデミック以降は比率が逆転し、利潤の寄与度が50台に上昇して、40台に低下した賃金を上回る事態。
こういうのを便乗値上げって言うんですよね。
















