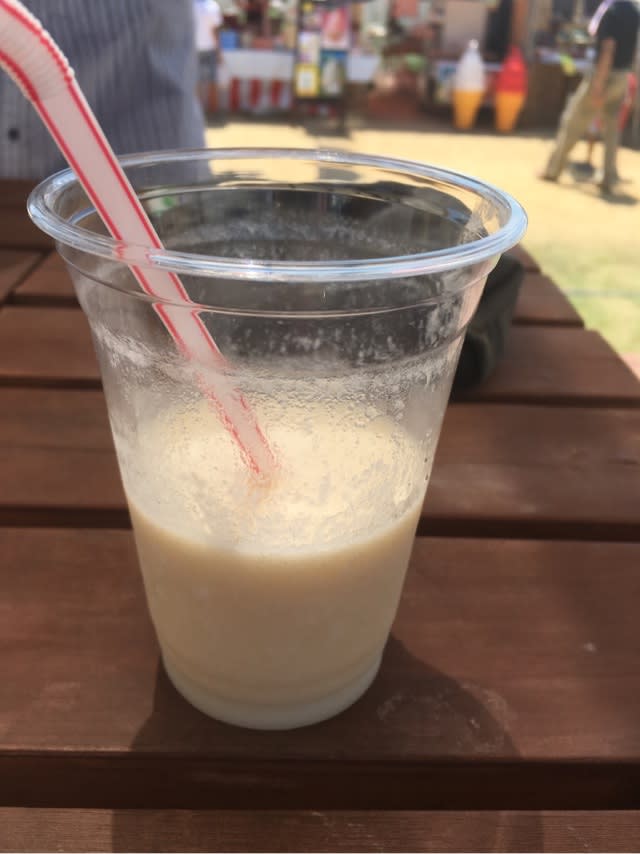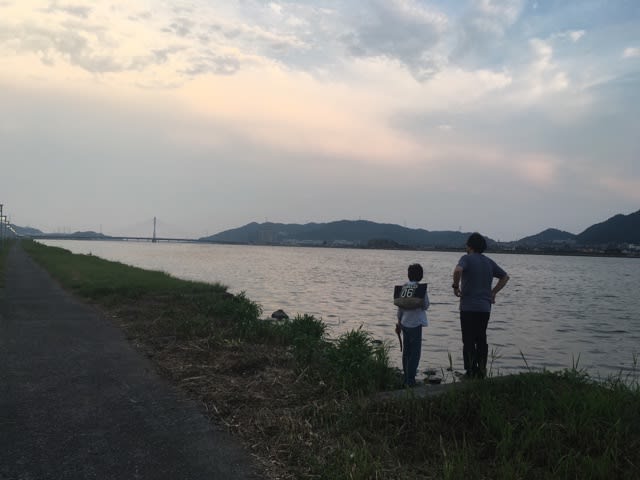お盆休みのど真ん中13日は、ピアノ合わせでした。
ピアニストの高橋美穂さんは、交野の方ですが、昨年から活動を東京に移されたので、お盆休みに帰ってこられる時を狙って伴奏合わせをお願いしました。

そうしたら今度は、ヴァイオリンの姪がドイツに先生のレッスンを受けに行ってしまい、3人で合わせられるのは当日の朝1回きりになってしまいました。
ドップラーのアメリカ、大筋は、姪とやってみたので、今回はその大筋を高橋さんに伝えます。
それからピアノが入ることで描けるブランに書き換えます。
後は、3人で、なんとかうまくいきそうです。
前にも1回私はやっていますが、ヴァイオリンパートをやっていたので、少し勝手が違います。また、フルート2本と、フルートとヴァイオリンのアンサンブルは、ずいぶん違います。
ハーモニーを、取れるのか?心配です。
まあ、自分の仕事をするのみです。
その後は、生徒さんたちとピアノ合わせです。
1日で、全てやるので、ピアニストは大変です。
ドビュッシーの月の光、Sさんは、本当に美しい音を出せるようになりました。
後はタンギングと少し苦手なリズムに乗る練習をするだけです。
リベルタンゴのE Sさんは、運指、音程が素晴らしいです。タンゴのリズム感で、全てを演奏することが課題です。
君をのせてのKさんは、初めてまだ半年。
間違えないで、初めから最後まで演奏できるようになりました。
後は、音がかすれないように、しっかり息を吹き込めるように練習です。
ドリゴのセレナーデMさん。
練習では、完璧なのに人前で吹くと緊張のあまりいろいろなことが起きます。
足をしっかりと床につけ、膝を曲げたり伸ばしたりして身体を意識して演奏することが、肝心です。
大丈夫。
みんな、前よりもずっと成長しています。
諦めないで、もっとよい演奏ができるように、練習、頑張りましょう!
私も、一生懸命、お手伝いさせていただきます。
ピアニストの高橋美穂さんは、交野の方ですが、昨年から活動を東京に移されたので、お盆休みに帰ってこられる時を狙って伴奏合わせをお願いしました。

そうしたら今度は、ヴァイオリンの姪がドイツに先生のレッスンを受けに行ってしまい、3人で合わせられるのは当日の朝1回きりになってしまいました。
ドップラーのアメリカ、大筋は、姪とやってみたので、今回はその大筋を高橋さんに伝えます。
それからピアノが入ることで描けるブランに書き換えます。
後は、3人で、なんとかうまくいきそうです。
前にも1回私はやっていますが、ヴァイオリンパートをやっていたので、少し勝手が違います。また、フルート2本と、フルートとヴァイオリンのアンサンブルは、ずいぶん違います。
ハーモニーを、取れるのか?心配です。
まあ、自分の仕事をするのみです。
その後は、生徒さんたちとピアノ合わせです。
1日で、全てやるので、ピアニストは大変です。
ドビュッシーの月の光、Sさんは、本当に美しい音を出せるようになりました。
後はタンギングと少し苦手なリズムに乗る練習をするだけです。
リベルタンゴのE Sさんは、運指、音程が素晴らしいです。タンゴのリズム感で、全てを演奏することが課題です。
君をのせてのKさんは、初めてまだ半年。
間違えないで、初めから最後まで演奏できるようになりました。
後は、音がかすれないように、しっかり息を吹き込めるように練習です。
ドリゴのセレナーデMさん。
練習では、完璧なのに人前で吹くと緊張のあまりいろいろなことが起きます。
足をしっかりと床につけ、膝を曲げたり伸ばしたりして身体を意識して演奏することが、肝心です。
大丈夫。
みんな、前よりもずっと成長しています。
諦めないで、もっとよい演奏ができるように、練習、頑張りましょう!
私も、一生懸命、お手伝いさせていただきます。