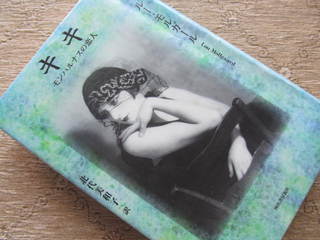出光美術館でお祭りが始まった。ほんとは初日に行く予定だったが、かなわず、祭も佳境に達する10日目にみてきた。もう少し、お客で溢れているかと思ったが、そうでもなく、うれしい誤算だった。だから、ゆっくりと、しげしげと観ることができ、タイムスリップして江戸時代の、祇園祭と浅草三社祭を見学しているような気持ちになった(汗)。
京都の祇園祭と浅草の三社祭は、最近、ほぼ、毎年欠かしたことがない(汗)。今年の祇園祭は、ほかのお祭りに行くので、3年振りくらいにパスするが、来年は行く予定。昨年は山鉾だけでなく神幸祭の神輿渡御も観た。三社祭は、この5月、三基の本社神輿の早朝宮出しも観たし、3月には700周年記念として行われた、54年ぶりの舟渡御も見学した。えへん、えへん。
まず、祇園祭。メーンステージに飾られた”祇園祭札図屏風”(桃山時代)。右隻に山鉾巡行、左隻には神幸祭の神輿が。天上の雲間から祭りの様子を描く構図。狩野派の作だといわれている。家屋には人がいないし、路上にも見物人があまりいない。山鉾を引っ張る人、神輿を担ぐ人を中心に描いている。見物人はぼくらでいいのだ。
さて、長刀鉾はどこか、函谷鉾は、山伏山は、と探してみる。左の壁に、山鉾の位置を示しているパネルがあることに気付いた。屏風の縦の3本の通りは、三条、四条、五条、奥の横道が寺町通り。その図をノートに写し取り、屏風絵と比較してみる。それがまた楽しい。矛先は桃山でも江戸時代でも変わってないだろうからと、長刀の矛先をもつ鉾はすぐみつかる。月をもつ鉾は函谷鉾か月鉾だ。正面にいるのは、舟形をした船鉾と山伏山と菊水鉾。左隻には、おなじみの三基の神輿が渡御している。それぞれ、中御座(六角形/スサノヲノミコト)、東御座(四角形/クシイナダヒメノミコト;スサノヲの奥さん)、西御座(八角形/ヤハシラノミコガミ;夫妻の子供)である。ついでながら三社の神輿も江戸時代は祇園のまねをした多角形の神輿だったとのことだ。
洛中洛外図屏風(江戸、元和期、紙本金地着色)は、祇園祭以外の風俗も描いてある。右隻には長刀、山伏、函谷の三つの山鉾の巡行。辻回しをしているような鉾もある。半裸の男が引っ張っている。祇園社(八坂神社)や清水寺もみえる。鴨川では水浴びをしている裸の女や子供たち。歌舞伎小屋も楽しそうだ。左隻には祇園社の三基の神輿巡行、賀茂のくらべ馬も。北野天満宮もある。
祇園祭札図屏風(江戸、元禄期)は、22基の山鉾勢ぞろい。先頭の長刀鉾から始まって、5番目くらいに函谷鉾、そして鶏鉾、月鉾も見つけて、あっ、あれはなんだ、なんだかカマキリのような飾りが。ひょっとして、ぼくの一番、愛する蟷螂山ではないか。ついでながら、蟷螂山は、14世紀後半の南北朝時代に、薬や菓子で有名な”ういろう”を始めた外郎(ういろう)氏がつくったのだ。外郎家はその後、小田原に移り、現在も家が存続している。小田原訪問記はずっと前、記事にしている。念にため前述のパネルに戻り、確認してみる。間違いなかった。タイムスリップして江戸の蟷螂山と会えるとは、感無量でごわす。今期は左隻のみの展示で、みられなかった可能性もあったのだ、よかったどす。
次は三社祭。”江戸名所図屏風”(江戸、寛永期)上野から品川までの江戸名所の賑わい。楽しんでいる人々がいっぱいで、こっちまで楽しくなってしまう。三社祭は、ななななんと、舟渡御の場面。隅田川から神輿を引き上げている。先のふたつの神輿は陸上ですでに渡御をはじめている。神田明神の神事能の舞台のほか、人形浄瑠璃の操り小屋、木挽町周辺の歓楽街、湯女風呂とか、江戸の庶民が楽しんだ”悪所”も描かれている。江戸風俗図屏風は右隻のみ前期展示。
展示構成は、
第一章”祭の前夜/神が舞い降りる各所、第二章”祭が都市をつくる/京都 江戸、第三章”祭の名残/遊楽の庭園、第4章”遊楽/閉ざされた遊び”
江戸、第三章”祭の名残/遊楽の庭園、第4章”遊楽/閉ざされた遊び”となっている。前述の祇園祭、三社祭関係は、1,2章で扱われている。3章には”邸内遊楽図屏風”など、どこを描いたものかが分からない遊里の絵、それと岩佐又兵衛の”職人尽図鑑”の展示もうれしかった。4章では歌舞伎や浄瑠璃関係。それぞれ、楽しめた。そうそう、草間弥生風の(笑)色絵狛犬の二匹、可愛かったことも付け加えておこう。柿右衛門作だそうだ。
おわりに、現代の祭りの様子も入れて、画面上で、お祭り騒ぎをもう一度。絵ハガキとぼくの写真から。
”祇園祭札図屏風”(桃山時代)山伏山と菊水鉾か。

神幸祭、神輿巡行2011年7月祇園祭

菊水鉾 2011年7月祇園祭

蟷螂山 2011年7月祇園祭

”江戸名所図屏風”(江戸、寛永期)三社祭、舟渡御

700周年記念三社祭舟渡御 2012年3月

三社祭 2012年5月

”江戸名所図屏風”(江戸、寛永期) 木挽町周辺の歓楽街


ああ、楽しかった。後期、もう一度、行きたい。










 江戸、第三章”祭の名残/遊楽の庭園、第4章”遊楽/閉ざされた遊び”となっている。前述の祇園祭、三社祭関係は、1,2章で扱われている。3章には”邸内遊楽図屏風”など、どこを描いたものかが分からない遊里の絵、それと岩佐又兵衛の”職人尽図鑑”の展示もうれしかった。4章では歌舞伎や浄瑠璃関係。それぞれ、楽しめた。そうそう、草間弥生風の(笑)色絵狛犬の二匹、可愛かったことも付け加えておこう。柿右衛門作だそうだ。
江戸、第三章”祭の名残/遊楽の庭園、第4章”遊楽/閉ざされた遊び”となっている。前述の祇園祭、三社祭関係は、1,2章で扱われている。3章には”邸内遊楽図屏風”など、どこを描いたものかが分からない遊里の絵、それと岩佐又兵衛の”職人尽図鑑”の展示もうれしかった。4章では歌舞伎や浄瑠璃関係。それぞれ、楽しめた。そうそう、草間弥生風の(笑)色絵狛犬の二匹、可愛かったことも付け加えておこう。柿右衛門作だそうだ。









 同じ日、松坂、6回途中まで1失点の好投ながら、勝ち星がつかず、今季初勝利、メジャー通算50勝は、またお預けとなった。しかし、復活のきざしは十分、みせてくれた。後半戦で一気に10勝だ。
同じ日、松坂、6回途中まで1失点の好投ながら、勝ち星がつかず、今季初勝利、メジャー通算50勝は、またお預けとなった。しかし、復活のきざしは十分、みせてくれた。後半戦で一気に10勝だ。

 祇園祭りに三社祭、たっぷり楽しんで(感想文は明日)、東御苑に。
祇園祭りに三社祭、たっぷり楽しんで(感想文は明日)、東御苑に。











 上野のパンダは赤ちゃんができたらしい
上野のパンダは赤ちゃんができたらしい






























 方丈前の3メートル四方の芝生の一画が、ネジバナの生息地。普通のお寺さんなら、雑草として抜かれてしまっているかもしれない。ネジバナフアンとしてはありがたいことだ。では早速、ちょっとひねくれた、ネジバナ嬢のお写真を。
方丈前の3メートル四方の芝生の一画が、ネジバナの生息地。普通のお寺さんなら、雑草として抜かれてしまっているかもしれない。ネジバナフアンとしてはありがたいことだ。では早速、ちょっとひねくれた、ネジバナ嬢のお写真を。








 (ねずみも安心)
(ねずみも安心)