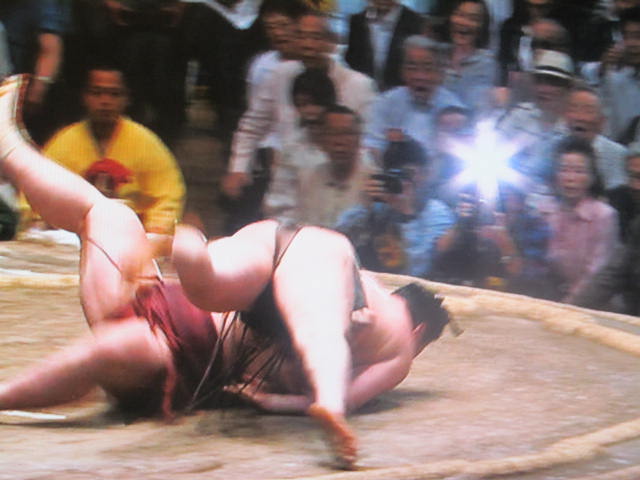ルネッサンス盛期の三代巨匠、レオナルドダビンチ、ミケランジェロそしてラファエロ。そのひとりの画家の展覧会を観ることだけだって大変な幸せなのに、ふたりの画家の展覧会を二つも同日に観られるなんて、度を過ぎた幸せ、極上の幸せだと思わなければならない。ぼくは、それを昨日、上野で達成し、大満足して帰ってきたノデアル。
西美のラファエロ展は、いよいよ終幕に近づき、すでに一度鑑賞しているが、同時鑑賞という偉業を達成するには、もうこの日しかないと、そぼ降る雨の中を出掛けたのであった。長蛇の列を予想していたが、お天気の悪さが幸いして、なんと15分待ちで済む。ラファエロの作品が世界の有名美術館から23点も上野に集結した、最上級の展覧会。二度目であっても、もちろん、同じ感動。もう生涯、見られないと思うと(汗)、よけいに聖母や幼児キリストがいとおしくなる。感想文は1回目に書いているので、ここでは省く。
さて、都美の”レオナルドダビンチ展”。こちらは、はじめて。レオナルドのデッサン(手稿)はたくさんあるが、彼自身の本画はたったひとつしか展示されていない。でも、ひとつだけでも、大変なこと。なぜなら、レオナルドは生涯、ほとんどデッサンばかり描いて、完成品は17,8程度しかない。分母が少ないのだからしょうがない。それに”音楽家の肖像”は彼が描いた唯一の男性の肖像画という貴重な絵画である。
自慢になるから言わないでおこうと思ったが、やっぱり言ってしまおう(爆)。2011年11月に観た、ロンドンナショナルギャラリーでの空前絶後(たぶん)のレオナルドダビンチ展を思い出す。なんとレオナルド作品の内、半数の9点が集結したのだ。その中のひとつに、アンブロジアーナ図書館から”音楽家の肖像”が来ていた。だから、再会ということになる。そのときは、白貂(てん)を抱く貴婦人、ミラノ宮廷婦人の肖像、聖母子と聖アンナと聖ヨハネ、岩窟の聖母2点、救世主キリスト、聖ヒロニムス、リッタの聖母が来ていたが、いずれおとらぬ名画ばかりで、むしろ楽士は、目立たない存在だった。
そのときのことを思い出しながら観ていたが、レオナルド派たちの作品の中に、”ロンドン作品”の面影を感じ、楽しめた。まず、はじめに出てきた、ロンバルディア地方のレオナルド派の画家による”貴婦人の肖像”。レオナルド自身の作品ではないかと思わせるほどの存在感。何とモデルは、(ぼくがロンドンで一番気に入っていた作品)”白貂を抱く貴婦人”と同じ人という説が有力らしい。そういえば、似ている。ミラノ宮廷婦人の肖像にも少し似ているけど。うれしい出会いだった。そして、ヴェスピーノによる、同名の”岩窟の聖母”。ルーブルとロンドンNGの岩窟の聖母が並べられた展示室を想い出す。そして、アンドレア・ソラーリオの”悔悛の聖ヒロニムス”。
そして、”音楽家の肖像”のある、メイン会場では、レオナルドの影響を受けたレオナルデスキと呼ばれた画家たちによる作品がずらり。ベルナルディーノ・ルイーニ(本名ベルナルディーノ・スカーピ)の”幼子イエスと子羊”。ロンバルディア地方のレオナルド派の画家による”洗礼者聖ヨハネ”。これは、模写としては最初のものだといわれているそうだが、本物は昨年、ルーブルで観ている。
というわけで、これだけでも、十分、楽しませてもらったが、アンブロジアーナ図書館からの、”アトランティコ手稿”も興味深く観させてもらった。天才レオナルドの面目躍如、古典絵画、人物のデッサンから始まり、光学、幾何学、建築、兵法、機械、装置、人体飛行などのノートも。この種のものは、以前の展覧会でもみているので、驚かないが、改めて、天才レオナルドの大きさを知る。
レオナルドダビンチ展とラファエロ展を同日に観た幸せをしみじみ味わってきたでござんす。もし福井で間もなく始まるミケランジェロ展が、今の時期に開催されていたならば、三大巨匠展、同日制覇というギネスブック級の記録を達成できたのに残念だ。その場合は飛行機を使えば可能だということも計算している(汗)。美術展の盛んな日本だからできる離れ業。日本人に生まれて良かった。
さようならラファエロ

こんにちわ 再会レオナルド

楽士と貴婦人の肖像と


レオナルド派の作品


上野はさつき展で賑わっていた。さつきは植物界のレオナルド。モナリザもいれば楽士もいる。

パンダは動物界のラファエロ。今度は幼児パンダを抱いたお姿、お願いします。













 明日、東慶寺に行ってみよう。
明日、東慶寺に行ってみよう。












 明日、東慶寺に行ってみよう。
明日、東慶寺に行ってみよう。