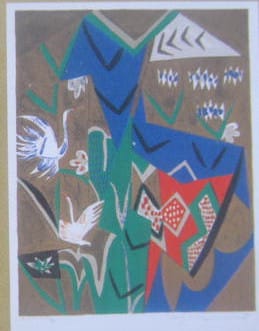こんばんわ。今日は、街中でハローウィンの仮装が目立ちましたね。さて、二、三日前の話です。
建築意匠がご専門の松崎先生の”鎌倉と横浜の建築再発見”の第二回目の講義を聞いたあと、久しぶりに常楽寺を訪ねた。講義のはじめに、熊本県、人吉・球磨地方の城泉寺の阿弥陀堂の写真がスクリーンに現れ、みなさん、これをみて、どこかで見たことありませんかと尋ねられた。それが、大船の地名の由来ともなった粟舟山・常楽寺の仏殿のことだった。
実は、鎌倉には鎌倉時代の寺社建造物はひとつも残っておらず(国宝の円覚寺舎利殿も室町前期)、なんと、遠く離れた、熊本県の人吉・球磨地方に二寺、残っているのだそうだ。
ぼくは、寺社巡りは好きな方だが、目的は境内の四季折々のお花見が主で、寺社の建築様式には余り関心を示さなかった。今回の公開講座を受講したのは、そちらの方面のことも、ちょっと知りたいと思ったからだ。
歩いて、10分ほどの、夕暮れの常楽寺に行き、仏殿と、隣りの茅葺の文殊堂などの写真を撮ってきた。そして、帰ってから、前述の熊本の城泉寺と青蓮寺の阿弥陀堂と比べてみた。
まず、熊本の二つのお寺の写真。熊本県広報課のホームページよりお借りした。
城泉寺(浄心寺)の阿弥陀堂。上球磨の豪族、久米氏の菩提寺として、鎌倉時代初期に建立された。現在、阿弥陀堂だけが残っている。昔は浄心寺と呼ばれたが、現在は城泉寺と呼ぶ。県内最古の寺で国指定重要文化財。主尊の阿弥陀如来、脇侍として観音菩薩と勢至菩薩を祀る。所在地は、球磨郡湯前町。
青蓮寺。源頼朝の命で、1198年、遠州から相良長頼がこの地に着任し、以後相良氏が700年間、統治した。鎌倉時代後期の永伝3年(1295年)に建立。本堂(阿弥陀堂)は県下最大のもの。五間四面の茅葺屋根。阿弥陀如来像と両脇侍が祀られている。国指定重要文化財。所在地は、球磨郡多良木町。
そして、我が常楽寺の仏殿。江戸・元禄四年(1691)の建立。桁行き(正面)、梁行き(奥行)とも三間。内部は、土間に鎌倉石を敷き詰め、厨子をおき、そこに阿弥陀如来坐像と勢至菩薩と観世音菩薩が祀られている。江戸時代の建造物とはいえ、以前の建築様式は踏襲している。開山は退耕行勇(1163-1241)、開基は北条泰時(1183-1242)で、嘉禎三年 (1237) に、泰時が義母 の追善供養のためにお堂を建てたのが始まりという。泰時が亡くなると、ここに葬られ、泰時の法名が常楽院殿観阿であることから、寺の名前を常楽寺としたようだ。

常楽寺の仏殿は、現在茅葺ではないが、いずれも、阿弥陀堂建築の特長である、正方形の平面で、屋根も三角の四面で、熊本県の二寺とよく似ている。そして、いずれも、阿弥陀三尊が祀られている。
その隣りには、茅葺の文珠堂がある。建物は明治のはじめに英勝寺から、移したもの。道隆が宋から持ってきたという文珠菩薩が祀られている。
この寺には鎌倉市内最古の(1248年作)の銅鐘があるが、国の重要文化財として、現在は鎌倉国宝館で保存されている。
裏に廻ると、北条泰時のお墓がある。第三代執権、泰時は、承久の変(1221)を抑え、貞永元年(1232)には”関東御成敗式目”を制定したことで知られる。
さらに裏山を登ると、頼朝に処刑された、木曽義仲の嫡子、 義高の墓(木曽塚)と、義高を慕い、若死にした頼朝と政子の娘、大姫のお墓がある。こちらに越してきたとき、偶然、これらを見付け、驚いた。ブログ記事にもしたような気がする。
こうして、見慣れたお寺だが、角度を違えて、観察するのも、面白いものである。
常楽寺の山門