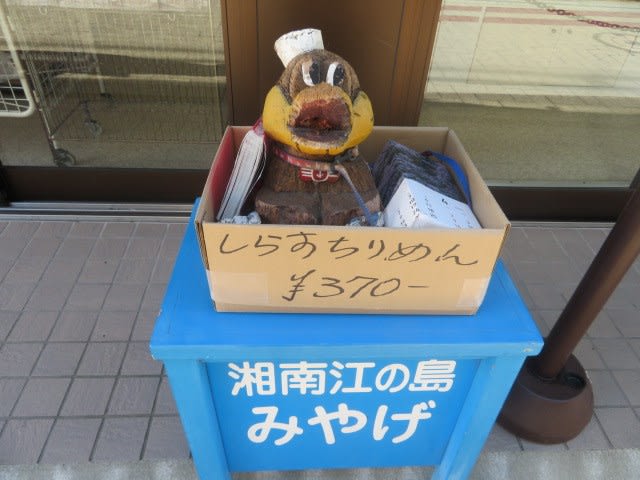徒然草はぼくの好きな古典のひとつ。気が向いたときに開いてみるが、それは、自分の好きな段の文章だけ。全段を通して一度、読んでみたいなと思っていたら、恰好の公開講座があることを知った。近くの大学で、徒然草の全243段を20回かけて読むという講座だ。講師の方も、和辻哲郎の孫弟子に当たる、著名な竹内整一先生。先々週から受講している。せっかくだから、今後、本ブログにも、なるほどと感心した段を記録しておこうと思う。
今回は12段と13段。最近、友人たちと談笑する機会が数回つづいた。心おきなく話せる人もいれば、多少、遠慮が入る人もいる。そういうような話題である。
はじめに原文を。
12段
おなじ心ならん人としめやかに物語して、をかしき事も、世のはかなき事も、うらなく言ひ慰まんこそうれしかるべきに、さる人あるまじければ、つゆ違(たが)はざらんと向ひゐたらんは、ひとりある心地やせん。
たがひに言はんほどの事をば、「げに」と聞くかひあるものから、いささか違う所もあらん人こそ、「我はさやは思ふ」など争ひ憎み、「さるから、さぞ」ともうち語らはば、つれづれ慰まめと思へど、げには、少しかこつかたも、我と等しからざらん人は、大方(おおかた)のよしなしごと言はんほどこそあらめ、まめやかの心の友には、はるかに隔たる所のありぬべきぞ、わびしきや。
訳文(島内裕子訳をもとに)
同じ心の人としみじみと話しをして、興味深いことも、世の中のはかないことも、裏表なく話しあったら、どんなに心が慰められようが、そういう人は、身の回りにはいないから、相手に話しを合わせて向かい合うのは、孤独で、まるでひとりでいるようだ。
お互いに、言いたいことがあるならそれを言い合い、なるほどと聞きがいがあるものの、少しは意見が違うこともある。そういうときに、わたしはそうは思わない、などと言って、反論し、”だから、こうでね”などと打ち解けて語り合えるなら、つれずれの退屈な倦怠感も慰められるというものだ。だが、実際に、自分と同じように、現実に対して少し不満感をもつ人がいても、その人は自分とは別人格であるから、世間のつまらぬおしゃべりくらいなら良いが、本当の心の友というには、はるかに隔たっているのが、なんともわびしいものなのだ。
そして、次の段に。
13段
ひとり灯のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。文は文選のあはれなる巻々、白氏文集、老子のことば、南華の篇。此の国の博士どもの書ける物も、いにしへのは、あはれなること多かり。
ひとり、灯火のもと、本を拡げ、見ぬ世の人を友とするくらい、無上の慰めはない。本といえば、文選、白氏文集、老子、南華の篇(荘子)。日本の文章博士たちが書いたものも、昔のものは、しみじみと心に沁みることが多い。
現実の中ではなかなか心の友を見つけることはできないが、古人の書物の中では心の友は容易に見付けることができる、と兼好法師は言っている。
ぼくの心の友は、書物の中だけではなく、ここにもいます。
富士山


そして、お月さま。

























 とうさん一番(1031)。
とうさん一番(1031)。