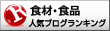十八粥の日とは、陰暦正月18日に食べる小豆粥にに餅花や団子を入れて作る日のことです。この日は、元三大師(がんざんだいし)の供供養にちなんでいます。元三大師は、中国の禅宗の開祖で、、魔除けの力があると信じられています。十八粥を食べると、ヘビやムカデなどの害虫から身を守るという伝説があります。
十八粥は、小正月15日に作った小豆粥にに餅花や団子を加えてて煮込みます。餅花は、小さく切ったた餅や団子を木に刺して飾ったもので、団子は、小豆粥に入れたものです。十八粥は、朝食として食べますが、昼間にも温めて持ち運ぶことができます。
十八粥は、中国では「十八粥」と呼ばれますが、日本では「十八日」と呼ばれることもあります。また、「大師粥」や「年賀」などとも言われます。十八粥の日は、新年を迎える前に家族や親戚と一緒に食べることで、幸せや健康を願う風風習があります。