

今日、1月17日は阪神淡路大震災の日です。この大震災では、食べ物もなく不安のどん底にいた被災者が、ボランティアによる炊き出しの「おむすび」に助けられました。
人と人とを結ぶ「おむすび」の大切さ、「おむすび」の温もりを忘れない日、また、身近な食べ物「おむすび」を見直し、「ご飯食の推進」をPRする日として、「ごはんを食べよう国民運動」推進協議会が制定を提案、平成12年に、この記念日が制定されました。
あらためてボランティアの善意、食料や危機管理の大切さを考え直していただけたらと思います。


今日、1月17日は阪神淡路大震災の日です。この大震災では、食べ物もなく不安のどん底にいた被災者が、ボランティアによる炊き出しの「おむすび」に助けられました。
人と人とを結ぶ「おむすび」の大切さ、「おむすび」の温もりを忘れない日、また、身近な食べ物「おむすび」を見直し、「ご飯食の推進」をPRする日として、「ごはんを食べよう国民運動」推進協議会が制定を提案、平成12年に、この記念日が制定されました。
あらためてボランティアの善意、食料や危機管理の大切さを考え直していただけたらと思います。


たくあんは、日本の伝統的な漬物であり、栄養価もあります。たくあんの主な栄養素には次のようなものがあります。
ただし、塩分も多く含まれているので、食べ過ぎにはご注意を!
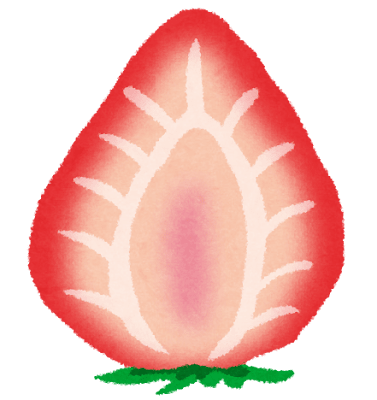

いちごの選び方のポイントをいくつかご紹介します。
これらのポイントを参考に、美味しいいちごを選んでください 🍓

1月12日は「いいにんじんの日」です。高麗人参が健康に良いことをアピールするために株式会社韓国人参公社ジャパンにより制定されました。
1と12で「いいにんじん」と読む語呂合わせと、2012年のこの日に、同社の設立記念パーティーが開かれたことから、この日になりました。

鏡開きは日本の伝統行事で、お正月の飾り物として使用した鏡餅を開いて食べる日です。鏡開きは地域によって異なりますが、一般的には1月11日に行われます。この行事は、お正月に神様や先祖を迎えるための鏡餅を食べて、一年の無病息災を祈る意味があります。
鏡餅を小さく砕いて雑煮やお汁粉などにしていただくのが一般的です。この儀式には「切る」という言葉を避け、「割る」や「開く」という言葉を使うことで縁起を担いでいます。😊


1月10日は「かんぴょうの日」です。かんぴょうは漢字で「干瓢」と書き、「干」の字を分解すると「一」と「十」になることから、栃木県干瓢商業協同組合が制定しました。
ユウガオの果実を紐状に剥き、乾燥させて作る乾燥食品「かんぴょう」は、栃木県の特産品で全国生産量98%以上を占めています。消費拡大の願いを込めてこの日を記念日にしています。


春の七草とは「セリ・ナズナ・ゴギョウ(ハハコグサ)・ハコベラ(ハコベ)・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)」です。この七草をお粥にして1月7日に食べる七草粥の習慣は、江戸時代に広まったそうです。
七草は、早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うといわれました。そこで、無病息災を祈って七草粥を食べたのです。古くはまな板の上で、草をトントン叩いて刻むその回数も決められていたとか。こんな、おまじないのような食べ方も素敵ですが、実はこの七草粥、とても理に叶った習慣です。
七草はいわば日本のハーブ、そのハーブを胃腸に負担がかからないお粥で食べようというのですから、正月疲れが出はじめた胃腸の回復にはちょうどよい食べものです。また、緑が不足しがちなお正月、滋養豊かな七草でクッキングしてみませんか。


1月6日は「ケーキの日」です。1879年(明治12年)のこの日、東京・上野の風月堂が日本初のケーキの宣伝をしたとされることにちなんでいます。
新聞に掲載された広告の内容は、「文化は日々開けていき、すべてのものが西洋風になってきていますが、ただ「西洋菓子(ケーキ)」をつくっている人はいません。そこで当店では外国から職人を雇ってケーキをつくり、博覧会へ出品したところ大好評でした。ぜひご賞味ください」というものでした。
関連する記念日として、カレンダーで22日の真上には15日があり、ショートケーキの上には苺(イチゴ)がのっていることから毎月22日は「ショートケーキの日」となっています。🍰

店頭にてレシピ差し上げています。

米粉、上新粉もあります。どうぞ、お越しください。
本年もどうぞよろしくお願いします!